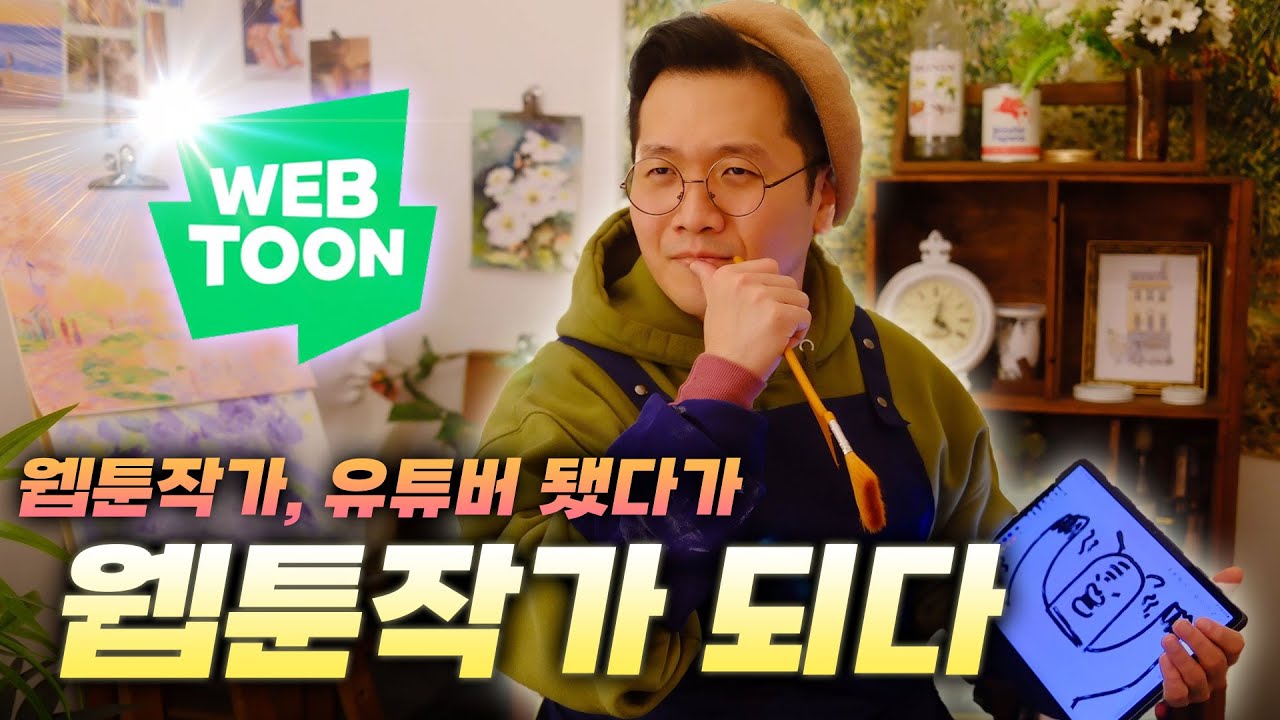
『ジンドルヒディ漫画』 - ジンドル、ヒディ
オ・ミンジ:美大受験生、美大生、塗色兵、ウェブトゥーン作家が、実は「色弱」だった!? これの事実の主人公「ジンドル」は、一週間かけて一生懸命描いた漫画を通じて読者とコミュニケーションを取る人生から一歩進み、配信を通じて直接読者とコミュニケーションする人生も同時に選んだウェブトゥーン作家兼ユーチューバーだ。配信中の「エピソード」によって「オタク」であることが世間に知られることになったが、むしろオタク力は「私の真髄、私の根幹、私の希望、私の自慢!! この空の下で私は一点の恥もない!!」と叫ぶ妻「ヒディ」もまたウェブトゥーン作家だ。色弱の夫とオタクの妻。このウェブトゥーン作家夫婦の日常漫画『ジンドルヒディ漫画』は個人配信のエピソードを、丸みを帯びた絵柄と台詞によって彼らが最も得意なもう一つの形式であるウェブトゥーンで描き出した作品だ。どこに行ってもカバンを背負わないと心が安定しない「行商人症候群」、虫をひどく怖がって、自分の人生は一寸先も見えないものの遠くにいる虫はよく見える「夏恐怖症」、夜に主に活動する「夜人間」のサラダは、夜中3時にデリバリーできる食べ物の中で最も野菜をとれるチョッパル&ポッサムセットで、夜食は朝限定メニューの「朝マック」だというエピソードなどは、小さなユーモアであり読者たちが共感するポイントだ。
『ジンドルヒディ漫画』は、お互いを知りすぎるほどよく知っているが、同時に「本当に、非常に、深刻にまったく合わないパズル」である2人がそれぞれの好みを徐々に相手に「中毒」させていく日常で、毎回漫画のように様々なことが起きなくても、単調な日常の中で楽しいことを観察すれば、いくらでもセンスのある漫画を描くことができると証明している。また、ウェブトゥーンの週1回連載が物足りないなら、いつでも個人配信を通じて作家と直接やりとりすることもできる。ウェブトゥーンと個人配信を通じたコミュニケーション。「色弱、美大に行く」編の「どう努力しても克服できないハンディキャップと共に生きて悟ったことは、できないことを上手くやろうと努力するより、できないと思うことはどうにか避けて通って、偶然ちょっと上手くできることを一つ発見できたら、最大限にそれらしく見えるようにラッピングして、それなりの適応をしてきたんだと思う」という独白のように、上手くできる何かを探し、より上手くできるように努力した作家だけに可能なことだ。
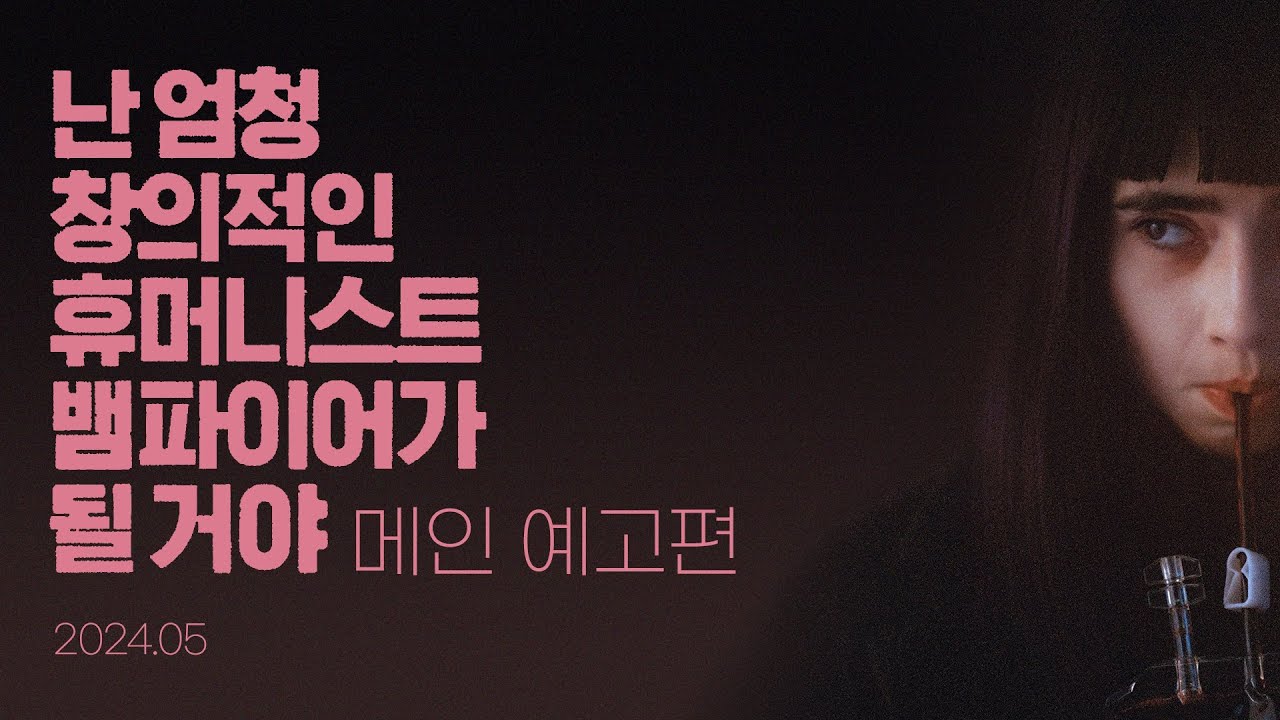
『ヒューマニスト・ヴァンパイア・シーキング・コンセンティング・スーサイダル・パーソン』
チョン・ソヒ(映画ジャーナリスト):良心さえなければ、食べて暮らしていける。見た目は10代である68歳のサシャ(サラ・モンプチ)は、人間の血だけで生きるヴァンパイアだ。彼女の問題は人の死に同情してしまうということに起因するが、映画はサシャのジレンマまでがサシャ自身であるのだと説く。日光に露出した途端に肌が縮れ、十字架アレルギー反応を起こすこのヴァンパイアは、殺人で営む摂生の輪、搾取と廉恥の板挟みになり、餓死を選ぼうとする。ゆっくり年を取る彼女にも自立の時が来たのだ。誰かの経静脈を吸血しなければならない「狩り」を激しく拒否して飢えた彼女は「自殺衝動者たちの匿名の集い」に参加し、いじめによって憂鬱な日々に陥ったポール(フェリックス・アントワーヌ・ベナール)と出会う。臆病で人生に未練のない「少年」と生きるための糧が必要な見た目上の「少女」は、犠牲者と加害者ではなく、お互いに望むことを提供するペアになれると信じる。思い描いた目的地と違い、サシャとポールはなぜか「非常に創意的なヒューマニスト・ヴァンパイア」の道に辿りつく。「自分」という存在と世界の不和によって、崖の前で崩れ落ちるような思いに苦しめられるが、自分の崖を知る者こそが自らを知る。辺境に辿り着いて同族を見抜いた彼女たちは、歩き続けることを決める。真っ暗な夜を。
「異世界アイドル」アイネのソロコンサート<EVER PURPLE>
ペク・ソルヒ(作家、コラムニスト):2024年5月11日、バーチャルアイドル「異世界アイドル」のメンバー・アイネ(INE)のソロコンサート<EVER PURPLE>がYouTubeを通じてリアルタイム配信された。この日のコンサートは4部に分けて行われ、アイネは計13曲を歌った。約1時間20分あまりの<EVER PURPLE>は、最高視聴者数8万人を達成し、盛況のうちに幕を下ろした。「異世界アイドル」メンバーのソロコンサートは今回が初めてではない。2022年5月15日、メンバーの一人であるジュルルが初めてJu. T'aimeというタイトルのソロコンサートを開催し、その次にゴセグとリルパがそれぞれTOURとdream againコンサートを開催した。
しかし、今回の<EVER PURPLE>は少し異なる。メンバーのアイネ自身が芸術監督となり、その指揮を取ったのだ。また、コンサートの始めから終わりまで、イントロ部分を除いてアイネの歌とダンス、照明と舞台装置、カメラまで全てリアルタイム配信で進行した。まるで実際のコンサートのように。2023年1月から準備を続けてきたという<EVER PURPLE>は、コンサートの臨場感を実現すると同時に、仮想世界ならではの演出を見せるために独自のプログラムを制作するなど、技術的に多くの努力が注ぎ込まれている。ステージの場合、実際のコンサート会場をベースに基本構成とステージセットの要素を把握した後、これらを再構成して実際の動線を組み、照明とカメラを配置したという。仮想の照明だけでも1870個入っていたというのだから驚きだ。「残酷な天使のテーゼ」のステージを見れば、現実では実現が難しい「セフィロトの樹」の演出を難なくこなしている様子を見ることができる。このように<EVER PURPLE>のすべての要素は、現実と仮想世界を行き来している。
さらに、<EVER PURPLE>でパフォーマンスされたカバー曲は全部、このコンサートで歌うためだけに再編曲したバージョンになっている。MRも新しく制作され、その過程では仮想楽器の導入なしにすべて人が演奏したという。さらに、バンドセッションやクラシックセッション、コーラスに参加した合唱団なども、実際に活動しているプロが参加している。先述したジュルルやゴセグ、リルパのコンサートと比較すると、バーチャルコンサートの技術がどのように発展してきたかをはっきり知ることができる。
2020年に新型コロナウイルスが蔓延し、パンデミック体制に入って以来、多くの芸能事務所がオフラインコンサートとオンラインコンサートを並行する傾向にある。しかし、果たしてこれほどのオンラインコンサートはともかく、これほどのオフラインコンサートを実現できるだろうか? 一度考えてみるべき問題だ。我々は今、<EVER PURPLE>によって新たな可能性の世界を目撃している。
『生きているか、黄金のモグラ』 (キャサリン・ランデル)
キム・ボクスン(作家):じっとカフェに座っていると、聞くともなしに人々の話を聞いてしまう。最近よく耳にする話はパンダのフーバオとその家族の話。そういった意味で、他の動物たちについて書かれた本を紹介してみよう。作家キャサリン・ランデルが著した『生きているか、黄金モグラ ‐ 消えゆく存在についての記憶(原題:The Golden Mole: and Other Living Treasure)』だ。この本は、作家がこれまでに寄稿した記事を編んだ本で、各チャプターで特定の種の動物についてじっくり扱っている。ページをめくってみると、聞き慣れた名前も初めて知るような動物もいるものの、共通点を探すとすれば、とても面白いということ! 400歳を迎えようとするサメ、眠っている間も絶えず羽ばたく小鳥たち。初めて知る事実も多い。コウモリが距離の計算にどれほど優れているのか、前を見ることができない黄金のモグラが実はどれほどつやつや輝いているのか。
この本の主人公たちのもう一つの共通点は、絶滅の危機に瀕しているという点にあるだろう。この本によって、ありふれているように思えるクモさえも人間によって深刻な絶滅危機に瀕しているという事実を初めて知る読者が多いはずだ。著者はこのエッセイを通じて、それらすべての動物を保護しようと訴える。動物たちを論じる構成が繰り返しに感じられるかもしれないが、むしろこの構成は、時間をかけて地道に動物たちについて深く考えられるチャンスになるのではないだろうか。著者は、それぞれの動物の名から取った歴史上の物語、詩、民話を探求するプロセスをウィット豊かに、かつ詩的に書き上げているが、さほど感傷的なレトリックに頼らずとも感動的なメッセージを伝える能力を持つ作家、ランデルによる動物の物語を一度読んでみてはどうだろう。