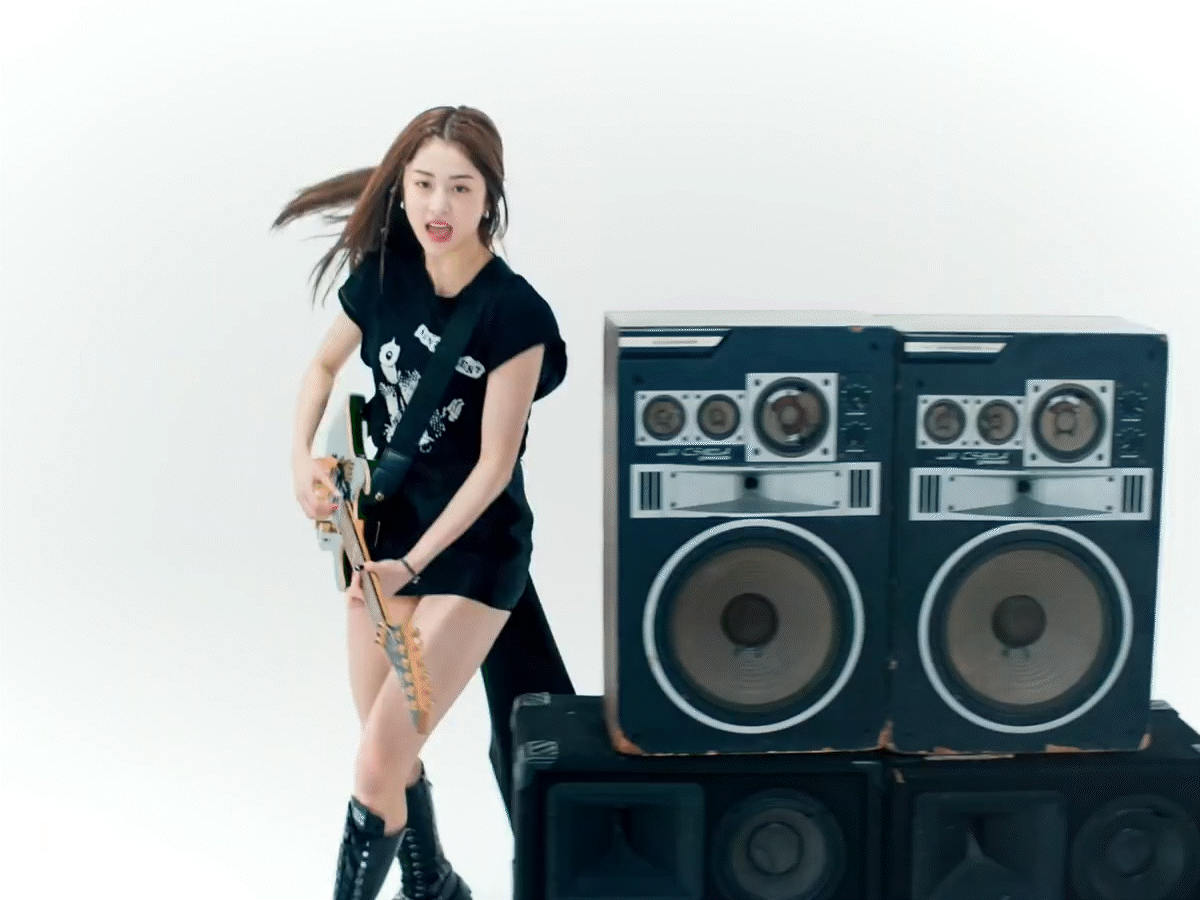愛について何か書こうとすると、数多くの論文や書籍を引用しなければならないように思える。本の中の哲学者の数ほど、愛に対する視点は無数にあり、愛の種類もまた多様だ。ヘーゲルにとって愛とは、自己と他者が対立しながらもそれを通じてより高次の統合された状態を形成することであり、サルトルにとっては自由と所有欲の間で生まれる葛藤が愛である。もう少し日常的に解釈してみよう。誰かにとっては心配し、気づかうことが愛であり、また誰かにとっては忘れられない出会いで経験した強い感情が愛であり、別の誰かにとってはモニターの中でしか会ったことのないアイドルが幸せでありますようにと願う気持ちが愛なのだろう。
これらすべての定義の前提は同じだ。「他者」が存在するということ。ひょっとすると、「愛する人を通じてすべての人を愛し、世界を愛し、結局は自分自身を愛することができる」というエーリッヒ・フロム『愛するということ』の一節が、愛についての明確な定義なのかもしれない。それが、HUH YUNJIN(LE SSERAFIM)の自作曲を聴いて、「愛」という言葉を最初に思い浮かべた理由だ。
彼女の音楽の中にはいつも「他者」が存在する。「I don't know what I'd be doing without you(あなたがいなかったら私は何をしていたかわからない)」という歌詞のように、他者の存在によって自分の存在を理解し、感謝を表現した「Raise y_our glass」も然り、他者の目に映る自分の姿を気にしながら、どんな姿でも愛してほしいと告白する「love you twice」もそうだ。彼女の視線は外にある。もう少し正確に言えば、周りの人々に向けられている。彼らと目を合わせて芽生えた感情、心のどこかから広がったあたたかな愛が歌詞のあちこちに込められている。
反対に、視線が他者から自らへ向かうこともある。直接的なメッセージを綴った「I ≠ DOLL」がそうだ。「昨日は人形(イニョン)のようで 今日はこのアマ(イ ニョン)」だと、アイドルを評価する匿名の人々の視線を借りる。これは自分自身をもう一度見つめ直し、内なる声に集中させる武器になる。これまで走り続けてきた中で直面した数多くの交差点、その一瞬一瞬の決意が作った道が「自分自身」のためのものだったと気づく「blessing in disguise」では、状況を見つめる視線をよりマクロなものに拡張する。その視線の先には結局、「私」がいる。

鉛筆を握った手が進む方向
HUH YUNJINは、自身のアイデンティティをジャンルではなく物語として紡ぎ出すストーリーテラーだ。彼女がこれまでソロシングルとして発表してきた5つの自作曲にジャンル的な統一性はない。しかし、それが物語の質感を決定し、感情の粒子をより鮮明にする。歌詞の中の物語とそれを表現するために選ばれたジャンルは、彼女の音楽の中で増幅される。
「I ≠ DOLL」のように直接的で強いメッセージを歌うため、ロックとヒップホップのサブジャンルであるトラップを混ぜて強烈なサウンドを構築し、「love you twice」のような控えめな告白や周りの人と共に過ごした静かな日々への感謝(「Raise y_our glass」)はアコースティック・ポップに乗せ、春風のような心を曲という形にした。リズミカルなバイオリンで序盤からムードを高め、ギターサウンドで全体を包んだ「blessing in disguise」は、「転禍為福(禍転じて福となす)」という四字熟語を盛り上がるディスコジャンルへと昇華させる。
HUH YUNJINの自作曲「jellyfish」の対話により集中できるのも、同じ脈絡からだ。アコースティックギターやウクレレなどを活用して、深海、漂うクラゲ、穏やかな波、その上で身を任せる姿を包み込むようなサウンドで形にした。穏やかなプロダクションのR&Bソウルは、クラゲが泳ぐ広い海になる。音楽を聴くそれぞれの場所で、それぞれのクラゲを見せてくれる。メッセージを伝えるのに最も適したジャンルと楽器を選んだというわけだ。
例えるなら、HUH YUNJINの音楽は鉛筆で描く絵画のようだ。鉛筆はインクのように一度で完結しない。その代わり、消しては重ねながら、少しずつ整えられていく。「jellyfish」もそうだ。曲はまるでクラゲが波に身を任せてゆっくりと流れていくようにシンプルに見えるが、その中には日々を生きる人々についての小さな観察と物語が積み重なっている。HUH YUNJINは、そんな瞬間を幾重にも重ねながら愛の顔を描いていく。ある日は、同じ波を繰り返しながら濃い明暗を加え、また別の日は、穏やかな波に沿って薄い背景を埋めていくように、彼女はそれぞれの曲で愛という感情を表現している。

Just keep swimming
クラゲは極めて受動的な生き物だ。水の流れに従ってのみ移動する。脳も心臓も骨もないため、体全体に広がる神経網によって環境の変化を感知する。このようなクラゲの姿をバカにする者もいるかもしれない。この荒々しい世界では、能動的に行動しなければ成長できないと教えられてきたのだから。しかしクラゲは、海の温度や深さに関係なくどこでも生きることができ、地球を覆う海のほとんどはクラゲの家になる。揺れる波に漂う姿は優雅にも見え、光を放って自らを守り、コミュニケーションを取る姿は、自然が贈る美しい光のようにも見える。
つまり、軟弱に見えるクラゲの特性はクラゲならではの強みにもなるのだ。海を私たちの住む世界に置き換え、クラゲを明確な目的なく人生を生きる人だと仮定してみよう。何かを欲する者は時折、人生の波に抗いたくなるものだ。行きたい方向が明確だと、流れるままではいられない。波に流され、転覆することもある。どうしようもなく傷ついてしまう。しかし、人生に明確な目的がなく、与えられた日常の中で毎日着実に泳ぐ人は、人生の波に忠実だ。予期せぬ傷を負うことがあるかもしれないが、再び、流れに乗って前へ進む。ずっとそうしてきたように。
どちらがより良いという価値判断をしようというのではない。しかし、「jellyfish」における彼女の視線に従えば、クラゲ、あるいはクラゲのように人生の波を悠々と受け入れる人間は羨望の対象だ。自らと対照的だからだ。「水面上」のものをやたらと気にして、その気持ちに苦しめられ、結局は「跡形もなく消えてしまいたい」と思う自分と。「I'm washed up on the shore(浜辺に打ち上げられた)」と打ち明けた後につぶやく問い「What am I searching for?(私は何を探しているんだろう?)」を通じて、彼女がクラゲとは反対に、人生の波に激しく抗ってきたことが推測できる。
「jellyfish」は、単にクラゲの人生に向き合う態度や、外見の美しさを讃えて終わるわけではない。歌詞全体がHUH YUNJINとクラゲが交わす対話のようにも感じられる。例えばこんなふうに。曲の語り手であるHUH YUNJINが「目的もなくjust cruising / 導かれていく 君は どこかへと」と語りかけると、クラゲが答えるように歌う。「ただ泳ぐだけ/特に立派な理由はないし 生きることに特別な意味もない/心臓だってない」と。「Just keep swimming」という歌詞は後半で再び登場する。その後の主語を「私」に変えて、「私はただ流れていく」という能動的な文脈を加える。クラゲに慰められたかのように。あるいは、同化したかのように。
HUH YUNJINの曲の中の愛は、誰かを通じて出発するものの、結局は自分自身に向かって戻ってくる。他者を見つめる視線は自らを理解する鍵となり、その気づきは人生全体へと拡張される。鉛筆を握った手は、毎日少しずつ違う方向に動きながら新しい物語を描き出すが、鉛筆の先端が完成させる絵はいつも同じだ。曲の語り手である、「私自身」。HUH YUNJINが描く愛のモンタージュは、そうやって、毎日少しずつ完成に近づいていく。
- HUH YUNJIN「LE SSERAFIMは優しさを学ばせてくれると思います」2024.02.24

- HUH YUNJINがInstagramを楽しむ方法2024.01.15

- HUH YUNJINの「青春ものの主人公」のような人生2023.01.16