2024年7月、すでに15回目を迎えた国立劇場の韓国伝統音楽フェスティバル「ヨウラクフェスティバル」にソン・ソヒが出演した。「空中舞踊:花間蝶舞」というタイトルを掲げた公演には、春に発売されたソン・ソヒの3枚目のEP『GANGGANGSULLAE』(原題『空中舞踊』、2024)が中心だったが、ステージでは彼女の初の自作曲から未発表曲まで、ここ数年のシンガーソングライティング活動が網羅されていた。これまで彼女が京畿民謡(ソウル、京畿道を中心に歌われてきた民謡)を歌い、研究してきた20年分の根と幹から伸び始めた新たな枝を聴かせるそのような構成は、年末に開催された初のソロ公演「風流」でも続いた。すでにテレビ番組で披露したカバー曲や、ゲストとして参加したsEODo BANDの曲目などが追加されたが、「風流」でも基本的なセットリストは維持された。それでも二つの公演の間に大きな違いがあるとしたら、今回はライブの様子が直接撮影され、彼女のYouTube公式チャンネルで公開されたことだろう。それを通じて、この1〜2か月の間にソン・ソヒの「Not a Dream」が、まだ「未発売自作曲」である状態にもかかわらず、多くの聴き手と出合うことができたからだ。

2月1日現在で約400万回を記録した「Not a Dream(未発売自作曲)」の映像の再生回数は、現時点(2月22日現在)ではなんと約870万回を超え、2倍以上に跳ね上がったのだが、そのような人気が国楽(韓国伝統音楽)家ソン・ソヒの「思い切」った「変身」のおかげだという意見がしばしば見られる。だが、花の間を飛び回る蝶の舞のように、さまざまな音楽の領域を行き来するソン・ソヒの「花間蝶舞」は、彼女がMAGIC STRAWBERRY SOUNDに所属事務所を移し、大衆音楽の創作に専念し始めた2022年以前から絶えず続いていた。京畿通俗民謡の「梅花打令」がソン・ソヒの最初の2枚のEP『NEW SONG』(2015)と『Modern Korean Folk Songs』(2018)に異なるアレンジで収録されたことは、その一つの手かがりだ。そこで、一つの音をその前後で装飾する国楽の技法であるシギムセを細かく調節して歌うソン・ソヒの技量とともに、アレンジでも伝統音楽と海外の音楽を交差させるいくつかの方法を確認することができる。国楽器と洋楽器の併存が際立つ2015年の「Song of Plum Blossom(梅花打令)」がゆっくりとしたスピードでクッコリ長短(巫俗儀式で演奏される音楽のリズムパターン)とブルースのリズムを混ぜようとする一方、エスニックフュージョンバンドのSecond Moonとコラボした2018年の「Song of Plum Blossom(梅花打令)」は、アイルランドのような他文化の民族音楽を伴奏に、澄んだ美しい音が交差する。国楽フュージョン、またはクロスオーバーといえば最も直観的に思い浮かぶ、「韓国的な」特徴と「韓国的ではない」特徴の組み合わせを選んだわけだ。
「Not a Dream」をはじめとするソン・ソヒの最近の自作曲が、これらのEPや「疲労困憊プロジェクト」のような既存のクロスオーバー作品とははっきりと区別される理由がまさにそこにある。国楽器で西洋の器楽を演奏したり、大衆音楽の伴奏で古典のパンソリのステージを繰り広げるなど、耳で聴くことができるだけでなく、目でもはっきりとわかる国楽と洋楽の区分が、そこでは明白ではないからだ。典型的なクロスオーバーで両者の境界線をどこまで引いて、何をどれだけ、どのように混ぜるかについての力比べが行われるのとは異なり、ソン・ソヒがいくつかのインタビューで例えているように、彼女の「別キャラ」が作って歌う大衆音楽で、「本キャラ」が堪能な京畿民謡が直接活用されたり、指示されることは稀だ。二つの領域の間の境界をはっきりさせずに互いの共有地を広げるのではなく、むしろ両者の境界をはっきりと決めて、一方からもう一方へ移るというわけだ。つまりソン・ソヒの自作曲は、国楽と洋楽の混在というよりも、分割をもとに成立する。新たな世界に向けた彼女の本格的な探検は、京畿民謡から大衆音楽へ、また「本キャラ」から「別キャラ」への境界を越えることにより始まるのだ。KBS 2TV『不朽の名曲〜伝説を歌う』のステージでも披露したように、その境界を通過するソン・ソヒの声は、シンプルなチャング(太鼓)の伴奏に合わせて巧みに音の端を下げたり震わせる「Monggempo Taryeong」から、力強いバンドの演奏に合わせてゆったりと口ずさむ「Journey to Utopia」へとスムーズに移り、「どちらが上、下ということなしに支えられる」「二つの世界を横断」する。
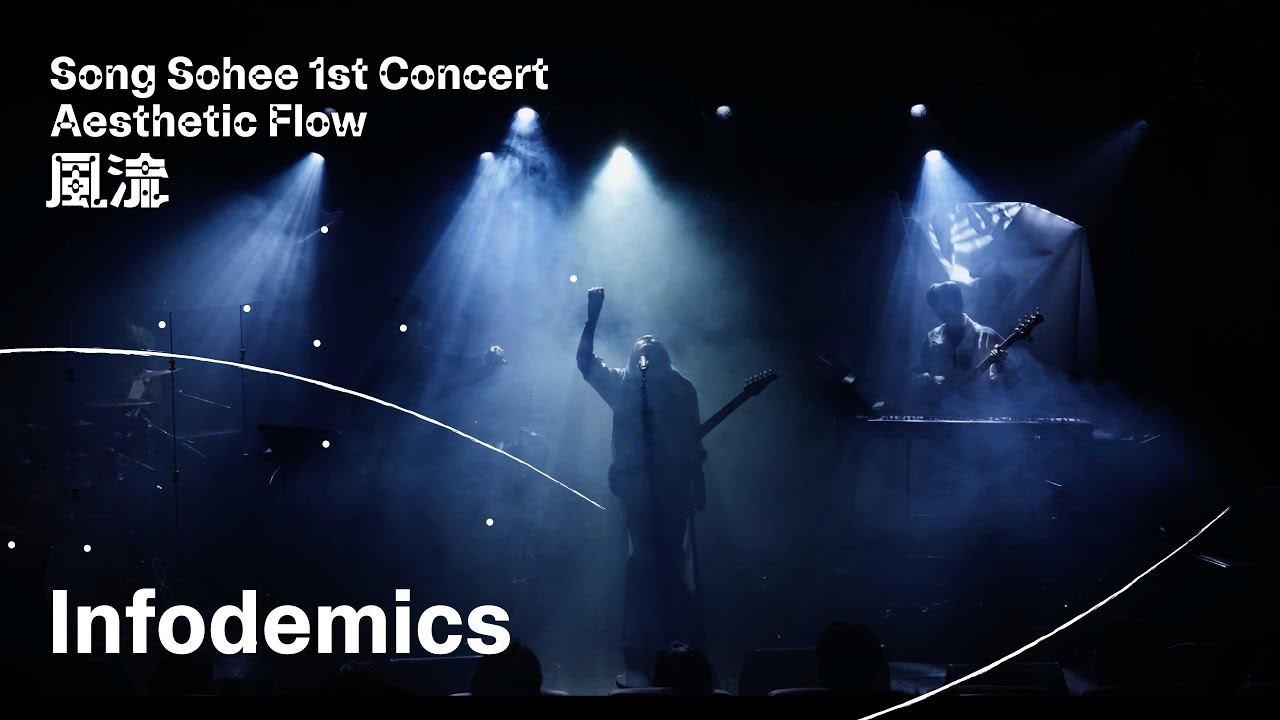
ソン・ソヒが横断してきたその場所は、彼女のインタビューでの発言を借りれば、長い歳月をかけて築かれた「正解に向かっていくジャンル」である伝統音楽よりも、さまざまな答案を提示できるように見える。それだけにその世界は、氾濫する情報が目まぐるしく回転する万華鏡のように感じられるかもしれない。そのような混乱を盛り込んだ2023年のシングル2曲は、ソン・ソヒのそのような情感を適切に伝えられるような大衆音楽のジャンルを、「別キャラ」に着せるさまざまな衣装のように活用する。「Infodemics (with Ilwoo Lee from Jambinai)」は、ロックバンドJambinaiのイ・イルが国楽器の演奏者ではなくギタリストとして、バンドメンバーであるチェ・ジェヒョク、ユ・ビョングとの強烈な演奏で渦巻く「言葉と文章の洪水」を、「Asurajang」は、iKONの「LOVE SCENARIO」やAKMUの「NAKKA」などを作曲したK-POPプロデューサー、MILLENIUMが提供するディスコ風のダンス曲により、騒然とした状態でぐるぐる回る世の中の万事を表現している。ソン・ソヒはその真ん中で音全般を率いる。船の舵取り役を担う彼女の声は、力強く押し寄せたり、ポンポン跳ね回るサウンドに合わせ、京畿民謡でのそれとはまったく異なる動き方をする。しっかりと力を込めたサビが、コーラスとともに壮大な空間の広がりを色濃く創り出すポストロックの演奏を突き抜ける「Infodemics (with Ilwoo Lee from Jambinai)」の後半部分や、同名の軽快なトロットの曲(「The world is So Strange」、原題は「Asurajang」と同じ)でシン・シネが歌う華麗な技巧を認識するかのように、音の端を下げて装飾する「Asurajang」のようにだ。
それぞれの曲のサウンドに合わせて声を調整するソン・ソヒのすばらしい発声は、『GANGGANGSULLAE』で自然というテーマと自己省察的にかみ合い、より幅広く展開する。彼女が国楽家より大衆音楽のアーティストとしてのアイデンティティに重点を置いて発売する、初めてのEPの旅路にふさわしい背景を作ったのは、ノルウェーのポップス歌手オーロラ(AURORA)やシグリッド(Sigrid)などの作曲家・プロデューサーとしても活動したオッド・マーティン(Odd Martin)だ。そのおかげで、今回はエキゾチックなメロディのエレクトロポップが不思議な雰囲気を霧のように敷き詰めている。美しく清らかな歌声が特徴的な京畿民謡の歌唱法は、神秘性を強調するオッド・マーティンのサウンドに特によく合っているが、そこでソン・ソヒは声の形を1曲の中でも多彩に変えながら、それによって高揚感を徐々に高める展開を聴かせる。例えば、「Dear My Lover」のサビが登場するたびに「エヘイヤ」が次第にはっきりしてきたり、口音がとても印象的に伸びる「GANGGANGSULLAE」のサビのようにだ。高音域でゆらめく「Against the Dark Ocean」の声は、大地の上を夢の中の如く漂うような感覚を強め、広大な森を疾走する迫力を与える「Forest Spirit」では声が一節ごとに変化に富んで動く。そのように『GANGGANGSULLAE』は、ソン・ソヒが巧みなイリュージョンを見せるアルバムだ。彼女は、自分の声で何をどのように表現するかについての答えは一つに決まっていないということを身をもって教えてくれる。

ソン・ソヒが京畿民謡をベースに大衆音楽における個性を発展させる過程で、聴く人に馴染みのあるポップスの聴き慣れた特性は、ふと滲み出る国楽的な要素を通して耳馴染みのないものになる。「Not a Dream」が聴く人にポジティブな衝撃を与えた理由を、まさにそこに見つけることができるだろう。「Not a Dream」は、まず『GANGGANGSULLAE』の神秘的な雰囲気と高揚する進行を引き継ぐ一方、特有の異色な歌声から、有名なアイルランドの音楽家ドロレス・オリアダン(Dolores O’riordan)やエンヤ(Enya)を思い浮かべるという評判のように、歌唱の技巧と装飾にずいぶん力を注いでいる。その時曲が個性を得る理由は、そのような大衆音楽や西洋の民族音楽の特性が、伝統音楽的な技術を活用するソン・ソヒの解釈と絶妙にかみ合うからだ。いくらバラエティ番組で本キャラと別キャラが関係のないふりをしても、結局二つのキャラクターが一人のコメディアンを通して演技するように、いくら国楽と洋楽の境界を分割しようとしても、結局はソン・ソヒという一人の音楽家から、本キャラの実力と別キャラの個性は一つの歌唱で表現されるのだ。
美しく清らかな歌声が特徴的な京畿民謡のスタイルは、「Not a Dream」の澄んだ高揚する雰囲気ととても合っており、長く伸ばした音節でシギムセにより音の進行を斬新に装飾するソン・ソヒの表現力はひときわ輝く。すがすがしい気分をたっぷり抱かせてくれるサビで、そのような特徴が最も際立つのだが、「心が」と「落ち着く」、「ここで」と「私を呼んで」の間の激しい変化に気づく間もなくスムーズに方向を変える流れは、聴く人をソン・ソヒの感情的な旅路へと導く。そのような壮大さは、彼女が爽やかに歌うように、「そう、私が望んだこと」かもしれず、その清涼感と爽快感こそ、まさにそれほど多くの聴き手が「Not a Dream」に共鳴する情感だ。自分が望む方向に道を歩んでいくことから、別の世界を自分のやり方で染めるまでの開放感。

人生のほとんどを過ごしてきた京畿民謡の世界から抜けだし、「ユートピアの向こうに鐘の音が鳴ったら 夢を横切って」で始まったソン・ソヒの旅路は、それまで大海原を渡り、暗く波立つ海に抗って、「Not a Dream」ではいつの間にか「ユートピアの向こう」まで行き着いた。何よりも自分に与えられた翼をはためかせて自由に飛ぶために、ソン・ソヒは「Journey to Utopia」の最初の一歩を踏み出した時から、それが決して「夢の旅ではない」と固く誓った。彼女が夢見ていた境界の向こうが本当に夢ではないということを、「Not a Dream」を歓迎する視聴者が証明してくれるなら、「Not a Dream」はそこがどんな風景だろうかという問いにソン・ソヒが提示する一つの答えだろう。2025年上半期を目標に制作中の曲がついに発売されたら、彼女の旅は、はるか遠くへの次の道のりに向かう歩みと泳ぎ、そして羽ばたきを続けるのだろう。多くの音楽家があちこちで扱ってきた境界を、これまで夢だとばかり思っていたやり方で少しずつ変えていきながら。
- マック・ミラー、感情の層の中で浮遊する2025.03.06
- ザ・ウィークエンド、自らを解放する2025.02.27
- HUH YUNJINが音楽で描く愛のモンタージュ2025.02.14