多数の女性は優れた業績と能力を備えたにもかかわらず、名のない忘れられた存在として残ってきた。20世紀初め、イギリスの女性作家、ヴァージニア・ウルフは「シェイクスピアに妹がいたら、シェイクスピアほどの大文豪になれただろうか」という問いかけを通じて、優れた芸術的才能を持つ女性たちに強いられていた社会的制約を批判した。名前を呼ぶ行為、ひいては自分の名前で呼ばれる行為は、ただ呼名そのものだけにとどまらない。個人の存在を公に証明し、その存在に歴史的生命力を与えることだ。

JENNIEは今年3月7日に発売された1stフルアルバム『Ruby』を通じて、呼名という行為を明確に示す。JENNIEにとって呼名は、証明以上の行為だ。存在をはっきりと示すことを通り越して、リスナーたちと共鳴することだ。アルバムのイントロの後すぐに続く曲が「like JENNIE」であることも、これと軌を一にすると見られる。この曲をシンプルに解釈すると、全世界を背景に1つのアイコンになったJENNIEの存在感を、機転を利かせて表現した曲だ。「JENNIEと盛り上がりたい人は誰?(Who wanna rock with jennie?)」や「JENNIEのように夢中にさせる人がいる?(Who else got ’em obsessed like JENNIE?)」という、得てして傲慢に映るかもしれないこれらの問いかけが歌詞になっていることに誰もが納得させられるからだ。獰猛にうなるようなビートにも圧倒される。
しかし、JENNIEは「JENNIE」がどんな人物なのか具体的な描写を並べながら特定しない。「AIが真似できないスペシャル・エディション(Special edition and your AI couldn't copy)」や「値段が付けられない(I'm priceless)」といった比喩的表現は、規定できない主体としての位置を確立する方法でもあるが、同時に境界をぼかした表現でもあるため、流動的な「JENNIE」をつくる戦略にもなる。外見に関する具体的なフォルムの代わりに、いかなるイメージも盛り込まないことで、JENNIEはむしろより多くの人がその名前を借りて自分の話を始められるようにする。そうして「like JENNIE」は固有名詞であると同時に、普遍的な呼名の形になる。存在の宣言であり、可能性の拡張である。

「ZEN」はまたちがう形の呼名だ。外部に向かっていた名前が内部に向かったときの呼名。「ZEN」とは、心を整えて精神を統一し、悟りの境地に至る仏教の修行方法の「禅」を意味する。そのため、曲が流れる間ずっと悟りの過程を聴いているような印象を受ける。一般的な考え方としてより良い人になる過程は、自分が思う良くない面を打破し、排除することに近い。だが仏教によると、そんな一面さえも「自分」であることを知ること、固定されたエゴはないということを知ることが悟りだ。彼女は「真夜中に咲く花(midnight bloom)」という歌詞を通じて、煩悩、不安、悩みを抱えて成長したことを、揺るぎのない存在になったことを表明する。修行の末に、自分を苦しめていたものさえも結局「自分」自身だったことを認める態度を取る。「私は禅を貫く(I keep it Z, Zen)」という歌詞から、「ZEN」は単なる到達点ではなく、その過程を通った「JENNIE」のもう1つの名前のように聞こえる。サウンドはこの修行と足並みを揃える。朦朧としてがっちりとしたベースが曲の重心を取り、その上にJENNIEが吐き出す歌詞がまばらに刺さる。まるで余白の美を表現したかのように節制されたメロディーは、JENNIEが心を静めて考え、超越する存在になったことを感覚的に証明する。その余白の中で彼女の名前は、聞き直さなくてもはっきりとしている。
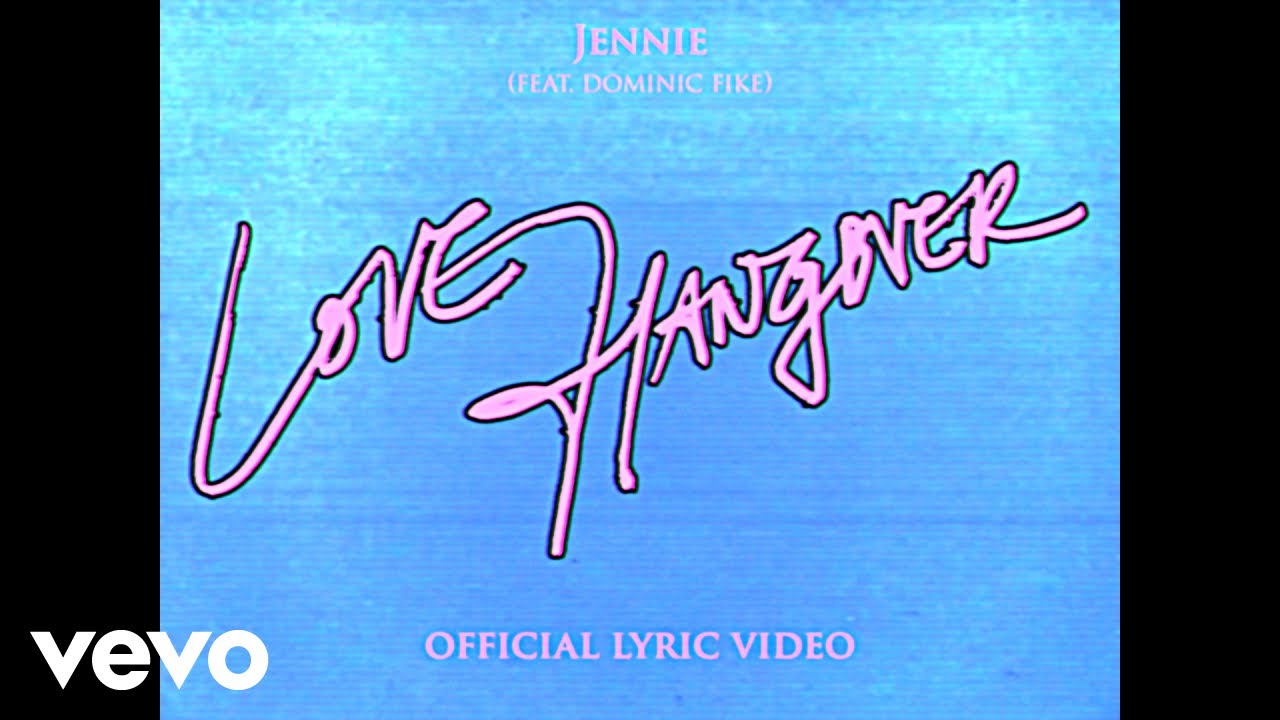
ところが、自分の名前を呼ぶということがいつも確信に満ちた宣言だけでできるわけではない。時として名前は感情の中で忘れられ、他人の言語の中で霞む。「Love Hangover (feat. Dominic Fike)」と「Twin」は、その境界に置かれた曲だ。JENNIEはこの2曲を通じて、関係の中で戸惑う自分を描く。恋に酔いしれ、他人の言葉に自分を任せる瞬間の数々。誰が自分を呼んでいるのかも、自分が誰に向かっているのかも明確ではない。このときの呼名は明瞭な自己宣言ではなく、感情によって照応し、歪曲される非定型の声掛けだ。
サウンド自体が感情の二日酔いのように聴こえる「Love Hangover (feat. Dominic Fike)」で、JENNIEはのんびりとして朦朧としたビートの上で断定的に話すよりは、まるで得体の知れない感情に誘われるように歌う。ふわふわとしつつ、混乱している。言葉の代わりに感情が流れ、その流れは自分の名前の境界を一時的に消してしまう。「Twin」の感情はむしろ明確になっている。深い後悔と心残りだ。アコースティック・ギターのリフがメインとなるミニマルなサウンドに、口ずさむようなJENNIEのボーカル、1枚の手紙を読み上げているような歌詞は、幼い頃親しかった友達を思い出させる。この曲でJENNIEの名前は「Twin」だ。それがその時代のアイデンティティだ。曲の終わりに繰り返される「Twin」は自分を呼ぶ名前でもあり、当時のその友達を呼ぶ名前でもある。
アルバムの中で表現された「JENNIE」という人物は、愛に無謀に飛び込み、感情にどっぷり浸ることに慣れている人物に近いのかもしれない。感情の温度を受け止めるために自分を受け止める過程を経て、堂々と自分の名前を呼ぶ状態にたどり着ける。ところが、名前を呼ぶということは、単に「自分」を確かめることだけにとどまらない。呼名はつながりであり、他人との絆である。「ExtraL (feat. Doechii)」と「Mantra」で、これはより鮮明になる。「私たち女性がステージを支配する(Do my ladies run this)」という歌詞を繰り返しながらテーマを強調させる「ExtraL」は、かっこいい女性たちで集まって作るステージ、「大きな目論見(Big Moves)」について語る。JENNIEの芯がありつつも流麗なボーカル・パフォーマンスも印象的だが、自分の名前を力強く叫びながら登場するドーチ(Doechii)は、この曲のもう1つの軸を作る。彼女が鋭く叩きつける「私は男たちの機嫌を取る必要なんてないから。彼らと妥協するつもりもない(「cause I' m not here for pleasin' the men Not here to reason with them」)という歌詞は、切れ味のいい解放感まで与えてくれる。
続いて登場する「Mantra」は、連帯で結ばれた女性たちに伝える経典だ。経典と書くと少し大げさに感じられるが、この経典は軽やかだ。「きれいな女の子の鉄則(Pretty-girl mantra)」と名付けられたこの経典には、外形的な「pretty」を保つ方法ではなく、女性同士の連帯について書かれている。傷に飲み込まれないこと、凛としていること、女性たちを守ること等々。女性なら誰もが自分のいる場所でできる行動鉄則は、フックするサウンドとループするサビの上に乗せられ、女性たちが一緒に共鳴する声になる。

『Ruby』は、JENNIEというアーティストが現在の音楽界においてどのような存在なのか確実に証明するアルバムだ。彼女が自分の名前を入れた歌詞で、滅多にない自信の込められたフレーズを歌うだけで全世界のリスナーたちを熱狂させる今、我々は1人のポップ・アイコンが自分の名前で世の中を説得する場面を目撃している。
「JENNIE」という名前は、歴史的生命力を孕んで激動する。その名前は1つの固有名詞であると同時に、何らかの状態に拡張されることもある。自分のことを物怖じせず表に出し、名前を堂々と掲げられる状態。JENNIEはまさにその力でリスナーたちと共鳴する。歌を一緒に歌う瞬間、誰もがJENNIEになれる。そうしてJENNIEは、どこにでも存在する。

- HUH YUNJINが音楽で描く愛のモンタージュ2025.02.14
- ドーチ、新たなヒップホップのマドンナ2025.02.07
- SZA、自らの世界を拡張する2025.02.05