
『ジュラシック・ワールド/復活の大地』
ペ・ドンミ(『シネ21』記者):南米フランス領ギアナのジャングルで、恐竜のゲノム実験が秘密裏に行われている。研究所には、実験中の突然変異で生まれた恐竜「D-レックス」も監禁されており、ある日、偶然の出来事によって事故が起こる。研究員が食べていたチョコバーの包み紙がシールドルームのロック装置に巻き込まれてドアが開き、飛び出した巨大なD-レックスが科学者たちを丸呑みにしてしまうのだ。『ジュラシック・パーク』(1993)のリブート作である『ジュラシック・ワールド/復活の大地』は、非現実的だがウィットに富んだオープニングシーンから新たな物語をスタートさせる。突然変異によって生まれた恐竜の危険性を警告する赤いライトとサイレンの音、そして往年のオリジナル作品を思わせるレトロなサウンドトラックが観客の心拍数を一気に高める。チョコバーの包み紙という些細なきっかけで凶暴な恐竜が世に放たれるという想像が、観客の目の前で恐ろしい現実として迫ってくる。
人類が恐竜を復活させてから32年の月日が流れ、D-レックスがギアナのジャングルに飛び出してからは17年が経った。もはや人々が恐竜を珍しがることはない。『ジュラシック・パーク』で鮮烈なデビューを飾ったブラキオサウルスは、交通渋滞を引き起こす厄介な存在になっている。恐竜に注目しているのは、いまや資本家だけだ。大手製薬会社は大きく強靭な心臓を持つ恐竜の遺伝子を使った新薬開発を企て、製薬会社の代表マーティン(ルパート・フレンド)は、情報員のゾーラ(スカーレット・ヨハンソン)と古生物学者のルーミス(ジョナサン・ベイリー)に1,000万ドルの報酬を約束して、恐竜の血を採ってくるよう依頼する。ところが、彼らを待ち受けていたのは、人間と同じフレームに収まりきらないほど巨大な恐竜たちの爪や牙だった。1,000万ドルの報酬よりも、生きて島を脱出することが主人公らの急務となる。
なぜ今、再び『ジュラシック・パーク』なのか。ギャレス・エドワーズ監督は、観客の根本的な問いに対して、チョコバーの包み紙を使ったセンスのある答えを返す。しかし、オープニングのユーモアが危険極まりないD-レックスを呼び覚ましたように、我々観客の笑いはたちまち消え去り、それは正体不明の巨大生物に追われる恐怖へと変わる。これによってエドワーズ監督は、人間がいかに小さな存在であるかを改めて気づかせてくれる。観る者を登場人物たちと一緒に絶望の底へ突き落とし、ホモ・サピエンスは約20万年を生き延びてきたものの、恐竜は100万年もの間生きてきたこと、地球から完全にいなくなった恐竜たちのように人類もいつか絶滅するかもしれないことを暗喩する。それだけに『ジュラシック・ワールド/復活の大地』は、これまでの『ジュラシック・パーク』や『ジュラシック・ワールド』シリーズを見ていない観客でも楽しめる自己完結性を備えた作品となっている。その「復活」が、ひたすら喜ばしい。
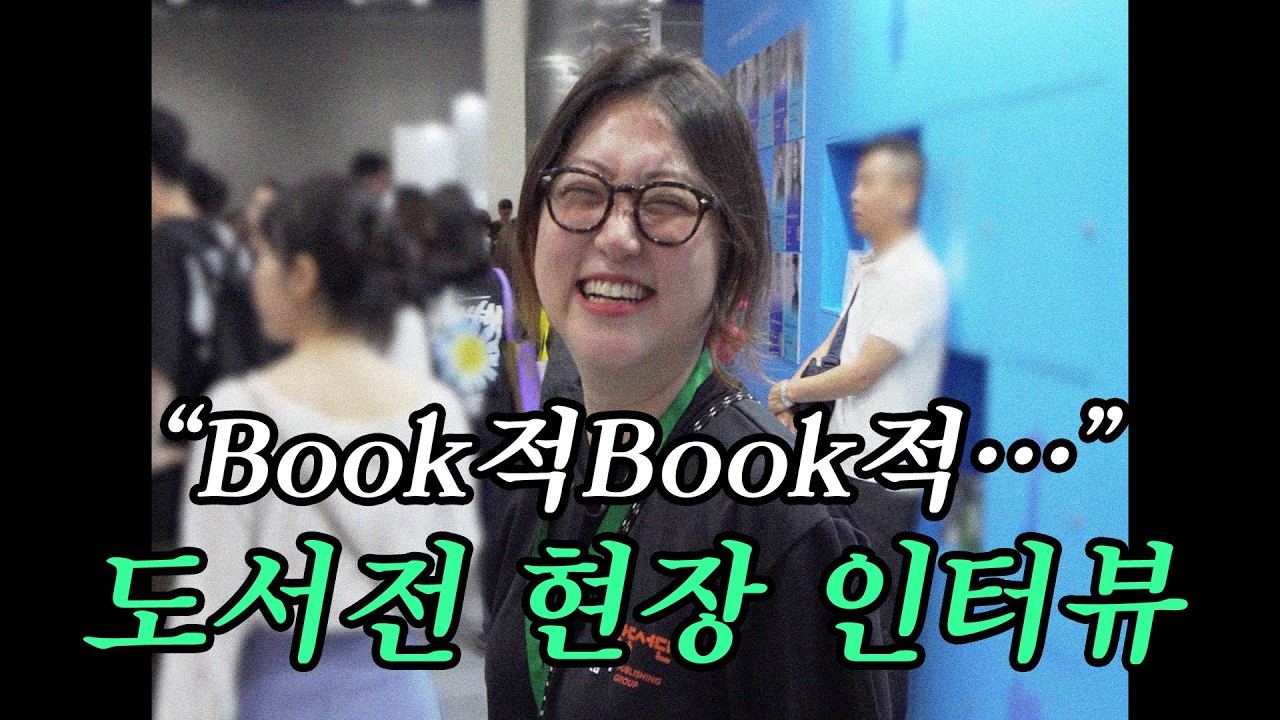
『民音社TV』(YouTube)
ユン・ヘイン:『民音社(ミヌムサ)TV』は、『世界文学全集』で知られる出版社「民音社出版グループ」が運営するYouTubeチャンネルだ。出版社のYouTubeチャンネルにありそうな新刊のPRや作家へのインタビューではなく、ここでは社員たちの日常を見ることができる。民音社の編集者やマーケター、デザイナーたちが読んでいる本を紹介したり、読書や趣味のためのグッズを自慢したり、開封動画を披露したりする。出版社の会議や昼休みといった普段の一日をVlogのように収録し、「オフィス・シットコム」さながらのムードでタロットカード好きの社員が同僚の未来を占ったり、料理好きの社員たちによる料理コンテストが開催されることもある。平均勤続年数14.3年の部長たちが、新入社員だった頃の「失敗談バトル」を繰り広げるなど、会社員ならば共感できるエピソードを打ち明けることもある。企業の広報チャンネルというよりも会社員Vlogのような親しみが感じられ、「坡州(パジュ)*のアイドル」と呼ばれるほど親しみやすいマーケティング部のチョ・アラン部長によるスムーズなMCが、皮肉にも出版社チャンネルである『民音社TV』ならではのYouTube的な魅力を生み出している。
もちろん、出版に携わる人々の会話が行きつく先は、結局「本」に変わりない。ただし『民音社TV』は、「本は難しくない」と説くのではなく、本とともに生きる社員たちの日常に溶け込んだ「本が持つ本来の楽しさ」を伝えることに集中している。社員たちは、通勤中に読んでいた本を何気なく鞄から取り出し、新しい趣味のために購入した本を自然な流れで紹介する。それと同時に、編集者でさえ締切りに追われながら本を読んでいて、1冊読み終えてから次に行くのではなく、複数の本を並行して読むという「並行読書」の実践を語り、読書が誰にとっても難しいもので、「これが答えだ」という正解もないと伝える。その一方、トーナメント形式で「世界文学全集」の古典文学のあらすじを紹介したり、奥深く難解そうな古典を親しみやすく解説したりもする。ショート動画がメインストリームとなった今、「テキスト」の価値が危機に瀕しているにもかかわらず、『民音社TV』はそれを逆手に取ってショート動画を活用し、古典文学の奥深い魅力を語ると同時に、読書そのもののハードルを低くする。こうした取り組みの積み重ねがチャンネル登録者約30万人という影響力につながり、出版社「MUZE(ムジェ)」を立ち上げた俳優パク・ジョンミンや、読書が趣味のガールズグループ「MEOVV」のメンバーをゲストに迎えたりと、「本」の話を通じて新たな読者との出会いを生み出している。
「テキストヒップ(text hip)」と「読解力の危機」というキーワードが同時に語られている現在、「2025年ソウル国際図書展」には15万人もの人々が来場した一方で、韓国の成人読書率は低下の一途を辿っていると報じられている。それでも、この「オフィス・シットコム」と「人文教養」チャンネルを行き来する民音社の日常と人々の言葉を追いかけていると、もっと多様な方法で本に親しめることに気づくとともに、今なお人間が本を必要としている理由を実感する。「これまでに経験したどんな中毒よりも、『活字中毒』が一番抜け出しづらいんです」という編集者キム・ミンギョン氏の言葉のように、『民音社TV』に登場する人々は、誰もが自分の「好きな本」と「読書」について真剣に、そして情熱的に語る。本が持つ固有の価値と意味、テキストが紡ぐ物語の楽しさ、それを味わう喜び。それこそが、『民音社TV』が伝える読書の本質的な楽しさなのだ。
*韓国の出版社や出版業者が多く集まる坡州出版団地のこと

「Heosse!」 - CHUDAHYE CHAGIS
カン・イルグォン(音楽評論家):おそらく「CHUDAHYE CHAGIS(チュ・ダヘ・チャジス)」というバンドに馴染みの薄い人のほうが多いだろうから、まずはこう言わせてほしい。「無い時間を割いてでも、ぜひ一度聴いてみてください。その時間は、きっと報われるはずです」。私のように好みに合った人なら痺れるような歓喜を味わえるだろうし、そうでなくても、前例のない画期的な音楽を体験したという記憶が残るはずだ。それほどCHUDAHYE CHAGISの音楽は衝撃的だ。2020年にリリースしたデビューアルバム『Underneath the Dangsan Tree Tonight(今夜、堂山の木の下で)』は、誰も予想しなかったジャンルの混交だった。巫歌(ムガ:祭祀の場で巫堂が歌う歌)とR&B、ファンクの融合。そこにヒップホップ、レゲエ、ダブ、ロックなどの要素も溶け込み、まるで呪術のような音楽が誕生した。チュ・ダヘ・チャジスは2020年の韓国大衆音楽において「独創性」の代名詞となり、『今夜、堂山の木の下で』は、韓国はもちろんのこと、世界的に見ても指折りの優れたオルタナティブアルバムになった。
それから約5年の時を経て、バンドの2ndアルバム『SOSUMINJOK(少数民族)』がやって来た。西道民謡(朝鮮半島において黄海道と平安道を中心として歌い継がれてきた伝統民謡)の唱法に基づいたチュ・ダヘのボーカルは依然として感情を自在に操り、「サイケデリック・シャーマニック・ファンク」と名付けられた音楽と演奏も、相変わらず聴く者を恍惚とさせる。とりわけ「Heosse!」は、かれらが追求する音楽的、精神的なベクトルを最も感じられる曲だ。うねるようなベース、ライブ感のある強烈なドラムビート、そしてコンス(巫俗儀礼の過程で、神のお告げを人間に伝える行為やその内容をいう)さながらのボーカルが混ざり合い、圧倒的な感興を与えてくれる。この神秘的かつ卓越した音楽に心を動かされたなら、ぜひニューアルバムの『少数民族』を、そして1stアルバムの『今夜、堂山の木の下で』を聴いてみてほしい。もう一度言おう。「その時間は、きっと報われるはずです」
*CHUDAHYE CHAGISは、民謡とロックを融合させたバンド「SsingSsing」として注目されたチュ・ダヘ(Windy City)とSoul Sauce(a.k.a. NST & The Soul Sauce)出身のイ・シムン、Windy City、CADEJO、3RD CHAIR出身のキム・ジェホ、FLING出身のキム・ダビンによって結成されたバンドである。
- 『K-POPガールズ!デーモン・ハンターズ』、弱点が私をもっと強くする2025.07.04
- 『F1アカデミー: 新たなる風となる者に』、夢を追う女性たちの最も熱い疾走2025.06.27
- 『カーニーを探して』、K-ドーパミンより中毒性のある真摯な心2025.06.20