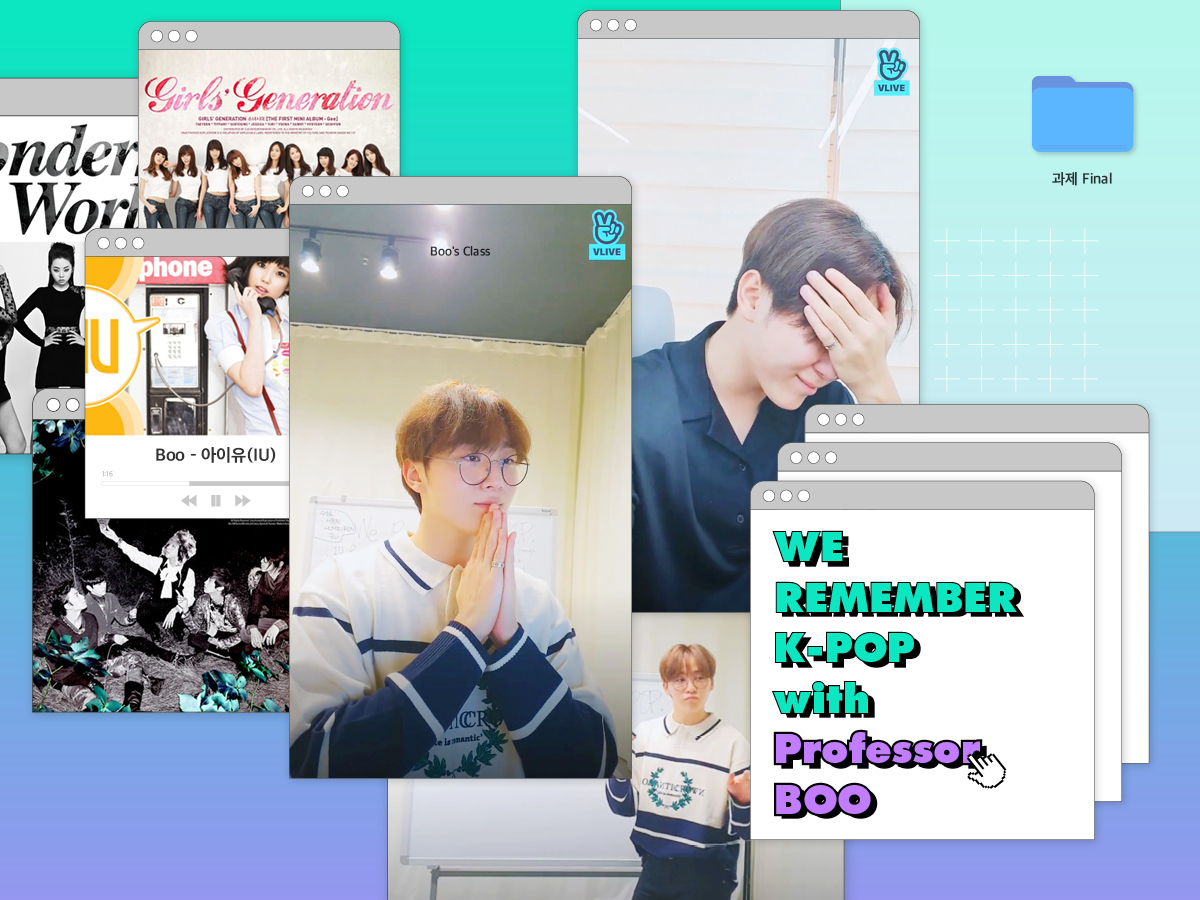FEATURE
『We Remember K-pop』、1990年代生まれの思い出探し
「隠れて聴く名曲」から「BU教授」の講義まで、1990年代生まれのK-POP
2021.06.15
「Twitterで、ONFのファンダムFUSEがリツイートし、THE BOYZのファンダムTHE Bがメンションをつけたことで知った」。某アイドル・グループのファンダムのホヨン氏が、「BU教授」と呼ばれるSEVENTEENのメンバーSEUNGKWANのV LIVE『We Remember K-pop』を知るに至った過程である。『We Remember K-pop』は昨年5月、SEUNGKWANがSEVENTEENのファンダムCARATに向け、普段から好きな歌を歌って聴かせていたV LIVE『歌を聴きたいCARAT集まれ』の途中で誕生した。バラードをメインに歌っていたSEUNGKWANは、ある瞬間から聴かせたい歌も合わせてかけ始め、それらの曲は彼が学生時代を過ごした2000年代後半から2010年代序盤までのK-POPだった。SEUNGKWANが、選曲した歌を曲に合わせて歌いながら、聴きどころを語って思い出に浸り、好きな歌を共有することを楽しむ姿は、SNSのタイムラインに載り、いつの間にか他のファンダムたちの間でも噂になり始め、K-POPファンたちが集まって自分たちが好きだった歌とアイドルの話をする場となった。SEUNGKWANはその後9月から本格的に『We Remember K-pop』を通して、10年余り前のK-POPを選曲し、K-POPに対する愛を伝えており、その時代の歌についての思い出と情報をぎっしり詰め込み語る情熱的な姿に、アイドル・ファンたちは彼を「BU教授」と呼び始めた。
さまざまなK-POPの映像を共有するTwitterアカウント「kpop_choochun」は、「BU教授」の「過去問題集アカウント」として話題にもなった。SEUNGKWANがV LIVEで取り上げた曲が、「kpop_choochun」で載せた曲と重なることが多かったからだ。「2010年前後に学生時代を過ごし、その頃の曲を聴くと特定の思い出が蘇る。学生時代の友だちに会った時も、その時代の音楽の話が必ず出てくる」という「kpop_choochun」の運営者の言葉の通り、彼もSEUNGKWANも10年余り前に学生時代を過ごしているからこそ可能なことだ。SEUNGKWANが『Weverse Magazine』のインタビューで「アイドルが好きな友だちと塾で会うと、今週の音楽番組の1位はあのグループがなりそうという話になった」と語っていたように、その時代のK-POPは、10代たちが会えば、互いに気軽に話せる話題だった。スマートフォンを通じたコンテンツ消費が始まったばかりの2010年代序盤は、テレビの影響力が依然として大きく、SBS『強心臓』などのテレビのトークショーでは、毎週人気アイドルたちが出演していた。もう少し遡れば、Wonder Girlsの「Tell Me」などのガールズ・グループのダンスと「フック」(印象的なフレーズ)を、世代を問わずまねてインターネットにアップする「UCC(User Created Contents)」という単語が、新たにメディア環境を象徴する単語になったりもしていた。「kpop_choochun」の運営者が「2008年以降を一種のK-POP黄金期」として記憶している理由だ。その頃学生時代を過ごした現在の20代たちにとってK-POPは、ともに聴き、互いに話さずにはいられない日常の一部だったと言っても過言ではない。SEUNGKWANはV LIVEで学生時代をこのように振り返った。「特技自慢の時、8つのクラスは『Gee』を、別のクラスは『Way To Go』(ともに少女時代)を、それからまた別のクラスは『8282』(Davichi)を歌った」。
どの世代も大人になれば、自身が学生時代をともにした歌を大切に思うものだ。2010年MBC『遊びに来て』は1970〜80年代のフォーク音楽に再び注目させた「セシボン・ブーム」(セシボンは70年代にフォーク・ブームを巻き起こした実在の音楽喫茶)を起こし、MBC『無限挑戦』は2014〜2015年に特別企画として放映された『土曜日、土曜日は歌手だ』で、1990年代に活動した第1世代アイドルに再びスポットを当てた。以降1990年代から2000年代序盤に人気を集めていたが、長く活動を続けておらず、近況が不明だった歌手たちを訪ねるJTBC『シュガーマン』が2019年のシーズン3まで続き、話題になった。YouTubeチャンネル『文明特急』の中で、2018年末からアップされた「隠れて聴く名曲」と最近の「再びカムバックしてもかまわない名曲」は、そのような流れの延長線上にあるように思える。だが、発表当時それほど大きな人気を集められなかった曲を再発掘する、『文明特急』のこの二つの企画のK-POPの扱い方は、前述のテレビ番組とは異なる。『文明特急』をはじめ、『We Remember K-pop』、「kpop_choochun」など、1990年代生まれがK-POPを懐かしむコンテンツは、YouTube、V LIVE、SNSなど、テレビではないメディアから誕生した。2020年代のメディア環境が、YouTubeをはじめとしたインターネット・メディアが主流だと言ってもいいほど成長したためでもあるが、1990年代生まれがまさにこのメディアでコンテンツを作る主体となっているためだ。『文明特急』のホン・ミンジPDは、「『再びカムバックしてもかまわない名曲』もまた、チャンネル登録者からの提案メールから始まった企画」だと言い、『文明特急』の企画を「これが私たちの文化なのに、知らなかったんですか。私たちにとってはあまりに当たり前のことです」というスタンスで作っていこうと思ったと説明している。同PDは「スタッフたちが1990年代生まれの当事者であり、番組の主催者であったため、外部から、まるで第三者が眺めているかのように語らないことができた」と言い、1990年代生まれがニュー・メディア・コンテンツの制作者であり、素材の決定権を持つ者だということもまた、『文明特急』の企画に大きく作用していると強調する。
「隠れて聴く名曲」と「再びカムバックしてもかまわない名曲」以外にも、『文明特急』は2000年代序盤、10代たちの心をさらった、いわゆる「インターネット小説」の有名作家であるクィヨニの元を直接訪れたり、最近数年の間オンラインで一度は聞いたことがあるだろう、「さようなら、皆さん」という動画メッセージ(アニメ『犬夜叉』のワンシーン)の声優を訪ねたりもした。『文明特急』は、テレビのようなマスメディア、またはレガシー・メディアでは記憶されない1990年代生まれの文化的経験を探し、現在時点での新たな意味を持たせる作業を地道に続けてきた。「隠れて聴く名曲」と「再びカムバックしてもかまわない名曲」もまた、そのような試みの一部だと言える。1990年代生まれが彼らの視点で立て直す2010年代。または1990年代生まれの思い出探し。1theKのオリジナル・チャンネル『私たちが愛した歌』は、2000年代後半から2010年代のK-POPの代表曲を、新人アイドルがカバーする企画だ。そのうち一部の企画に参加したKakao EntertainmentのノウルPDは、「1theKチャンネルの他の映像に比べ、このシリーズは、視聴している国とコメントの反応すべてのデータにおいて、韓国国内視聴者と18〜24歳の年齢層が圧倒的に多かった」と話す。『私たちが愛した歌』シリーズの選曲と衣装選びもまた、「1990年代生まれのため、自分が経験してきたアイテムを前半部分に入れ、後半にはその頃を経験した、当社のインターンたちの意見を多く反映」した結果だ。
さまざまなK-POPの映像を共有するTwitterアカウント「kpop_choochun」は、「BU教授」の「過去問題集アカウント」として話題にもなった。SEUNGKWANがV LIVEで取り上げた曲が、「kpop_choochun」で載せた曲と重なることが多かったからだ。「2010年前後に学生時代を過ごし、その頃の曲を聴くと特定の思い出が蘇る。学生時代の友だちに会った時も、その時代の音楽の話が必ず出てくる」という「kpop_choochun」の運営者の言葉の通り、彼もSEUNGKWANも10年余り前に学生時代を過ごしているからこそ可能なことだ。SEUNGKWANが『Weverse Magazine』のインタビューで「アイドルが好きな友だちと塾で会うと、今週の音楽番組の1位はあのグループがなりそうという話になった」と語っていたように、その時代のK-POPは、10代たちが会えば、互いに気軽に話せる話題だった。スマートフォンを通じたコンテンツ消費が始まったばかりの2010年代序盤は、テレビの影響力が依然として大きく、SBS『強心臓』などのテレビのトークショーでは、毎週人気アイドルたちが出演していた。もう少し遡れば、Wonder Girlsの「Tell Me」などのガールズ・グループのダンスと「フック」(印象的なフレーズ)を、世代を問わずまねてインターネットにアップする「UCC(User Created Contents)」という単語が、新たにメディア環境を象徴する単語になったりもしていた。「kpop_choochun」の運営者が「2008年以降を一種のK-POP黄金期」として記憶している理由だ。その頃学生時代を過ごした現在の20代たちにとってK-POPは、ともに聴き、互いに話さずにはいられない日常の一部だったと言っても過言ではない。SEUNGKWANはV LIVEで学生時代をこのように振り返った。「特技自慢の時、8つのクラスは『Gee』を、別のクラスは『Way To Go』(ともに少女時代)を、それからまた別のクラスは『8282』(Davichi)を歌った」。
どの世代も大人になれば、自身が学生時代をともにした歌を大切に思うものだ。2010年MBC『遊びに来て』は1970〜80年代のフォーク音楽に再び注目させた「セシボン・ブーム」(セシボンは70年代にフォーク・ブームを巻き起こした実在の音楽喫茶)を起こし、MBC『無限挑戦』は2014〜2015年に特別企画として放映された『土曜日、土曜日は歌手だ』で、1990年代に活動した第1世代アイドルに再びスポットを当てた。以降1990年代から2000年代序盤に人気を集めていたが、長く活動を続けておらず、近況が不明だった歌手たちを訪ねるJTBC『シュガーマン』が2019年のシーズン3まで続き、話題になった。YouTubeチャンネル『文明特急』の中で、2018年末からアップされた「隠れて聴く名曲」と最近の「再びカムバックしてもかまわない名曲」は、そのような流れの延長線上にあるように思える。だが、発表当時それほど大きな人気を集められなかった曲を再発掘する、『文明特急』のこの二つの企画のK-POPの扱い方は、前述のテレビ番組とは異なる。『文明特急』をはじめ、『We Remember K-pop』、「kpop_choochun」など、1990年代生まれがK-POPを懐かしむコンテンツは、YouTube、V LIVE、SNSなど、テレビではないメディアから誕生した。2020年代のメディア環境が、YouTubeをはじめとしたインターネット・メディアが主流だと言ってもいいほど成長したためでもあるが、1990年代生まれがまさにこのメディアでコンテンツを作る主体となっているためだ。『文明特急』のホン・ミンジPDは、「『再びカムバックしてもかまわない名曲』もまた、チャンネル登録者からの提案メールから始まった企画」だと言い、『文明特急』の企画を「これが私たちの文化なのに、知らなかったんですか。私たちにとってはあまりに当たり前のことです」というスタンスで作っていこうと思ったと説明している。同PDは「スタッフたちが1990年代生まれの当事者であり、番組の主催者であったため、外部から、まるで第三者が眺めているかのように語らないことができた」と言い、1990年代生まれがニュー・メディア・コンテンツの制作者であり、素材の決定権を持つ者だということもまた、『文明特急』の企画に大きく作用していると強調する。
「隠れて聴く名曲」と「再びカムバックしてもかまわない名曲」以外にも、『文明特急』は2000年代序盤、10代たちの心をさらった、いわゆる「インターネット小説」の有名作家であるクィヨニの元を直接訪れたり、最近数年の間オンラインで一度は聞いたことがあるだろう、「さようなら、皆さん」という動画メッセージ(アニメ『犬夜叉』のワンシーン)の声優を訪ねたりもした。『文明特急』は、テレビのようなマスメディア、またはレガシー・メディアでは記憶されない1990年代生まれの文化的経験を探し、現在時点での新たな意味を持たせる作業を地道に続けてきた。「隠れて聴く名曲」と「再びカムバックしてもかまわない名曲」もまた、そのような試みの一部だと言える。1990年代生まれが彼らの視点で立て直す2010年代。または1990年代生まれの思い出探し。1theKのオリジナル・チャンネル『私たちが愛した歌』は、2000年代後半から2010年代のK-POPの代表曲を、新人アイドルがカバーする企画だ。そのうち一部の企画に参加したKakao EntertainmentのノウルPDは、「1theKチャンネルの他の映像に比べ、このシリーズは、視聴している国とコメントの反応すべてのデータにおいて、韓国国内視聴者と18〜24歳の年齢層が圧倒的に多かった」と話す。『私たちが愛した歌』シリーズの選曲と衣装選びもまた、「1990年代生まれのため、自分が経験してきたアイテムを前半部分に入れ、後半にはその頃を経験した、当社のインターンたちの意見を多く反映」した結果だ。
SEUNGKWANに学生時代の音楽鑑賞について尋ねた時、彼は「あの頃毎月1日になると、『アル』や『ティン』(当時の携帯電話の学生向けの料金制度)で呼び出し音を1曲だけ設定できるので、一番好きな曲を選びに選んで設定したりした」と当時を振り返った。今の10代には馴染みがない「アル」や「ティン」のように、1990年代生まれが大衆文化コンテンツを消費する方法は急変した。『私たちが愛した歌』シリーズに登場する二つ折り携帯やミッキーマウス型のMP3プレーヤーがスマートフォンに置き換わるのにかかった時間は、わずか10年余りだった。テキスト・ファイルや音源物理ファイルを入れることができた電子辞書、または映像ファイルも見られたポータブル・メディア・プレーヤーが急速に登場しては消えていった時期でもあった。1940年代から使われていたLPにカセットテープとCDが、そしてMP3などの物理ファイルがCDに取って代わり始めた周期と比べると、あまりにも急激な変化だった。音楽だけではなかった。10代から20代に移る間に、ハドゥリ(ビデオチャット・サービス)がCyworldに、そしてFacebookとInstagramに替わった。これらのSNSで他の利用者とDM(Direct Message)をやりとりしていると、buddybuddyやnate onのようなメッセンジャー・サービスはまるで存在しなかったかのようにも感じられる。それ以前の世代は若い頃ずっと同じやり方でコンテンツを楽しんで使用し、30〜40代の大人世代になる頃に時代の変化を体感して、学生時代の音楽を思い出として消費した。一方1990年代生まれは学生時代、大事に扱ってきた音楽プレーヤーも、メッセンジャーも、メッセンジャーの中で友だちと語り合った記録も、製造中止やサービス終了により消えてなくなった。学生時代の経験が、社会に出る頃にはすでにどこにも見つけることができないものとなっており、彼らは大人世代よりもう少し早く彼らの思い出を自ら探し始めた。
1990年代生まれがK-POPを思い出すことは、それ故、社会から消えた彼らの経験を公式に歴史として残す作業になってもいる。1990年代生まれが中心となってその時代のK-POPを思い出すコンテンツを作り、それがまたその世代によってインターネットのあちこちに広がっていく。「隠れて聴く名曲」の映像がアップされたり、BU教授の講義が終わると、YouTubeや音源プラットフォームには、紹介された音楽をプレイリストの形にして共有する。またBU教授の講義は、V LIVE終了後に縮約版の映像に編集されて再びアップされ、『文明特急』や『私たちが愛した歌』は、画像や短い動画の形に変わってSNSや掲示板にすぐに共有される。この10年余りの間、本人たちが望むと望まざるとにかかわらずアーリーアダプター(新たな商品、サービスなどを早期に取り入れる利用者層)であるほかなかったこの世代は、その変化についていくと同時に、その時代に愛していた大衆文化コンテンツを通して彼らだけの共通の話題を思い出させ、共有して連帯感を持つ。
10代の頃のSEUNGKWANが聴き、20代のBU教授が講義する、または『文明特急』や『私たちが愛した歌』の制作陣が作る、そして「kpop_choochun」の運営者やアイドル・ファンのホヨン氏が愛するK-POPは、失われることのないこの世代の経験をつなぐ接点だ。MP3を使っていた10代の頃からYouTubeで音楽を聴く現在まで、その時代のK-POPは今も変わらず彼らのそばにある。多くの大衆文化コンテンツが登場しては消える間にも、その時代のK-POPの名曲は、YouTubeでいくらでも資料を探すことができ、今彼らが聴いている新たなK-POPにもたくさんの影響を及ぼしている。そして第2世代アイドルの曲を、第3世代と第4世代のアイドルたちが登場した今、聴き語る過程で、1990年代生まれはK-POPを媒介として彼らの10代を大人の目線で振り返る。ホン・ミンジPDは、「隠れて聴く名曲」の企画の初期段階を振り返り、「資料画面を探しているときに、あの当時のアイドルのステージ映像を見たが、自分がカメラに捉えられていなくても一生懸命にパフォーマンスをする姿が、プロフェッショナルだと感じた。それは学生の頃には見えていなかったのだが、大人になって改めて見ると、その中にある努力が見えた」と語る。『文明特急』がアイドルを扱う原則の一つとして、ホン・ミンジPDが「彼らをプロと認識して向き合う姿勢」を挙げた理由だ。「ただ踊って歌う人としてだけ消費するのではなく、K-POP分野で専門的に成長する、社会の新人として表現したかった。彼らは社会人として最善を尽くしている」というのだ。社会に出てみると、自分の学生時代を楽しくしてくれた歌は、その時代のアイドルたちがステージの上やそれ以外で努力した結果だった。10代の頃には、学生であるためによくわからなかったり、両親や周りの大人たちのネガティブな視線や偏見により認知できなかった価値が、今や社会生活を経験する年齢になった1990年代生まれには見える。彼らにとって10年余り前のK-POPは、ただ単にその時代を思い出す手段ではない。すべてが急速に変わった10代を過ぎ、20代になった彼らは、K-POPを通して自身の人生が子どもの頃からつながっていることを確認する。言い換えれば、自分の思い出が消えないようにしてくれる過去の音楽は、現在を生きていくための力だ。今まさに社会に出なければならない者たちにとっては、なおのことだ。
BU教授の受講生たちは、時に「K-POPコインムル(溜水)」とも呼ばれる。ホヨン氏はこのような呼び名について、「語源は愉快な感じではないので、気をつけて使うべき言葉ではある。しかし、止まっている水の中には溜まって腐る水もあるだろうが、同時に浄水を経て飲むことができる有益な水にもなる」という立場を語った。「kpop_choochun」アカウントの運営者もホヨン氏も、過去のK-POPを楽しむと同時に、最近出たK-POPも誰より早く幅広く聴いている人たちだった。以前の音楽を聴きながら、学生時代の友だちとの思い出を振り返ったり、運動したり仕事をする時流して聴く楽しみも存在する。ただひたすらに幸せだったと言うのは難しいだろうが、何かを、後先考えることなくひたむきに好きになれた時代に対する懐かしさも存在するだろう。だが、社会的に消えてしまったも同然な自分たちの10代を復元する過程は、その頃の音楽を努力の結果として尊重し、彼ら世代の言語として肯定しながら、新たな美しさと価値を見出すことでもある。その結果、その歌を歌った人、聴いていた人すべての人生を肯定することにまで広がっていく。そう考えると1990年代に生まれたこの「K-POPコインムル」たちは、実は波に似た人たちかもしれない。繰り返し引き返すように見えるが、実は水の流れに沿って絶えず形と高さを変えながら適応し、いつかは広々とした大海に向かうことを願う人たち。
1990年代生まれがK-POPを思い出すことは、それ故、社会から消えた彼らの経験を公式に歴史として残す作業になってもいる。1990年代生まれが中心となってその時代のK-POPを思い出すコンテンツを作り、それがまたその世代によってインターネットのあちこちに広がっていく。「隠れて聴く名曲」の映像がアップされたり、BU教授の講義が終わると、YouTubeや音源プラットフォームには、紹介された音楽をプレイリストの形にして共有する。またBU教授の講義は、V LIVE終了後に縮約版の映像に編集されて再びアップされ、『文明特急』や『私たちが愛した歌』は、画像や短い動画の形に変わってSNSや掲示板にすぐに共有される。この10年余りの間、本人たちが望むと望まざるとにかかわらずアーリーアダプター(新たな商品、サービスなどを早期に取り入れる利用者層)であるほかなかったこの世代は、その変化についていくと同時に、その時代に愛していた大衆文化コンテンツを通して彼らだけの共通の話題を思い出させ、共有して連帯感を持つ。
10代の頃のSEUNGKWANが聴き、20代のBU教授が講義する、または『文明特急』や『私たちが愛した歌』の制作陣が作る、そして「kpop_choochun」の運営者やアイドル・ファンのホヨン氏が愛するK-POPは、失われることのないこの世代の経験をつなぐ接点だ。MP3を使っていた10代の頃からYouTubeで音楽を聴く現在まで、その時代のK-POPは今も変わらず彼らのそばにある。多くの大衆文化コンテンツが登場しては消える間にも、その時代のK-POPの名曲は、YouTubeでいくらでも資料を探すことができ、今彼らが聴いている新たなK-POPにもたくさんの影響を及ぼしている。そして第2世代アイドルの曲を、第3世代と第4世代のアイドルたちが登場した今、聴き語る過程で、1990年代生まれはK-POPを媒介として彼らの10代を大人の目線で振り返る。ホン・ミンジPDは、「隠れて聴く名曲」の企画の初期段階を振り返り、「資料画面を探しているときに、あの当時のアイドルのステージ映像を見たが、自分がカメラに捉えられていなくても一生懸命にパフォーマンスをする姿が、プロフェッショナルだと感じた。それは学生の頃には見えていなかったのだが、大人になって改めて見ると、その中にある努力が見えた」と語る。『文明特急』がアイドルを扱う原則の一つとして、ホン・ミンジPDが「彼らをプロと認識して向き合う姿勢」を挙げた理由だ。「ただ踊って歌う人としてだけ消費するのではなく、K-POP分野で専門的に成長する、社会の新人として表現したかった。彼らは社会人として最善を尽くしている」というのだ。社会に出てみると、自分の学生時代を楽しくしてくれた歌は、その時代のアイドルたちがステージの上やそれ以外で努力した結果だった。10代の頃には、学生であるためによくわからなかったり、両親や周りの大人たちのネガティブな視線や偏見により認知できなかった価値が、今や社会生活を経験する年齢になった1990年代生まれには見える。彼らにとって10年余り前のK-POPは、ただ単にその時代を思い出す手段ではない。すべてが急速に変わった10代を過ぎ、20代になった彼らは、K-POPを通して自身の人生が子どもの頃からつながっていることを確認する。言い換えれば、自分の思い出が消えないようにしてくれる過去の音楽は、現在を生きていくための力だ。今まさに社会に出なければならない者たちにとっては、なおのことだ。
BU教授の受講生たちは、時に「K-POPコインムル(溜水)」とも呼ばれる。ホヨン氏はこのような呼び名について、「語源は愉快な感じではないので、気をつけて使うべき言葉ではある。しかし、止まっている水の中には溜まって腐る水もあるだろうが、同時に浄水を経て飲むことができる有益な水にもなる」という立場を語った。「kpop_choochun」アカウントの運営者もホヨン氏も、過去のK-POPを楽しむと同時に、最近出たK-POPも誰より早く幅広く聴いている人たちだった。以前の音楽を聴きながら、学生時代の友だちとの思い出を振り返ったり、運動したり仕事をする時流して聴く楽しみも存在する。ただひたすらに幸せだったと言うのは難しいだろうが、何かを、後先考えることなくひたむきに好きになれた時代に対する懐かしさも存在するだろう。だが、社会的に消えてしまったも同然な自分たちの10代を復元する過程は、その頃の音楽を努力の結果として尊重し、彼ら世代の言語として肯定しながら、新たな美しさと価値を見出すことでもある。その結果、その歌を歌った人、聴いていた人すべての人生を肯定することにまで広がっていく。そう考えると1990年代に生まれたこの「K-POPコインムル」たちは、実は波に似た人たちかもしれない。繰り返し引き返すように見えるが、実は水の流れに沿って絶えず形と高さを変えながら適応し、いつかは広々とした大海に向かうことを願う人たち。
文. ユン・ヘイン
デザイン. ナム・デヒョン(south_big)
ビジュアルディレクター. チョン・ユリム
Copyright © Weverse Magazine. All rights reserved.
無断転載及び再配布禁止
無断転載及び再配布禁止
Read More
- HOSHI、パフォーマンス・チームのリーダー2021.04.16

- 세븐틴의 새 앨범, 들어봤나요?2020.10.20
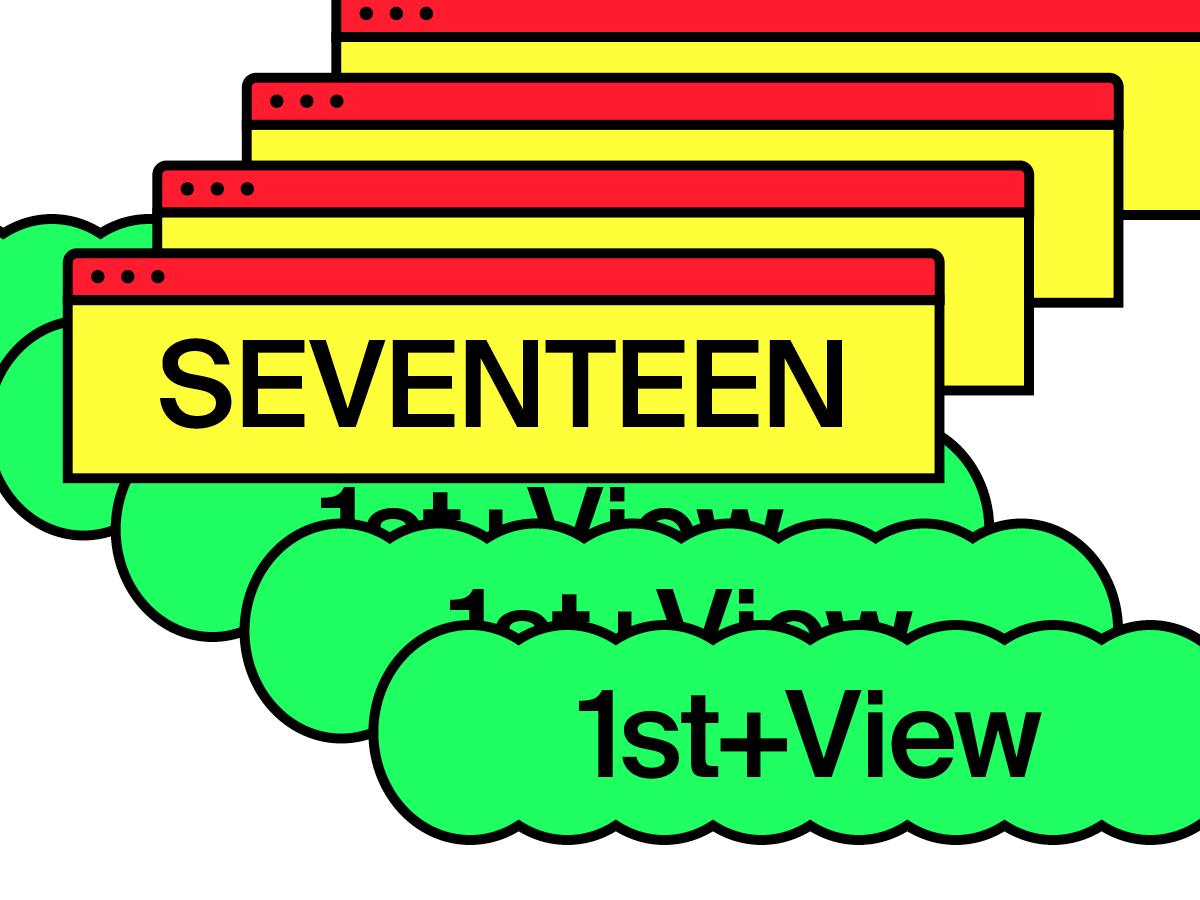
- 2020 SEVENTEENのパフォーマンス2020.12.30

- BU教授の過ぎ去りし時代の思い出し方2021.06.14