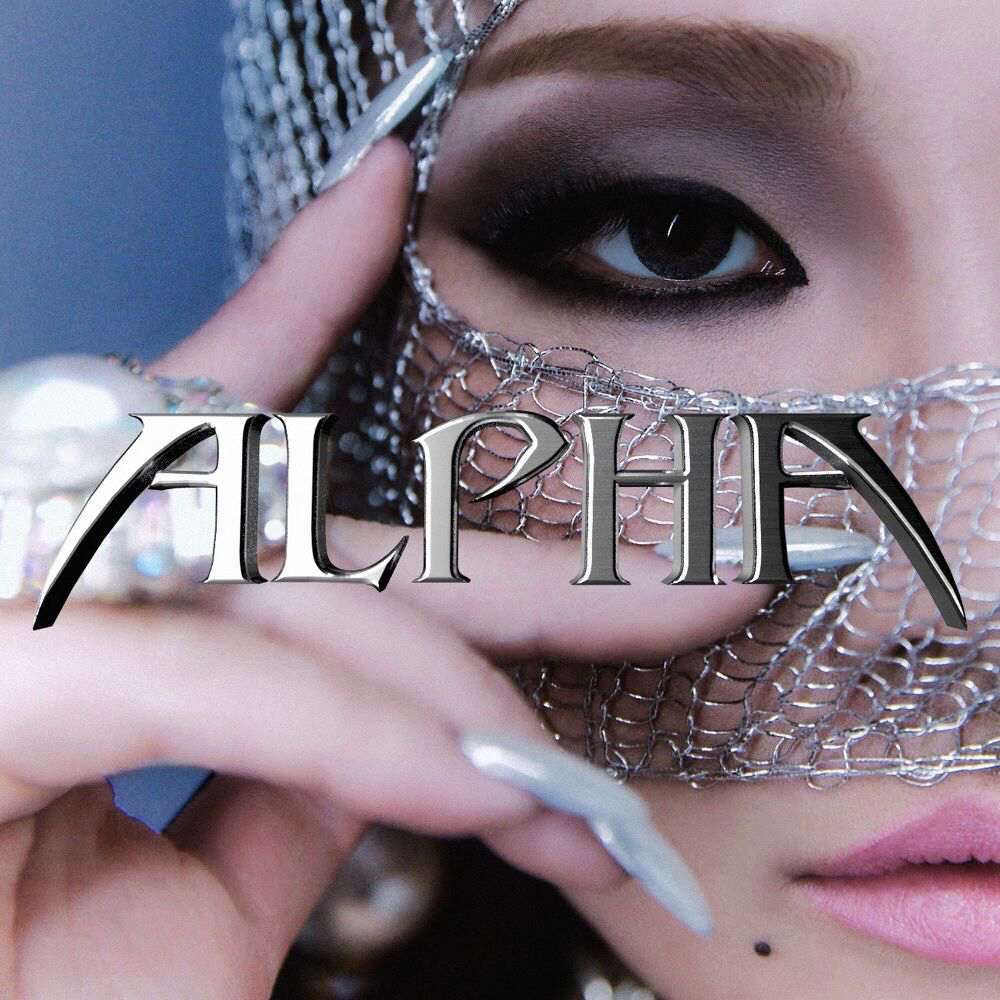
REVIEW
CLという名前で
CLの初ソロ・フルアルバム『ALPHA』の話
2021.11.22
Credit
文. ナ・ウォニョン(大衆音楽批評家)
写真. Very Cherry
デビュー12年、ソロ活動8年、アメリカデビュー5年、独り立ち2年で出されるポップスターの初アルバムに対し、何を期待できるだろうか。そもそもCLの初めてのソロ・フルアルバムが今、発売されたという事実自体が、彼女がこれまで突き抜けてきた過程を意味するだろう。『ALPHA』は、そうやって集められた時間から未来を描いてみる青写真にもなる。それだけでなく、「独立的なポップスター」であり「世界的な韓国語圏のソロ歌手」でもあるかなり珍しい立ち位置で、CLのポップスは音楽評論家のサイモン・フリス(Simon Frith)の話の通り、「自らすべてをやりこなす音楽ではなく、専門的に制作され包装される」工程によって作られる。そのような見方からすると、『ALPHA』では反対方向に働くそれぞれ異なる力が極度に緊張したまま張り合っていることになる。このようなアルバムは、過去を締めくくりながらも未来を描いて(みなければならず)、様々な人物が至る所に参加するも結局、単一の名前の下、完成される。ポップスターのアルバムとして『ALPHA』に期待できるのは、まさにそのように働く複数の力が結合して作られた音楽の中でCLが見つけたバランスポイントだ。
『ALPHA』は、CLという名前にふさわしい様々なサウンドで飾られた。片方には「THE BADDEST FEMALE」と「Hello Bitches」の延長として作曲されたという「SPICY」で代表されるトラックがある。極めて短く区切られた尺をループさせながら攻撃的なベースの音を単発的に弾きまくるビートは、単純明快なフックをしっかりと支えてくれる。その上には、(YG時代のそのすべてのフックを時々連想させる)耳慣れた「韓国のメロディ」の中でも図らずも最も有名になった旋律と語句を選び取った「ムクゲの花が咲きました / しっかり隠れて、髪の毛見えるぞ(「H₩A」)」や、そういうベタな受け売りの当為を堂々と示す「Imma do it my way(「My Way」)」といった句がつけられる。もちろん、そのような「私が歩んできた通り ありのままの私らしく(「My Way」)」には多数のスタッフを動員し、「私」らしいサウンドを調整する手が加えられている。中でも最も馴染みのあるバンガー(Banger)に近い『ALPHA』のトラックは、ソロ活動初期のようにどっしりした低音部で直撃したり、ポップスター的なブラガドシオ(braggadocio)を誇張せず、CLのボーカル・トーンに似合うように上手にブラッシュアップされた。そのような仕上げは、料理の上にペッパーソースをまんべんなくかけ、「辛味」の感覚を統一させることのように機能するが、CLが自分自身を出すために今は別に飾りつける必要がなかったから(「私はフリなんてしない すぐ見破る(「Chuck」)」)ではないだろうか。そうやって『ALPHA』の中の辛味はアルバムのスタートを切る「SPICY」からアルバム全体にわたって期待できる風味を効率よく示しており、もちろんそこには辛味しかないわけでもない。
『ALPHA』は、CLという名前にふさわしい様々なサウンドで飾られた。片方には「THE BADDEST FEMALE」と「Hello Bitches」の延長として作曲されたという「SPICY」で代表されるトラックがある。極めて短く区切られた尺をループさせながら攻撃的なベースの音を単発的に弾きまくるビートは、単純明快なフックをしっかりと支えてくれる。その上には、(YG時代のそのすべてのフックを時々連想させる)耳慣れた「韓国のメロディ」の中でも図らずも最も有名になった旋律と語句を選び取った「ムクゲの花が咲きました / しっかり隠れて、髪の毛見えるぞ(「H₩A」)」や、そういうベタな受け売りの当為を堂々と示す「Imma do it my way(「My Way」)」といった句がつけられる。もちろん、そのような「私が歩んできた通り ありのままの私らしく(「My Way」)」には多数のスタッフを動員し、「私」らしいサウンドを調整する手が加えられている。中でも最も馴染みのあるバンガー(Banger)に近い『ALPHA』のトラックは、ソロ活動初期のようにどっしりした低音部で直撃したり、ポップスター的なブラガドシオ(braggadocio)を誇張せず、CLのボーカル・トーンに似合うように上手にブラッシュアップされた。そのような仕上げは、料理の上にペッパーソースをまんべんなくかけ、「辛味」の感覚を統一させることのように機能するが、CLが自分自身を出すために今は別に飾りつける必要がなかったから(「私はフリなんてしない すぐ見破る(「Chuck」)」)ではないだろうか。そうやって『ALPHA』の中の辛味はアルバムのスタートを切る「SPICY」からアルバム全体にわたって期待できる風味を効率よく示しており、もちろんそこには辛味しかないわけでもない。
従来のポップス的な方向性を保ったまま密かな感情とボーカル・ラインに重きをともに置いた「+PARADOX17115+」や「+I QUIT180327+」などの影響力の延長線上のトラックも『ALPHA』を成していくまた違う力だ。それは、込み上げるようなシンセ音と密度の高いリズム区間で盛り上げたテンションをサビのメロディで徐々に高めていく「Xai」や、さらに劇的にサウンドを入れたり取ったりすることでアルバムの後半を飾る「Siren」と「5 STAR」で目立って見える。ただし、『In The Name Of Love』を埋めていた感情的なハイライトは、『ALPHA』の前出のトラックのより重みのあるトラップ風のポップス・サウンドを通り過ぎ、「Lover Like Me」と「Tie a Cherry」で落としどころを見つけたように見える。そのおかげでこの両トラックは、スタイルと感情の側面でアルバムにおける主な軸になる。CL固有の声を輝かせるべく、上手に滑り降りていくサビのメロディとドロップに向かって着実にビルドアップを重ねていく構造に沿った進行と(「Tie a Cherry」)、ビートの華やかな音色に合わせてラップ区間を差し込むタッチ(「Lover Like Me」)がいい塩梅に混ざっている。『ALPHA』におけるバランスポイントはこのように、CLのソロ経歴で見つけられてきたいろんな味を少しずつ異なる性質やスタイル、サウンドで構成されたトラックと各部分にくまなく混ぜ合わせる方法で見いだされる。
特に、2NE1のメンバー全員が揃った形を想定し作られたという「Let It」と、もしかするとCLの磁場では距離が最も離れていると考えられ、トラヴィス・スコット(Travis Scott)のようなリファレンスも連想される「Paradise」の手掛け方からこのことがよくわかる。エレクトリック・ギターで先頭を切る「Let It」では、わりとゆっくりめの拍とビートのリズム感のため「If I Were You」や「It Hurts」、はたまた「Come Back Home」の導入部などを思い出させるに十分足りる。一方、うねりのあるメロディに沿ってオートチューンを微妙にかけたラップがつぶやきのように入った「Paradise」でも、2010年代半ばから後半のメジャーなヒップホップとポップラップを難なく指し示すに足りる。CLが過去の活動の残滓と同時代の一番流行りのサウンドを組み合わせただけだと言えるかもしれないが、当該スタイルを取り入れたことにより、サウンドがかけ離れてしまったり目立ちすぎたりすることなく、むしろ『ALPHA』の全体像にもっと似合う形で組み込まれたことに意義を持ちたい。オートチューンの運用や合いの手の入れ方において、「Paradise」はメロディ・ラインを適度に包むくらいでこれらを施しており、このようなアプローチは、当代のトレンドを取り入れる時の損失を甘受してでもCLの磁場に当該スタイルを取り込んだ2010年代半ばのトラックでも同様だった。似たような形で、「Let It」でも2NE1のいろんな「キラキラ」した特色のあるサウンドを取り払う代わりに節制したビートを取り入れることでメロディを強調しており、このような例からすると、CLが『ALPHA』というレシピにこれらの材料を見事に盛り込めたように聴こえる。作詞家にTablo、sokodomo、naflaが名を連ねてはいるが、ラップそのものではCLの耳慣れたフローに参加者らのスタイルが遡及されたとしても似通ったものになっただろう。どんなスタイルやスタッフをその材料として用いても、『ALPHA』でそれははっきりとCLのもののように感じられる。
特に、2NE1のメンバー全員が揃った形を想定し作られたという「Let It」と、もしかするとCLの磁場では距離が最も離れていると考えられ、トラヴィス・スコット(Travis Scott)のようなリファレンスも連想される「Paradise」の手掛け方からこのことがよくわかる。エレクトリック・ギターで先頭を切る「Let It」では、わりとゆっくりめの拍とビートのリズム感のため「If I Were You」や「It Hurts」、はたまた「Come Back Home」の導入部などを思い出させるに十分足りる。一方、うねりのあるメロディに沿ってオートチューンを微妙にかけたラップがつぶやきのように入った「Paradise」でも、2010年代半ばから後半のメジャーなヒップホップとポップラップを難なく指し示すに足りる。CLが過去の活動の残滓と同時代の一番流行りのサウンドを組み合わせただけだと言えるかもしれないが、当該スタイルを取り入れたことにより、サウンドがかけ離れてしまったり目立ちすぎたりすることなく、むしろ『ALPHA』の全体像にもっと似合う形で組み込まれたことに意義を持ちたい。オートチューンの運用や合いの手の入れ方において、「Paradise」はメロディ・ラインを適度に包むくらいでこれらを施しており、このようなアプローチは、当代のトレンドを取り入れる時の損失を甘受してでもCLの磁場に当該スタイルを取り込んだ2010年代半ばのトラックでも同様だった。似たような形で、「Let It」でも2NE1のいろんな「キラキラ」した特色のあるサウンドを取り払う代わりに節制したビートを取り入れることでメロディを強調しており、このような例からすると、CLが『ALPHA』というレシピにこれらの材料を見事に盛り込めたように聴こえる。作詞家にTablo、sokodomo、naflaが名を連ねてはいるが、ラップそのものではCLの耳慣れたフローに参加者らのスタイルが遡及されたとしても似通ったものになっただろう。どんなスタイルやスタッフをその材料として用いても、『ALPHA』でそれははっきりとCLのもののように感じられる。
様々なピースが合わせられ、一つの名前とその形状を構成していくポップ・アルバムの性質が、『ALPHA』ではCL特有の声音とそれを際立たせるメロディに集中し、デビュー12年目としてのイメージをしっかり固めることで獲得できたものと見られる。それがループするビートに載せられた「リフ」のような音の連続であれ、トラック全体を展開していくボーカルの進行過程であれ、それはさておこう。もちろん、このようなメロディというバランスポイントから再び重心を辿っていくと、CLの声がある。『In The Name Of Love』よりは少し控えめに強調されたが、彼女の音楽の最も確然たる特徴である声は、太く短い尺を効果音のように繰り返し繋いだ重みのあるトラップ・ダンス曲をはじめ、よくできている感情の流れに見事に身を任せて上下するバラード的な曲に至るまで、『ALPHA』のすべての瞬間において中心になる。そのためにすでに多様に出されてきた彼女の形状をきめ細かく擦り合わせる微調整の方式は、「SPICY」の導入部であり『ALPHA』の始まりとも言える部分でも小さいながらも確実に現れる。ジョン・マルコヴィッチ(John Malkovich)に音声を録音して送ってもらった長さ5分のモノローグからアイコニックな「Energy, Power, Chemistry」だけを切り取り低音のベースに沿って散りばめ、レコーディング上発生した妙な音質のバラツキを力強いビートで整えることでCLの声を際立たせたイントロは、CLの内部や外部に存在する様々な材料の味をバランスよく混ぜて一つに作り上げた制作方法のかなりいい象徴になるだろう。
そうやって『ALPHA』は、多面的かつ分節的だったCLのこれまでの時空を「2021年の初ソロ・フルアルバム」という単位に合わせてきめ細かく加工し、均質に統合させたため、彼女の音楽とCLという人物自体にとって一枚の「青写真」になることができた。振り返ってみると、CLほど自分自身が誰なのか、そのエゴを直接表しながらもその重みにつぶされ乱れることなく、最も確然たる表にエゴの華麗なところや密かなところを同等に出しつつも一つの固定された形状をだいぶしっかりと定立できたケースは極めて稀だった。自己像に働く数々の力を効率よく司る能力もポップスターとして持つべきさらに重要な資質だとすれば、CLが『ALPHA』を通じて自分を再構成する方式は、彼女が何に長けているかを物語る。結局、自らを初めて紹介すると同時に自分自身に下した定義「I go by the name of CL」は、いつも変わらなかった。デビューから12年で出された初アルバムでもCLは、巨大な力や規模、イメージなしで効率よく自分の多くの部分を表現して見せる。「私のことをチェリンと呼んだ最後の時を覚えている? / あなたが私のことをその名前で呼んだ最後の時を覚えていない(Remember the last time you called me Chae Lin / Can't remember the last time you called me that name) (「Lover Like Me」)」と自問自答しながらも、一言ずつはっきり「C H A E L I N THAT'S ME(「Chuck」)」と歌ったり、おどけて言うダジャレや「捨てられた楽しみ(韓国語で「チェミ」) (「Siren」)」のように「チェリー」をもじり、随所に飾っておく彼女は、相変わらずCLという名前で呼ばれる。
そうやって『ALPHA』は、多面的かつ分節的だったCLのこれまでの時空を「2021年の初ソロ・フルアルバム」という単位に合わせてきめ細かく加工し、均質に統合させたため、彼女の音楽とCLという人物自体にとって一枚の「青写真」になることができた。振り返ってみると、CLほど自分自身が誰なのか、そのエゴを直接表しながらもその重みにつぶされ乱れることなく、最も確然たる表にエゴの華麗なところや密かなところを同等に出しつつも一つの固定された形状をだいぶしっかりと定立できたケースは極めて稀だった。自己像に働く数々の力を効率よく司る能力もポップスターとして持つべきさらに重要な資質だとすれば、CLが『ALPHA』を通じて自分を再構成する方式は、彼女が何に長けているかを物語る。結局、自らを初めて紹介すると同時に自分自身に下した定義「I go by the name of CL」は、いつも変わらなかった。デビューから12年で出された初アルバムでもCLは、巨大な力や規模、イメージなしで効率よく自分の多くの部分を表現して見せる。「私のことをチェリンと呼んだ最後の時を覚えている? / あなたが私のことをその名前で呼んだ最後の時を覚えていない(Remember the last time you called me Chae Lin / Can't remember the last time you called me that name) (「Lover Like Me」)」と自問自答しながらも、一言ずつはっきり「C H A E L I N THAT'S ME(「Chuck」)」と歌ったり、おどけて言うダジャレや「捨てられた楽しみ(韓国語で「チェミ」) (「Siren」)」のように「チェリー」をもじり、随所に飾っておく彼女は、相変わらずCLという名前で呼ばれる。
Copyright © Weverse Magazine. All rights reserved.
無断転載及び再配布禁止
無断転載及び再配布禁止