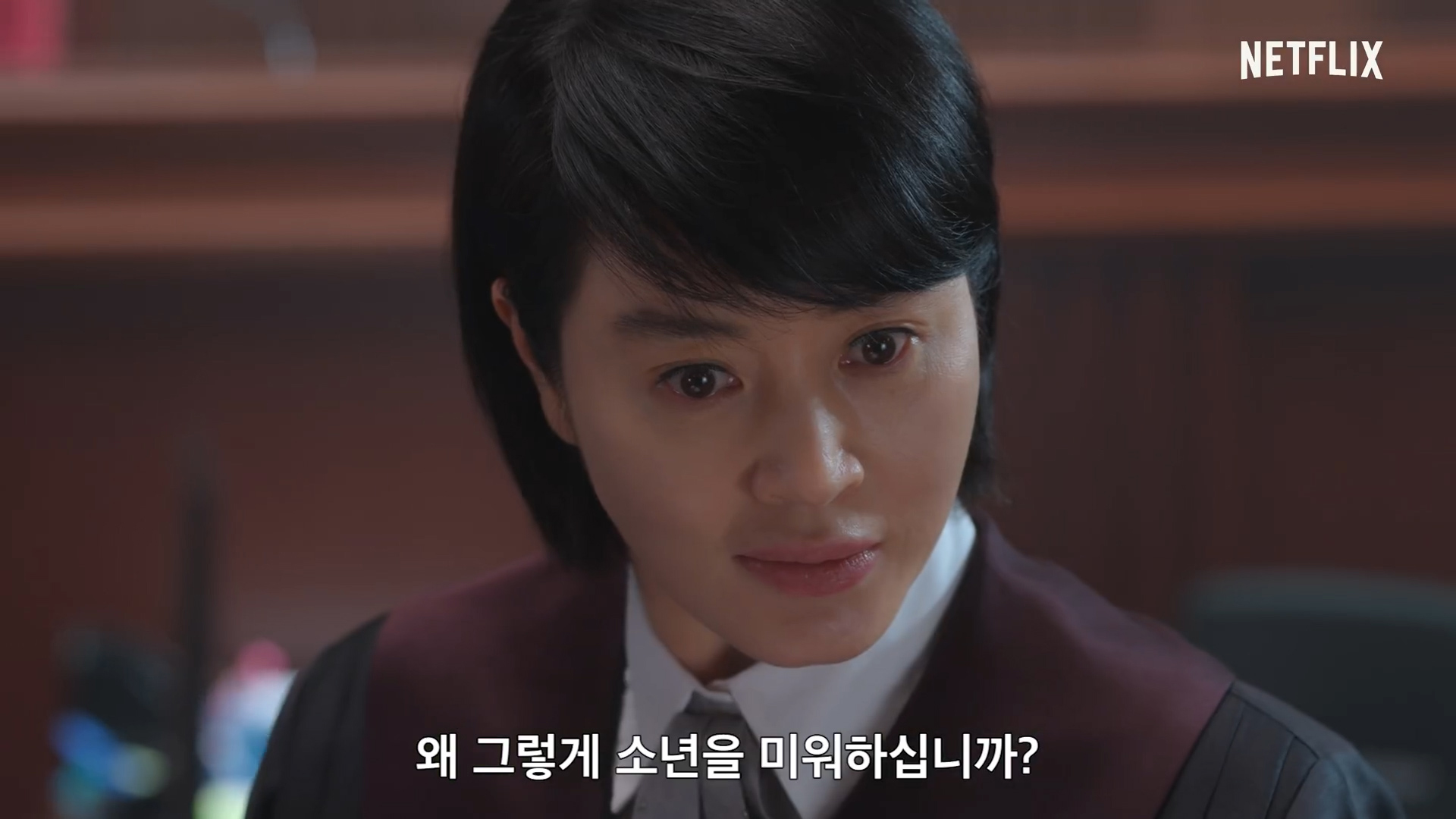去る2月20日夜、ソウルのある少年保護施設から少年犯11名が火災報知器を作動させ、自動ロック装置が解除された隙に逃走した。7名は翌日施設に戻り、2名は無人のアイスクリーム店で器物破損と窃盗の罪を犯して逃げ、4日後に捕まった。残りの2名もまた1週間後に検挙された。1か月後、この事件を報道した「国民日報」は、「犯罪映画を見ているよう…ソウルで少年犯11名が脱走劇」というタイトルをつけた。ポータルサイトに掲載されたこの記事に書き込まれたコメントの中で最も支持を得たのは、「少年法はとにかく廃止するべき」、「犯罪者たちが更生するだろうと考えることがもどかしい。彼らは大きくなったらもっとあくどい犯罪者になるだけだ」だった。続いて多かった、1,000件に近い「いいね」がついたコメントはこうだ。「私は非行少年を憎んでいます」。Netflixドラマ『未成年裁判』の主人公シム・ウンソク(キム・ヘス)のセリフだ。
シム・ウンソクは少年犯を憎んで少年部の判事になった。触法少年(満10歳以上14歳未満で刑事処罰の対象にならず、最大でも少年院2年の保護処分のみが可能な年齢)だった小学生たちのいたずらによって、子どもを失ったためだ。一方、家庭で暴力を受けていたことが原因で少年犯となったチャ・テジュ(キム・ムヨル)判事は、過去の自分と似た境遇の少年犯たちを献身的に支援する。彼らの上司カン・ウォンジュン(イ・ソンミン)部長判事は、政治的な野望ばかりを追い求めているように見えるが、実は司法制度の中で少年犯罪問題を解き明かしていこうという意志の強い人物だ。カン・ウォンジュンの後任ナ・グンヒ(イ・ジョンウン)は、過重な業務に苦しめられる少年刑事合議部で、効率化を図るために官僚統制方式を選択するが、結局その盲点に気づき、反省する。『未成年裁判』は、それぞれ異なる信念を持った4人の判事、その中でも少年犯罪に関連したトラウマに苦しめられるシム・ウンソクを中心に、さまざまな少年犯罪事件を描く。そして少年犯を憎むと言いながらも、事件の本当の真実を究明するために身を投げ打って、判事の権限を超え、捜査の領域まで縦横無尽に駆け回ったシム・ウンソクは、最後に自分の立場を改めて確立する。「私は非行少年を憎んでいます。(中略)嫌い憎めど、少年のために最善を尽くします。嫌い憎めど、冷静に処分を下します。嫌い憎めど、少年に対して偏見を持ちません」。
つまり『未成年裁判』の核心となるメッセージは、少年犯罪に関する社会の責任を問うことだ。「家庭が、そして環境が少年に影響を及ぼすのは事実ですが、さまざまな選択肢から犯罪を選んだのは結局少年です」と厳しく叱責していたシム・ウンソクは、続けて強調する。「少年は決して一人で育つわけではありません」。少年犯罪に対する私たち社会の全般的な認識が前者に近かったとすれば、後者は少年の保護者だけでなく、私たちすべての責任に向けた言葉だ。ただこの作品が伝えようとしていたことと、残したイメージの間には、微妙なギャップがあるようだ。『未成年裁判』の最初と最後で扱われていた小学生殺人事件とレンガ投石殺人事件は、どちらも触法少年と関連している。ここ数年の間に韓国社会で少年法廃止論争を触発してきた実際の事件がモチーフとなっており、ドラマではレンガ投石殺人事件の犯人たちがきちんと更生しなかった結果、集団レイプと不法撮影及びその流布という犯罪を犯す悪人に成長したという設定だ。実は少年犯罪の多数を占めている事件が生計のために犯す非行であり、暴力が過去に比べてより激しく、また残酷になっているわけではない(チョン・ジョンホ著『私が出会った少年について』)という現職判事の証言は、「子どもたちの犯罪がメディアにより凶暴にばかり描かれている。少年法の焦点は更生だ」というカン・ウォンジュンのセリフと軌を一にするが、『未成年裁判』はまさにその稀に凶暴な犯罪事件を選択し、大衆に強烈な物語を伝えているという点でジレンマに陥る。
前述の少年保護施設逃走事件の記事で、もう一つ目についたコメントはこれだ。「だから私はあんたたちが嫌いなの。更生なんてできないから。本当に『未成年裁判』のセリフが全部当てはまっているよ。ワオ」。『未成年裁判』の序盤、施設の処分を終えた少年たちと判事たちの食事の席で、他の客の財布を盗んだ少年にシム・ウンソクが言い捨てた言葉だ。シム・ウンソクはその後いくつもの事件を経て変化するが、問題はそのように少年犯に向けた嫌悪のセリフだけが爽快感のあるミーム(meme)として一人歩きし、偏見を強化することだ。記事で「犯罪映画」のようだと表現した少年保護施設の少年犯逃走事件は、すでに『未成年裁判』に登場している。青少年回復センターを献身的に運営しているオ・ソンジャ(ヨム・ヘラン)の努力にもかかわらず、いざこざが起きた隙に乗じて、少年たちはどっと逃げ出す。お金もなく行くあてもない彼らは、まもなく犯罪の誘惑に負ける。シム・ウンソクの言葉通り、少年犯罪は「犯すものではなく、染まっていくもの」だ。大多数の少年犯は、家庭内暴力-児童虐待-少年非行が密接に結びついた環境の中で作られる。ソウル家庭裁判所で少年保護裁判を担当してきたシム・ジェグァン判事はこう話す。「少年が自ら努力を怠る場合もあるが、少年の意志だけでは環境の問題に打ち勝つことができないことの方がもっと多い。少年がいくら変わっても、少年が戻っていった環境が変わらなければ、悲惨な結論は繰り返される(著書『少年のための裁判』)より」。それ故、少年の人生はそういう犯罪映画のようなものではない。
少年院で1年間国語の授業を行った経験をもとに『少年を読む』を執筆した作家ソ・ヒョンスク氏は、「加害者である少年を永遠に閉じ込めておけるなら、ただ閉じ込めればいい。閉じ込めることだけで罪を償えばいい。だがその子は、私たちの隣人として、社会の構成員として、何より魂を持った一人の存在として、私たちの傍らに立つことになるだろう。それが罪を償うその『先』を考えなければならない理由だ」と言う。「ろくな人間にならない」子どもたちだから永遠に閉じ込めてしまおうと言うことは容易い。しかしそうはできないから、その「先」を想像し、実現できるようにすることが、私たち皆の責任だ。『未成年裁判』のホン・ジョンチャン監督は、シーズン2を制作するとしたら、「少年犯の環境と彼らがそこに置かれたストーリー、少年犯たちが出現し続けるようになる社会システムを、少年犯の立場から描いてみたい」と語る。今私たちに本当に必要なのは、おそらくそういう話だろう。
無断転載及び再配布禁止