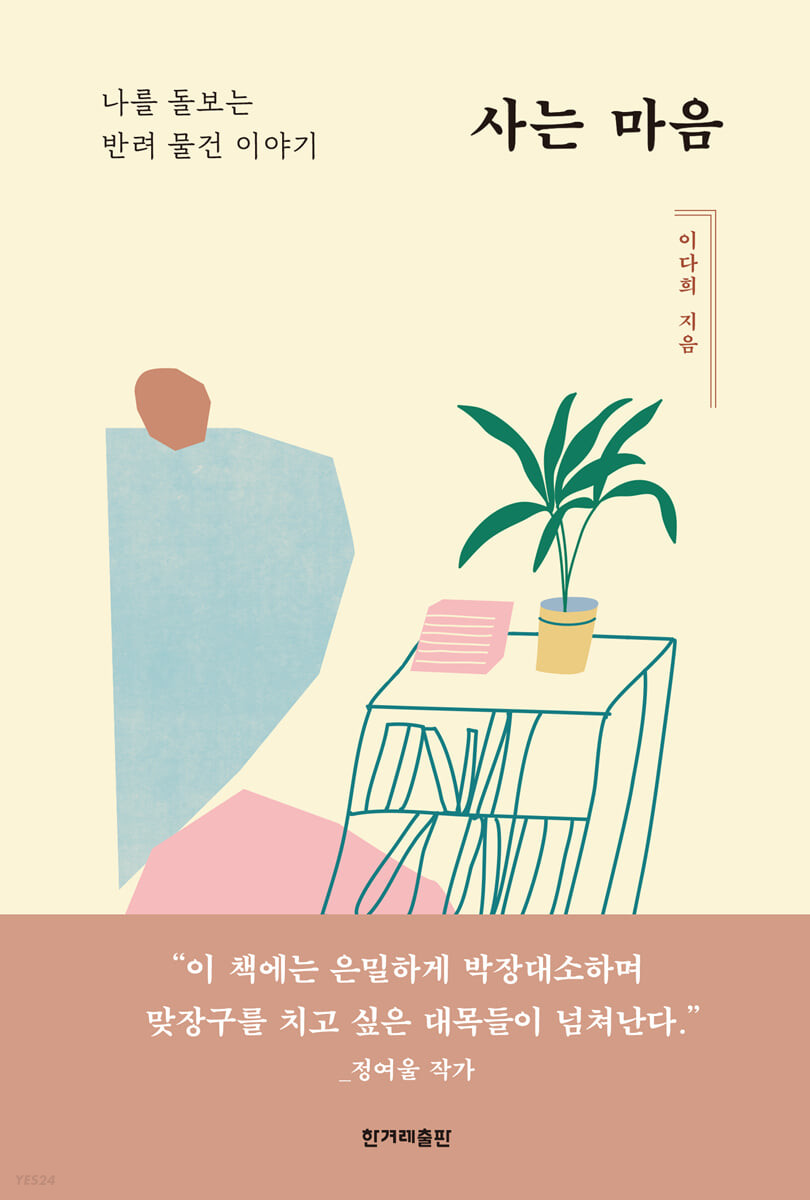NoW
『アメリカン・ボーン・チャイニーズ』、誰もが自分の世界を救うことができる
今週のOTT、映画、本、音楽
2023.06.09
Credit
文. ユン・ヒソン、イム・スヨン(映画専門誌『シネ21』記者)、 キム・ギョウル(作家)、 キム・ユンハ(ポピュラー音楽評論家)
デザイン. チョン・ユリム
写真. Disney+
『アメリカン・ボーン・チャイニーズ』(Disney+)
ユン・ヒソン:アメリカで生まれた中国人ジン(ベン・ワン)は、ありふれた他と異なる少年だ。両親の母国語をろくに聞き取れないほどのアメリカ人であると同時に、何をせずとも中国人だと弁別される外見を持つティーンエイジャーである彼にとって、世界はいたって過酷だ。このような少年が突然ヒーローになることから始まる物語は、ありふれた冒険談のように聞こえるかもしれない。だが、『アメリカン・ボーン・チャイニーズ』はそのヒーローのポジションに孫悟空を置き、これが単なる内気な少年のファンタジーではなく、明らかにアジア人のために作られた重要なチャプターであるとはっきり示す。ヒーローが孫悟空である意味、それは単に、孫悟空が数え切れないほど変奏され、広く知られたキャラクターだからではない。ジンの両親と似た境遇のアジア人らは、常に「強要」の中で成長し、いつ何時も他人の視線を意識させられるくびきに囚われてきた。彼らにとって生まれながらの無法者である孫悟空の存在は、羨望よりもまず、解放のカタルシスを与える存在だ。一般的なヒーローが夢と希望を守ってくれる存在ならば、孫悟空はむしろ、抽象的な価値を崩壊させていっそう偉大な存在として君臨する。さらに、この作品のもう一人の主人公は孫悟空の息子だ。「決して諦めることなく飛び回る」孫悟空の世界を再び裏切ってこそ成り立つ、他と異なるありふれたヒーローだ。
それぞれのやり方で孤立した2人が出会い、新たな世界に進もうという段階で、彼らの背中を押す存在は往年のシットコム俳優ジェイミー(キー・ホイ・クァン)だ。「アジア人」というミームで登場した彼は、少年たちとは無関係だが、一方で彼らの人生を最もよく理解する人物でもある。背景として存在する彼が、これ以上世界にとって心地よい方法で「自分たち」を受け入れさせないと宣言する場面は、この作品が用意した「かめはめ波」の瞬間だ。たとえ誹りを受けようとも「自分」として存在するのだという彼の選択は、「旅立つ誰か」がヒーローなのだという彼自身の話と重なる。このシリーズは、観世音菩薩に始まって東洋の神秘的な素材を積み重ねた壇上から発される、力いっぱいの歓声だ。誰もが自分の世界を救うヒーローになれる、アジア人であってもそれができるのだ、と。当たり前だと言う人もいるかもしれない。しかし、 その「当たり前」の物語を見るまでに、これまで実に長い時間がかかったのだ。
『JAURIM, The Wonderland』
イム・スヨン(映画専門誌『シネ21』記者):デビュー25周年を迎えたバンド、JAURIM(紫雨林)がファンと共にアルバムを制作する。「大合唱オーディション」と名付けられたイベントの応募者は660人にも及び、最終的に117人のJAMONG(JAURIMのファンダム名)が、JAURIMの代表曲を再録したニューアルバムのコーラスとして参加する。また、25年記念コンサートの準備を行うJAURIMのステージ裏の姿にスポットを当て、25年間の彼らの軌跡を振り返る。『JAURIM, The Wonderland』は、25周年記念アルバムの制作記を中心に、バンドとしてのJAURIMとキム・ユナ、イ・ソンギュ、キム・ジンマンそれぞれの率直な声を収録した音楽ドキュメンタリーだ。「Magic Carpet Ride」、「Hey, Hey, Hey」、「17171771」、「I’m My Fan」、「Twenty-five, Twenty-one」をはじめとした名曲が響き渡る中、彼らの音楽世界を伝え、ファンとアーティストの間に生まれる感情がきらめく特別な瞬間を生み出すことに成功している。一般公開を控え、映画に挿入される公演副音声を劇場環境に合わせるため、再度ミキシングを行ったという。
『買う心』 - イ・ダヒ
キム・ギョウル(作家):誰も皆、何かしらを秤にかけながら暮らしている。これを買おうか、やめようか? 天秤は「買う」と「我慢する」の間を危うげに行き来し、買うべき理由と買わない理由が一日おきに追加される。そうやって悩んだ末に結局買うことになるもの、だから簡単に捨てられないほど大切になるもの、長く自分の側に寄り添ってくれるものがある。著者イ・ダヒは、繰り返されるこれらの過程と結果をじっくり書き留めた。リストには身近なものが並んでいる。本棚、ティーカップ、トレンチコート、机、乾燥機、段ボール。本と椅子、靴とズボン、そして、万年筆とノート。本書は、作家で著者の父親でもある故イ・ユンギが残した本棚から始まり、生きているわけでもないのに乗ると言葉に気をつけるようになる自動車で終わる。著者は、慎ましい女性性神話に囚われていた20代を象徴するウェディングドレスを折りたたんで廃棄し、抗がん治療のために買ったかつらの新しい主人を探すために箱から取り出す。自らの万年筆を前に、他人からの妬みの可能性を噛みしめるその態度には、著者自身の世界に対する態度まで感じられる。万年筆との相性が抜群だという「スマイソン(Smythson)」のノートから、富の多寡によって成功を量る世に思いを馳せる著者の文章を読んでいるうち、「スマイソン」を検索してみようと思わされるのは、単にわたしが万年筆を使っているからだろうか。消費で自らを表現する時代に「わたしが買うものが、わたし自身である」という真理を実感させられる本でもある。
「MOJO」 - META.
キム・ユンハ(ポピュラー音楽評論家):「根本がない」というフレーズは、韓国人がよく使う自嘲混じりの表現だ。生まれたときから「パッリパッリ(早く、早く)」を内面化した人々が作り出したものは、どこか雑然としているものの、その分クリエイティブだった。音楽も同じだ。韓国の音楽が韓国人だけに愛されるものでなくなってから早数年。案の定、そのごった煮に魅了された人々が遡る韓国ポップミュージックの歴史にも、あちこちに穴が開いている。いちいち説明するのも難しい多くの理由によって途切れた音楽の脈を再び繋ごうとする試みは、21世紀の韓国音楽に欠かせない独特な思潮の一つだった。
「MOJO」はラッパーであるMETA.が自身の名で世に放った初めての曲だ。どんな音楽家でも必然的に持たざるを得ない「1曲目」がそんなに重要だろうか、と首を傾げるあなたには、その曲を歌った人物の名前をもう一度確認することを勧める。韓国ヒップホップを知る者なら知らないはずはない、国産ヒップホップ第1世代を代表するグループGarionのメンバーMC META.のソロデビュー作が、とりも直さずこの「MOJO」なのだ。さらに驚くべきは、曲誕生の舞台裏に隠された名前だ。1990年代末、ソウルの弘大(ホンデ)にあった伝説のクラブ「マスタープラン(Masterplan)」で共に音楽を始めた韓国テクノ第1世代トランジスタヘッド(Transistor head)がプロデュースを、やはり同時代に活躍したロックバンド・ノイズガーデン(Noizegarden)のメンバーであり、現在はバンド・ローダウン30(Lowdown 30)を率いるギタリスト、ユン・ビョンジュが制作を担当している。かつての戦友たちが面白半分で集まっただけじゃないか、と思うだろうか。歳月の重みが直に感じられるビートやラップ、歌詞に集中して聴けば、そんなことは気軽に口にできなくなるだろう。このトラックが、リリースを控えたMETA.のファースト・ソロアルバムが打ち上げた挨拶代わりの一曲だということを知れば、なおさらだ。韓国ポップミュージックの脈に空いた穴を埋めるため、彼らが戻ってきた。
Copyright © Weverse Magazine. All rights reserved.
無断転載及び再配布禁止
無断転載及び再配布禁止