
近頃ENHYPENの「Polaroid Love」をよく聴いている。刺激的な曲ではないので、日常のどの場面で流しても満遍なく合う。落ち着いていて穏やかな表情の隣の席の学生のようだ。歌が表現する場面もまた同じだ。情熱的だったりスカッとする一場面ではなく、ときめきを否定したいがそうできない不器用な思いを短く描いている。「パピーラブ※」から感じる感情をインスタントフォトに例えた、2022年タイプのティーンエイジ・ラブソングだ。あるファンのTikTokダンスがバズったおかげで、今はチャレンジも真っ盛りだ。
メジャーの曲だが、どこかマイナーのようにメランコリックなニュアンスがある。曲を構成するコード進行を見ると、 Cm7 - F7 - Bbmaj7 - Gm7 (ii - V - I - vi)が繰り返される。ジャズで最もよく使うii - V – I進行に、最後の1拍にはマイナーのviを加えた構造だ。鍵盤の左手と右手がズンチャッズンチャッというリズムをやり取りする感じが、茶目っ気がありながらも、恋を「格好悪い感情」と思いたがる、幼い話者の心の中の棘が表現されている。
イントロ(歌のサビでもある)部分は、たった4小節で曲のテーマを甘くほろ苦く描き出す。JAKE特有の発音の仕方も耳に集中させるのに一役買っている。ㅊ(ch)やㅈ(j)のような後部歯茎音やㄱ(g)のような軟口蓋音の子音は柔らかく、母音はより大きく開いて表現し、「恋、格好悪いその感情」という挑発的な歌詞を、耳障りでなくするだけでなく、むしろキャッチーなパートに仕上げている。
1番は惹かれる気持ちを否定する、いわゆる「ツンデレ」のような話者を描く。最初のバースをそっけない感じでクールに歌ったJAYと、もう少しスイートに表現したSUNGHOONのボーカル・シークエンスが対比を成す。話者は、恋は格好悪くてわかりきったもの、皆が知っているものと考える。ここで皆が知っているというのは、ときめき自体についての知識というよりは、その後に伴う失敗した時に耐えなければならない重荷について考えるという意味だろう。それは青少年世代だけでなく、どこまでも続く競争の時代を生きる大部分の人が置かれた状況だろうが、幼い少年少女たちにまでそのような考えをさせる社会が、どれほど潤いのないものかを映し出す鏡像でもある。いつかは終わる感情の交流や恋愛の後のほろ苦さ、あるいはすべきことを全部できず取り残された結果について、自らが一人寂しく責任を取らなければならないという事実が、ときめき自体を躊躇させたり、この曲の話者のようにあえて過小評価して回避させる。
しかし話者は、プレコーラスで相手が自分の名前を呼ぶ時、心臓がドキドキするのを経験する。その馴染みのない喜びは、単調に繰り返されていたii - V - I – viのマイナーコード(vi、Gm)がしばしメジャー(VI、G)に変わるやり方で表現されている。HEESEUNGが柔らかいポップ・ボーカルで歌う「When you call my name」の「name」の部分が、まさにピカルディの三度とも呼ばれるその長三和音だ。そうして胸いっぱいになる感じは、SUNOOが胸声からファルセットを交差させ、「胸が痛く」という歌詞で受け止める。歌はお茶目で甘い感じかと思うと、そのようなほろ苦さを加味して進行する。バースとプレコーラスの間ずっと単調に続いていたリズムは、「僕の心臓がドクンドクン」というパートですべての楽器が一瞬止まった後、ポップドラムが入ってくる構成に変わるのだが、それが過度ではない。もう少し楽しくなる程度だ。よくある単純な構造が、昔の歌のように心地よさを与える。リパッケージアルバムに追加で入っている小品のような曲だ。複雑で刺激的なK-POPシーンでは、むしろそういう理由でより際立っているようにも思う。
青少年の聴き手は、この歌をどのように聴いているのか気になって検索をしてみた。歌から感じたという感情は、「かわいい」、「スイートだ」、「共感できる」、「淡い(dreamy)」などだった。そのうち「淡い」という表現に目が行った。どういう意味だろうかともっと把握してみると、歌をレトロなコンセプトで聴かせる装置、つまりLo-Fi効果や古風な電子ピアノから、夢のような感じを受けているようだった。今はすべてが高音質で高画質だからだ。年齢が上の人たちは低音質、低画質から郷愁を感じるが、その時代を直接経験していない人たちは、同じことからこれという対象のある懐かしさを感じないだろう。代わりに、すべてのことが鮮明で情報がとても多い現実とは少し離れた、夢のような世界として感じるようだ。
ポラロイドカメラが初めて発売されたのは1948年だった(ポラロイドはインスタントカメラを初めて発売した会社名だが、インスタント写真の代名詞として使われているため、この記事では引き続きポラロイドと表記する)。当然の話だが、最初に出た当時としては最新の技術だった。写真を撮った後、フィルムを暗室に持っていき現像しなければならない普通のフィルムカメラとは異なり、写真を撮った後すぐに見ることのできるポラロイドカメラは、概念を変える革新だった。20世紀後半に盛んに人気を集めたポラロイドカメラは、21世紀に入り、デジタルカメラの普及で次第に立場を失った。デジタルカメラは、撮影してすぐ写真を予め見ることができたのはもちろん、欲しいイメージだけを選んでプリントすることができた。消耗品であるフィルムをいつも買って使う必要もなかった。そうして欲しいものだけ選択できるようにしたデジタル技術は、印画紙という物質の存在を煩わしい過去の遺物にした。ポラロイド社は2000年代後半、インスタントカメラ事業をたたんでいる。しかし同じ時期、同じインスタント写真技術を保有する富士フイルムは、小石のように丸い「instaxカメラ(チェキ)」を発売し、製品の宣伝の方向を以前とは異なるファンシー製品路線に据えた。「デジタル」の時代に反する「アナログ」を追求する人々に、感性に訴えるアイテムとしてアピールすることにしたのだ。戦略は大成功だった。衰退の一途をたどっていたインスタントカメラは、しっかりとしたマニア層を持ったファッショナブルな商品として生まれ変わった。そしてファッション、音楽など分野を選ばず、20世紀リバイバルがポップカルチャー全般を支配している2022年現在、ポラロイドは格好良くはないが特別なレトロ感覚の代表的な媒体だ。
ENHYPENの「Polaroid Love」もまたその感覚を共有する。ポラロイドのインスタント性は、デジタルカメラ時代を過ぎて、一人につきスマートフォン一台に近い今の時代には、もはや強みではない。代わりに、プリントする前にフィルターを使ったり補正することのできない制限が、かえって被写体をありのままに写し出しているという保証になる。液晶の上を無限によぎる情報としての写真、無限に複製できるデジタル媒体としての写真とは異なるポラロイド写真は、最初に選んだたった1枚の物としてのみ存在する(もちろんその写真をスキャンしたり、撮ってデジタルとして複製することはできるが、それはオリジナルではないので)。「君への僕の気持ちをここに補正なしに刻むんだ/だんだんはっきりしていく この気持ちは世界でたった1枚だけなんだ」とNI-KIとJUNGWONが幼さの残る声で仲良く分けて歌う2番に、ポラロイドの媒体的属性が集約されている。フィルムからデジタルに移っていった時期には不便さとして認識されていた性質が、今は手間を必要とする特別さになった。格好悪いが気に入っている、矛盾した存在としてだ。
「Polaroid Love」の中の恋は、ひたすら甘く幻想的なものばかりではない。前提が現実に対する恐れであるため、甘さの後に必ずほろ苦さが伴う。ENHYPENの他のラブソングにも「Polaroid Love」と似た視点が描かれている。同じアルバムの「Just A Little Bit」は、世の中のことをすべて知っていると思っていた「僕」が、恋に落ちて変化する瞬間を歌う。恋の歌だが、相手に投げかける熱い告白というよりは、恋に変わる「僕」の気づきを日記のように描いた成長物語だ。2ndミニアルバムの中の「Not For Sale」もまた、俗物的な世の中をあざ笑っていた「僕」が、「君」に出会って初めてときめきを感じ、世の中の法則とは異なる関係の大切さを学んでいくストーリーを描いている。「FEVER」や「Let Me In(20 CUBE)」のように、もっと勢いよく突き進む姿勢の歌もあるが、これらの曲はどちらもファンタジックな世界を背景にしている。ENHYPENの現実の恋の歌は、ほとんどが世の中に対して冷笑的で慎重だという共通点がある。
ENHYPENのファンダムの多数を占める女性たちの立場でも、そのような「ENHYPEN印の現実の恋の歌」にすぐに共感する姿を見ることができる。そのような冷笑と慎重さは、単なる日常の中の恋愛関係を離れ、アイドルが好きなファンのパラソーシャル関係(メディア利用者が、メディアと対人的な没入関係を持つこと)にも影響を与えたように思える。甘くはない現実のために、深い感情を持つのが難しいことがまず一つ目だ。その上、今の世代の青少年の女性ファンたちは、幼い頃第1世代、第2世代の男性アイドルのうち一部が社会的に物議をかもした姿、またあるファンたちは彼らを庇護し、道徳的共犯になったりもした姿をすべて見て育った人たちだ。SNSで青少年ファンたちを観察してみると、以前の世代と比べた時、アイドルが好きではあるが、人間は人間をいつでも失望させ得るという前提の上に、情熱を冷静に維持しようとする姿が際立つ。もちろん思い通りにいかないのが恋、あるいはファン心理なので、「Polaroid Love」のように尖っていても、不可抗力に右往左往する姿もよく見られる。ファンになっても否定をしたり、距離感を維持するために「ファン活」の対象に酷いことを言うなどだ。パラソーシャル関係においてさえ、気を許して愛することが難しい環境なのだということに、気の毒に思ったりもする。昨年釜山国際映画祭で公開されたドキュメンタリー映画『Fanatic』は、そのような批判的に「ファン活」することについての議論を公的な領域に持ち込む役割を果たした。今年中に公開もされるというから、そのような話し合いが社会にもっと拡張されるかもしれない。
いつの時代よりもラブソングを作りやすくない時代だ。それでも人々は恋をする。青少年たちもまた世界のあちこちで人に惹かれる経験をし、そんな感情をさまざまな方法で噛みしめながら成長する。自分の気持ちを代弁してくれる歌を口ずさむのもそのうちの一つだ。「It’s like a Polaroid love/恋、格好悪いその感情」。呪文のように繰り返すのに良い歌詞だ。もしかしたらポラロイドのような低画質の昔の媒体には、この矛盾を鎮める魔法があるのではないかと期待しながら。
※パピーラブ:青少年期の交際の発達過程の一つで、異性またはロマンチックな対象との接触が慣れていないため、ぎこちなく不安定なことが特徴
無断転載及び再配布禁止
- ENHYPENがおすすめするヒーリング・プレイリスト2021.10.20

- ENGENE、ENHYPENのためのグローバル世界2022.01.03

- ENHYPEN、再び躍進する2022.01.11
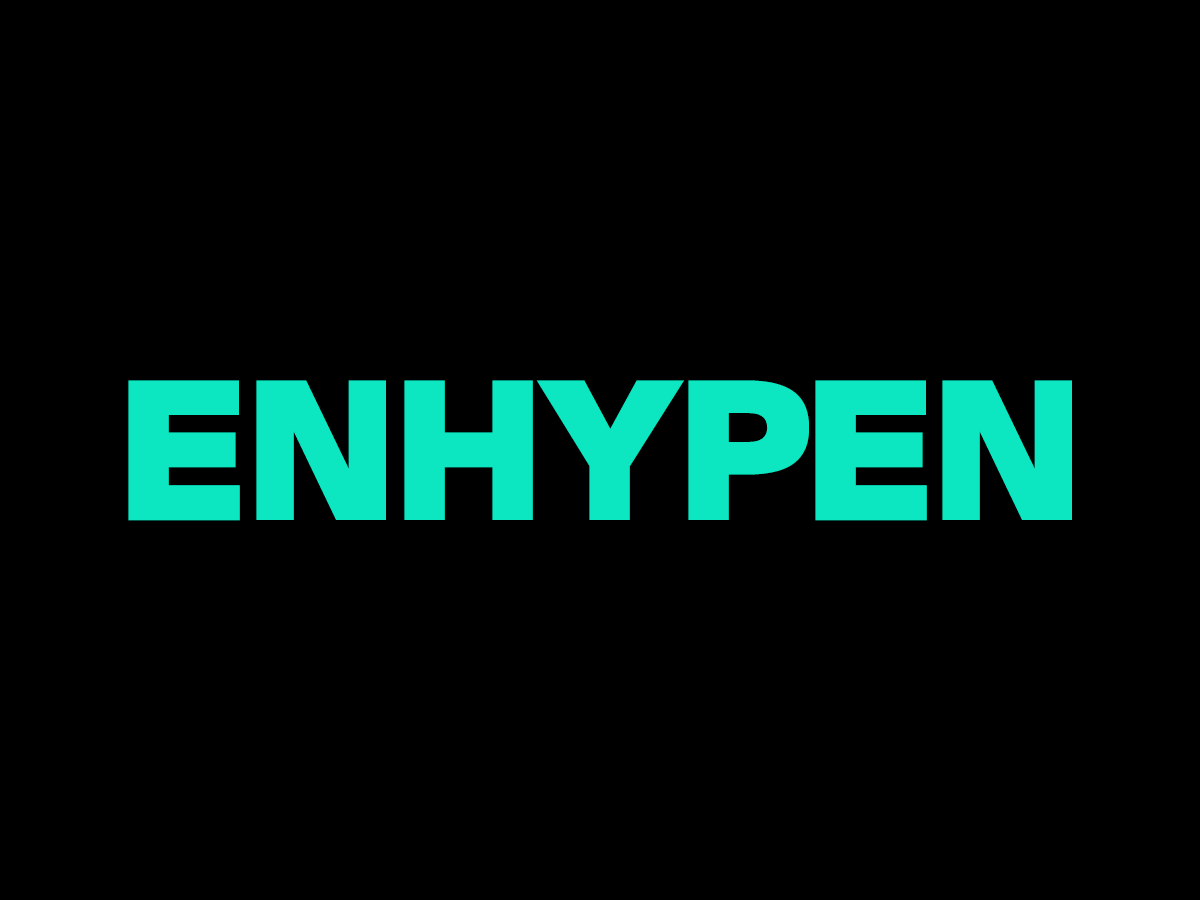
- ENHYPEN Other Cuts2022.01.23
