-
 ©️ SHOWNOTE
©️ SHOWNOTE
1
今まさにキャリアをスタートした新人俳優にとって、ミュージカル『ヘドウィグ』はとても難しく、チャレンジングな作品である可能性が大きいです。「ヘドウィグは複雑な事情を抱えたトランスジェンダーだ」などということは、実は大きな問題ではありません。ヘドウィグの人生のドラマチックな部分で深みのある演技をしながらも、あいだあいだに日常の会話の言語をはさみ込んで、ヘドウィグが私たちのすぐ近くにいて、周りで会えるかもしれない人物だという点を同時に表現するために、相反する二つの言語を行き来しつつ、ごく自然に演技しなければならないのが最も難しい点です。「異質感と親近感を同時に感じさせよ」という、一見矛盾した目標を持ち、それをステージで具現化すること、つまりヘドウィグをとても独特な個人として認めながらも、私たちと同じ人として同質感を感じさせることが難しいのです。この舞台で一字一句まちがえず伝えなければならない台詞は、そう多くはありません。ただヘドウィグを演じる俳優は、必ず台詞をすべて体得し、自分の言語として自然に表現して、観客が、私たちと日常的な会話をするヘドウィグと、自身の話をドラマチックに表現するヘドウィグの両方から、一つに統合されたヘドウィグに出会えるようにしなければなりません。新人の意気込みでそのすべてのことを克服していけるかもしれませんが、それには台詞の量がとても多く、劇中で俳優が試みるアレンジは、絶対にストーリーの本質を損ねてはなりません。基本的な骨格の中で舞台が進行する間、俳優自らが状況によって台詞を変えたり、または必要に応じて状況を作り出さなければならないミュージカルなので、俳優の力量が大変要求される役で、だからこそ多くの俳優たちが演じたがる役でもあります。ストーリーの間の空白は、俳優本人のキャラクターで埋めなければなりませんが、その過程での伝達が完璧でなければならないため、技術的な完成度もまた度々試されます。
もちろん『ヘドウィグ』がそういう舞台だという事実を観客たちのほとんどがすぐわかるので、普通そこまで厳しくは見ません。韓国で『ヘドウィグ』という型破りな舞台が大ヒットした理由の一つは、俳優たちが本人の個性をさらけ出し、観客たちとのコミュニケーションを惜しまずにしてきて、それを歓迎する人たちが多かったからです。『ヘドウィグ』はそうして主人公ヘドウィグと彼のアングリーインチ・バンド、客席に座っている観客たちがお互いに影響を与え合って作っていく舞台だと言えますが、そうだとしても主人公にやすやすと挑戦できる作品だとは言い難いです。
そこに加えて、現役のアイドルにとってヘドウィグを演じるということは、そのような演技の力量自体の難しさ以外にも、最初に置いておいた副次的な問題が再び重要になってきます。素材が持つタブー性において、アイドルにとって多少負担になり得る点があります。ヘドウィグの口を通して流れ出る(若干の検閲削除が必要かもしれない)赤裸々な場面描写や、露骨な異質感、主人公が口を開けば出てくる罵詈雑言や不親切な態度など、そのすべてが、生き抜いてきた少数者が自ら自分の存在を消さずにさらけ出そうとする抵抗行為であることを勘案しても、文字通り「崇拝の対象」であるアイドルにとっては、本人が維持しなければならないイメージの対極を演じることにもなり、困難が生じます。アイドルとしてアイデンティティを維持していこうとすると、役になり切れずに俳優として失敗するリスクがあり、俳優としてキャラクターを完全に自分のものにしようとすると、アイドルとしてのイメージに傷がつくリスクを受け入れなければならないのです。
2
今回の『ヘドウィグ』でヘドウィグ役を演じる「NU’EST」のRENは、どんな姿を見せてくれるでしょうか。RENは世の中に対する探索をやめることなく、愛されることに対する期待を絶対に手放さない、幼い子どもの魂を終始表現し続けるヘドウィグです。「道端」というタイトルの詩を完全に自分の言葉で、真っ直ぐに吐き出す姿を見て、このヘドウィグは果たしてどんな人物なのだろうかと気になっているうちに、観客たちはいつの間にか、オーブンの中に頭を突っ込み楽しそうに歌を歌いながら、その小さな世界の完全さを楽しんでいる幼いハンセルに出会うことになります。ハンセル自身はその事実に気づいていませんが、彼の魂の片割れが音楽であり、音楽と一つになったその場所で彼はすでに完全だったということを、観客は舞台の序盤から確信できるのです。
だからこのヘドウィグは、まるで誰にとっても他者だったことがない人物のようです。先輩のヘドウィグたちが経験してこなければならなかった世の中の偏見や異質感に対する冷酷な嫌悪などは、ただひょいと飛び越え、自ら存在することを渇望し、そのまま存在してしまうのです。「あなたは私のことが嫌なんでしょ。だからって私を消すことはできない。私がここに存在しているということを、はっきりと感じさせてあげる」というような、闘志や生き抜いていく少数者としての自己憐憫はほとんど感じることができません。「皆さんが好きだろうが嫌いだろうがヘドウィグ」という紹介の言葉で呼ばれて出てきては、それでも結局自分を愛することになるだろうという、そうやって自らが愛されるだろうという確信に満ちています。嫌悪する者がいないからではなく、彼らに対して特別な寛大さを持っているからでもありません。このヘドウィグは、決して犠牲者になる気はなく、自分が受けている愛に集中しているからでしょう。
ヘドウィグの歌を聴いてすっかり心を奪われてしまったトミーは、アダムとイブ、禁断の果実の話をし、ヘドウィグに禁断の果実を求めます。「僕にあなたが知っている善と悪をすべて教えてください。僕は全部知りたい」。『ヘドウィグ』でのRENは、まるで禁断の果実を求めるトミーのように見えます。ヘドウィグのライブが行われている途中途中に、遠くの別のライブ会場から聞こえてくるトミーの声は、REN本来の姿や声であるかように茶目っ気がありながら、馴染みがあり自然です。ヘドウィグにとってトミーは、あまりに「悪いやつ」ですが、ヘドウィグが心から渇望していた、だからこそ永遠に一緒にいたかった存在でもあります。すでにその場でRENは、ヘドウィグを受け入れ、学び、愛しています。ヘドウィグには「Wicked Little Town(Reprise)」を歌い聴かせるトミーが必要でした。RENは初めからヘドウィグを完全だと信じていたにちがいありません。彼の『ヘドウィグ』は、RENがトミーの声を通して観客たちに伝える、結局はヘドウィグの耳に届くトミーの声です。
大衆芸術家たちは基本的に、自身を見る「他人」や「他者」を必要とする存在であり、本人が積極的に「他者」になることを受け入れなければならないこともある職業です。演技者が大衆に見せる「役」という仮面をかぶった姿は、しばしば意図された誤解とともに、俳優本人がその役と同じ人だという錯覚を引き起こすこともあります。本当のお前は誰だ、どの姿に近いのか、などの愚問を聞くことになったりもします。ヘドウィグは自分の人生全般を横切る他者性を認識し受け入れますが、その他者性により、ばらばらになった自らを一つにまとめることができず苦しむ人物で、ディスフォリアとは何なのかを隠喩的に表現しています。自身の本質がずっと他の人たちから認められず、自分が属す場所がどこなのかわからず、どちらかはっきりしない存在として浮遊するヘドウィグの苦しみを、似た過程の中に置かれている大衆芸術家は、どんな方法で感じ、表現するのでしょうか。RENはそこに無理して悲劇を盛り込もうとせず、自分ができるアプローチと持ち味により統合された自我を表現します。
3
メイキャップが好きだというRENにとって、『ヘドウィグ』は果たしてどんな作品になるのか気になります。ヘドウィグが自身の口で語るように、彼のウィッグやメイキャップは、能動的にも受動的にもさまざまな脈絡で解釈できる象徴です。今日の舞台の話は今日だけの話です。これから残りの舞台の期間、『ヘドウィグ』を通してRENは自らを拡張することになるでしょうし、このヘドウィグを演じるRENを通してもまた、これまで発見されていなかったヘドウィグのストーリーが現れることでしょう。若いヘドウィグはそうしてもっと前に進んでいくでしょう。RENは自分を観に来た観客たちに「ヘドウィグ」をどれぐらい見せることができるでしょうか。また観客たちは、「ヘドウィグ」にどれほど出会って帰っていくのでしょうか。観客たちは自分が「ヘドウィグ」になったということに気づけるでしょうか。ヘドウィグの「異質感」は、どのように日常性を獲得できるのでしょうか。俳優としての達成感は、観客が、彼が仮想の人物を演じているということがわかっていても、実際には俳優がかぶっている仮面に誰も気づけないことで、彼がどこかに実在しているだろうと感じさせる感覚から来ます。おそらく彼にとってミュージカルの世界は、K-POPの世界とはまた別の「索漠とした冷たい都会」かもしれません。『ヘドウィグ』という道を歩きながら、RENがどんな声になっていくのか、自分の声を完全に持てるようになるのか、とても気になります。
少し慣れない感覚で彼のヘドウィグをしばらく見て、トミーになった彼の姿をまたしばらく見て、大団円の幕が下りた後、再びカーテンコールでそれまで見ることができなかった姿を見せる「レンドウィグ」の3段階の変身は、本当に印象的でした。カーテンコールのステージに再び現れ、ヘドウィグでもトミーでもない、だからといってアイドル本来の姿でもない、生まれたての新人俳優の清らかな顔で歌うRENの「Wig In A Box」は、ずいぶん長いこと記憶に残るでしょう。


無断転載及び再配布禁止
- NU’ESTが贈るロマン2021.04.20
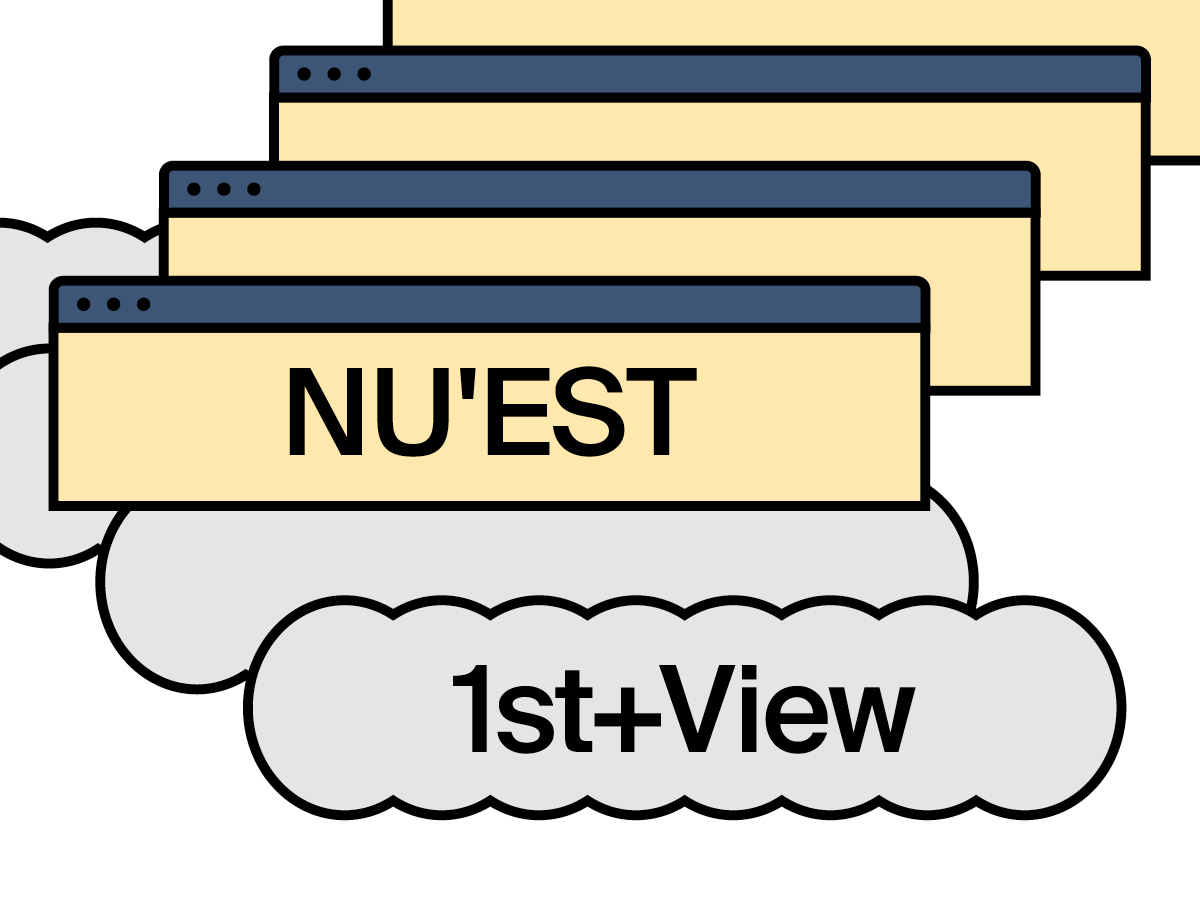
- REN、「L.O.Λ.Eは僕が生きていく理由です」2021.04.29
