2024年、韓国のポップミュージックシーンにおけるJ-POPの活躍は目覚ましかった。imaseの「NIGHT DANCER」、YOASOBIの「アイドル」という2曲のメガヒットによってJ-POPというアトランティスが浮上した2023年に続き、昨年は日本の音楽が普遍的な好みの一つとして完全に定着した年になった。その背景には、1年を通じて活発に開催された来韓公演があった。その中で特に象徴的なイベントを3つほど挙げるならば、韓国初となるJ-POPメインのフェスティバル『WONDERLIVET 2024』、2日間で2万5,000人あまりの観客を動員したYOASOBIの来韓に加えて、藤井風の公演は外せない。彼は日本のアーティストとして初の高尺ドーム公演を実現し、J-POPが韓国の音楽シーンにおいて一定の軌道に乗ったことを名実ともに示した。
興味深かったのは、むしろJ-POPマニアたちが彼のドーム公演に対して半信半疑といったリアクションを見せたことだ。そうした反応は、おおむね自分の周りに彼のファンがなかなかいないという話に帰結することが多かった。これはおそらく、彼が日本音楽のカテゴリーにいながらにしてJ-POPらしからぬ活動と作品を展開しているからだろう。彼はなぜ韓国のJ-POPファンたちにとって比較的馴染みが薄いのだろうか。また、それにもかかわらず指折りのグローバルスターにのみ門戸が開かれる高尺ドームのステージに立つことができた背景に、どんなファンベースが存在していたのだろうか。このように突然生じた疑問に答えるためには、彼のキャリアから読み取れる藤井風ならではの特異点をいくつか見ていく必要がある。
今となっては広く知られた事実だが、彼はYouTubeでの活動を通じてミュージシャンとして飛躍したケースだ。最初にピアノの演奏動画をアップロードした2010年以降、ジャンルや国にとらわれることなく様々な曲を弾き語りした藤井風は、自らのポテンシャルを誠実に証明しつづけた。そのアーカイブによって徐々に存在感を示すようになり、デビュー前から様々なイベントに出演して経験を積み、2018年のメジャー契約後、オリジナル曲の正式リリースなしにワンマンツアー〈Fujii Kaze "JAZZ&PIANO" The First〉を完売させるなど、新人としては異例かつ破格の形でアーティスト活動をスタートするに至った。

この時点ではまだ、カバーではない「オリジナル曲」でメインストリームに乗れるかについての疑問が存在していた。その疑念を一気に払拭したのがデビュー曲の「何なんw」だった。自身の強みであるピアノ演奏をベースに、R&Bやヒップホップ、歌謡曲などの要素を融合させ、岡山弁と英語を行き来する彼独自の言語で曲を紡ぎ出した才能は、大衆および評論家から手放しの賞賛を引き出すのに十分だった。日本産ブラックミュージックの新たな道を開拓した宇多田ヒカルの登場当時に似た反応も多くあった。宇多田ヒカルの音楽が収めた成果が「日本というローカリティの限界の克服」というポイントで注目されていたことを考慮すれば、彼の成果もまた、列島を超えて世界にアピールできる完成度を認められたという結論に至る。
海外でただならぬ動きが感知されはじめたのは2022年7月のことだ。2022年10月に2ndアルバムのリリースを記念する〈Fujii Kaze LOVE ALL SERVE ALL STADIUM LIVE〉が2日間で7万人を動員し、藤井風が時代を代表するアーティストになった瞬間、1stアルバム『HELP EVER HURT NEVER』の収録曲「死ぬのがいいわ」がTikTokを中心に広がりはじめた。その熱は一気に拡散し、Spotifyでは世界23の国と地域で1位を獲得、2022年に海外で最も再生された日本の音楽にランクインすると同時に、再生回数2億回を突破するなど、予想だにしなかったグローバルヒットとなった。

藤井風の音楽にポップミュージックとしてのポテンシャルが十分なことはすでに認められていたが、アルバム曲であった「死ぬのがいいわ」のヒットは予想外のことだった。タイのTikTokユーザーから始まった熱狂はブータンやベトナム、マレーシアなどアジア各国へ広がっていき、韓国とアメリカもその例外ではなくなった。一見するとこれは、ショートフォームで見つけた曲をストリーミングサイトで聴くニューメディア時代の一般的なコンテンツ消費の傾向のように映るかもしれない。しかし彼のケースは、その他のバイラルヒットと比べて相対的にアーティスト自身のファンダムに繋がる傾向が強く現れている。順を追って見ていけば、結局のところ楽曲の属性と人間としての魅力、SNS中心の活動戦略が噛み合った大きなシナジーが人気の核にあることが分かるだろう。
具体的な考察をする前に、個人的にも「死ぬのがいいわ」のヒットは不思議に思えた。もちろん「死ぬのがいいわ」は彼のポップセンスがバランスよく形になった優れた曲であり、メロディーやリズムも初めて聴く人々に受け入れられやすいキャッチーさで武装している。それでも、よりによってなぜこの曲だったのだろうか。その理由は、リスナーの参与を導く歌詞にある。「三度の飯よりあんたがいいのよ / あんたとこのままおサラバするよか / 死ぬのがいいわ / 死ぬのがいいわ」という普遍的な情緒をまっすぐに表現する歌詞が、何かに向かう自らの愛を表現するのに最も適したツールとして捉えられたのだ。
実際にこの曲が本格的なバイラルになりはじめたのは、自分の好きな何かとこの曲を組み合わせた動画が流行するようになってからだという点に注目する必要がある。さらに、「死んでも離さない」や「銃で撃たれたように」といったストレートな歌詞に馴染んできた韓国人にとってみれば、これまでになく最適化された歌詞でもあった。比較的メタファー中心の歌詞が多い日本の音楽とは異なり、そういった「J-POPへの違和感」を見事に回避しながら、藤井風は新たな「好み」を探し求める韓国のSNSノマドたちを自らの懐に引き寄せているのだ。

これに加え、SNSを基盤とした巧みなコミュニケーションにも注目する必要がある。日本でSNSを活用したプロモーションが徐々に本格化しはじめた頃、自己紹介や楽曲解説の動画を投稿するなど、ファンが楽しめるオンラインコンテンツをいち早く展開してきた。「死ぬのがいいわ」が並々ならぬ人気を示すと、ただちに武道館のライブ映像をYouTubeに投稿し、X(旧Twitter)にもメッセージを残すなど、感謝を示す積極的なリアクションでこれに応えた。そうしたコミュニケーションが全て英語でなされたという事実は決定的だ。彼がJ-POPという枠組みから解き放たれた「海外ポップスター」としてのペルソナを与えられえたのは、このように言葉の壁が消滅したからである。こうして、「もう一つのJ-POP」ではなく「もう一つの好み」を求めていた人々を対象として、J-POPのクリシェを脱した藤井風の作品と活動のあり方がより広い層の大衆を取り込んでいる様子を、我々は今目撃している。
このように、王道のように思えたOTT(ストリーミングサービス)とタイアップ中心のグローバル戦略を覆しつづけ、藤井風は新たなJ-POPの進出戦略を展開している。その潮流の波に乗って彼の音楽世界に浸透しつつある人々は、ある瞬間、彼が伝える究極のメッセージに辿りつく。彼は「Higher Self」、つまり、自我や利己、嫉妬といったネガティブな感情から解放された愛そのものを手に入れることを、音楽を通じて促している。そんな彼にとってファンや観客は、どんな姿であれ皆一つであり、常に感謝し、愛すべき対象である。アジアツアーによって「自分のふるさとみたいなものがさらに広がった」と述べ、NewJeansの「Ditto」をカバーしたり、朝鮮半島の民謡である「トラジ」を自身の「まつり」と組み合わせて披露するなど、その空間でのみ存在する「今」を大事にする姿もまた、そういった「Higher Self」と同一線上にあると言えるだろう。
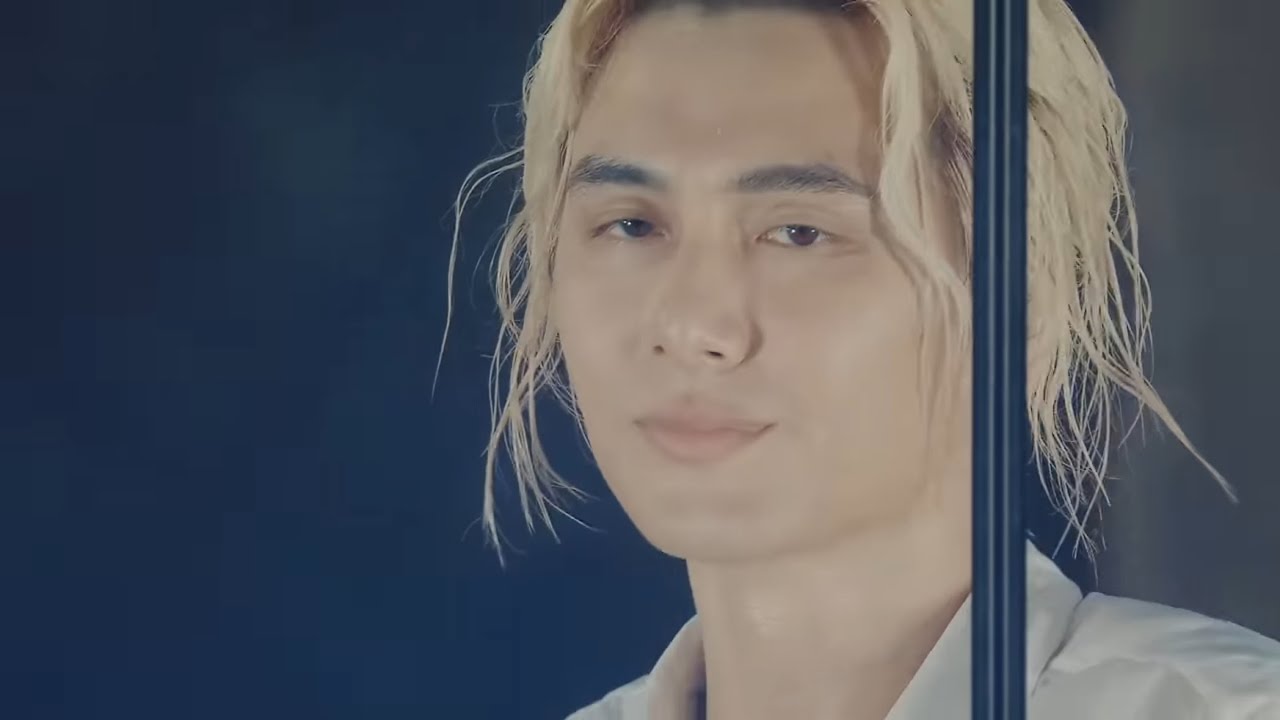
先述したように、藤井風の作品を単純に「J-POP」と分類するには無理がある。大衆が共感できるポピュラーミュージック、全世界の人々をターゲットとした気さくで心のこもったコミュニケーション。そして、過去でも未来でもない「今」を生きている感情を大切にしようと語りかけながら、人生をより広い視点で見つめるように促すアティチュードまで。知れば知るほど藤井風というアーティストは、単なる「J-POPブーム」の潮流だけでは捉えきれない存在であることに気づかされる。青春は儚いからこそ、その輝きから目を逸らしてはいけないという「青春病」の歌詞のように、藤井風はすでに国境を超え、「ポップアイコン」としてこの時代に降り注ぐまばゆい光になっている。まるで今日の一日を力いっぱい眩しく輝ききって、明日消えてしまっても誰も不思議に思わない光かのように。
- なにわ男子の挑戦は現在進行形だ2025.01.13
- 野田洋次郎が伝える慰め2024.11.27
- King Gnu、J-POPの概念を再定義する2024.02.05

- Ado、ニュータイプの出現2023.11.06
