ベーシックなスリーピースバンドのサウンドを土台に、ヒップホップやサイケデリック、エレクトロニカなど、多様なジャンルを旺盛に吸収しながら独自のオリジナリティを築いているブランデー戦記。ボーカルを担当する蓮月の言葉通り、洗練よりも「今いちばんワクワクできるサウンド」を形にしようとする素直な個性は、多くのリスナーを急速に魅了しつつある。〈仁川ペンタポート・ロック・フェスティバル〉出演の2日前に行ったインタビューでは、わずかに緊張を見せつつも、それぞれの考えを落ち着いて語り、バンドの羅針盤がどこを指しているのか教えてくれた。ペンタポートのステージで、韓国の観客との初対面を成功裏に終えたブランデー戦記。いっそう密なコミュニケーションが期待される12月の年末ワンマンに先立ち、活動の幅を広げつつある今の心境に耳を傾けた。
まずは、韓国のファンの皆さんにお一人ずつご挨拶をお願いします。
蓮月:韓国の皆さん、こんにちは。ブランデー戦記のボーカル、蓮月です。
みのり:ベース、みのりです。
ボリ:ドラム、ボリです。
「ブランデー戦記」というバンド名についてお聞きします。初めて聞いた時、ユニークな名前だなと感じたんですが、どんな意味が込められているのか、誰のアイデアだったのかを教えてください。
蓮月:これは完全に半々で決めたんですけど、まず私とみのりが「お酒の名前ってかっこいいよね」っていう話になって、そこで「ブランデー」って響きがいいねって。それで、まず「ブランデー」を入れようってことになりました。
ボリ:後ろの「戦記」は僕が作りました。ブランデーに何かを加えて、造語として名前を付けたいなと思って。それで、カタカナ+漢字のフォーマットがすごくいいと言われて、漢字は何が合うかなと考えた時に、戦う「戦」の字がバンドとしても意味がマッチしそうだなと思って提案しました。
バンドを結成する前、皆さんがそれぞれ音楽を始めたきっかけや、影響を受けたミュージシャンがいれば教えてください。
ボリ:元々父がすごいバンド好きで、日本のバンドではBOØWYや布袋寅泰さん、Dragon Ashとか、そういったバンドミュージックがすごい好きな父だったんです。家でも車で旅行する時とかも、よくバンドの曲が流れてました。そこからバンドという存在を知って、徐々に年月が経って、楽器を始めたいなと思ってドラムを始めました。弟がギターをやってるんですが、弟のほうが早い段階でギターを始めてて、僕もギターとかの弦楽器にしようかなと思ったんですけど、同じ楽器だとセッションがやりづらいなって。違う方向で、リズムのほうに振り切ったほうがいいかなと思ったんです。ドラムが叩ければバンドする上でも需要が高そうだなと思って。それでドラムを始めました。
蓮月:私の場合は、音楽自体は2歳からバイオリンを10年以上習っていて。家でも兄が先にバイオリンをやってたので、「皆やるものなのかな」くらいの感じで始めました。そこから10数年経って、中学生ぐらいの時に、すでに存在するクラシックの譜面を心を込めて演奏するのもいいけど、自分で1から曲を作ったり、歌ったりしてみたいなって思うようになりました。そこで、歌いながら演奏できる楽器は何だろうと考えた末にギターだなと思って、ギターにチェンジして弾いたり曲を作ったりするようになりました。(その頃よく聴いた音楽、ミュージシャンは?) 今でもずっと聴いてるのは、andymoriやザ・ストロークス、ニルヴァーナとかですね。あとは、K-POPのアイドルもずっと好きでした。
みのり:私は、3歳ぐらいからピアノを習っていました。祖父母の家にピアノが置いてあって、母親も習ってたんです。そういったピアノがある環境にいて、幼心に「ピアノって楽しそうだな」と思って始めたのがきっかけです。そして、中学の卒業から高校に入るくらいの時期にバンドを好きになり始めました。たまたま好きになったバンドが、男性メンバーの中で女の子がベースを弾いてるバンドだったので、すごくカッコよく思えてベースを始めました。
どんなきっかけでバンドを結成したのかも教えていただけますか。
みのり:私と蓮月が中学校と高校が同じだったんです。うちの学校は軽音楽部がなかったので、音楽好きな人もあまりいなくて、それで仲良くなりました。2人とも楽器をやってたんで、バンドできるねって。ボリと出会ったのはそれより後だったんですが、蓮月とボリがニルヴァーナのコピーバンドをしたことがきっかけで、ボリのドラムがバンドに欲しいってなって、3人でバンドを組みました。
ボリ:僕だけ、住んでるところがすごく遠かったんです。2人の住んでる所まで通ったりして、バンドの活動をしたい一心で。
蓮月:私は、テレビで大きいステージ、〈SWEET LOVE SHOWER〉とか大きいフェスとか、大きい会場でやってるバンドを見て、自分もあっち側に行くべきだなって思っていて、ずっとそのイメージはありました。
「Musica」が発売されたのが2022年ですよね。YouTubeの再生回数が驚くほどのスピードで増えていったと聞きましたが、理由は何だったと思いますか?
みのり:あの時はシンプルにびっくりでした。曲がいいなと思ってもらえたことは理由のひとつだと思いますし、サムネイルで惹かれたっていう声も結構ありました。
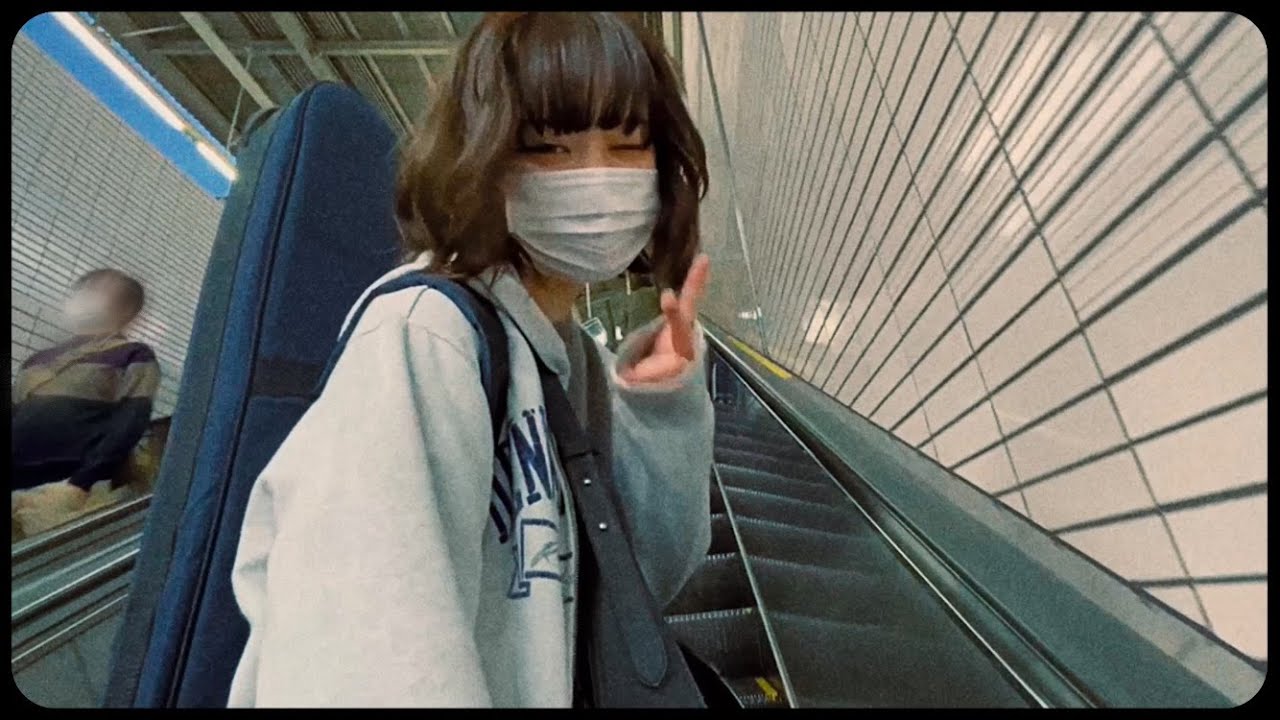
去年、テレビ番組の『バズリズム』や『EIGHT-JAM』で年間ベストとして言及されたこともあり、多くの人に知られるきっかけになりました。また、今年5月にはメジャーデビューを果たしました。
ボリ:当時、初めてのワンマンツアーのタイミングで、その番組が放映されました。僕らは北海道に行っていて、帰りの船に乗ってる時にそれを見たんです。フェリーの端っこのテーブルみたいなところで。ツアーで色々な地域に行くと、色々な人が来てくれるんだなって分かると同時に、テレビメディアでも紹介してもらえて、SNSでも反響を多くもらいました。たくさんの人に名前を知ってもらえる大きなきっかけになったなと思いました。
みのり:デビュー以降、こういうインタビューだとか、ラジオといったプロモーションをメディアにしてもらう機会も増えました。
初のフルアルバムのタイトルは、セルフタイトル『BRANDY SENKI』です。通常、1stアルバムには特別な意味を持たせたりユニークなタイトルをつけたりすることも多いですが、セルフタイトルを選んだ理由が気になります。
蓮月:1stアルバムには、これまでリリースしてきた曲を入れて、そこに新曲をいくつか加えました。ブランデー戦記ってこういうバンドですよ、と知ってもらえるアルバムになったと思うので、タイトルもそのままセルフタイトルがいいねという話になりました。
おっしゃる通り、3年間の価値の集大成だと言える作品でした。制作時期の差はあると思いますが、違和感なく聴くことができました。例えば、「ラストライブ」は初期に制作された曲だと聞きましたが。
ボリ:はい。導入部分が後から変わった曲です。当初はシームレスに上がっていく感じ。それが、1回曲が終わるかと思いきや……みたいな、前半と後半を区別して、もう一度始まるという感じの構成にアレンジし直しました。
みのり:ライブでもずっとやっていた楽曲なんですが、ライブではシームレスに上がっていく形で。曲のリリースタイミングでレコーディングするにあたって、改めてアレンジしました。
また、アルバムを通してヒップホップやサイケデリック、エレクトロニカ……たくさんの要素が混ざって、このバンドだけのサウンドになっています。
蓮月:ブランデー戦記のことを全く知らない人が初めて手に取った時にどう感じるか、というところに重点を置いて考えました。ストーリー性ももちろん重視しました。普段の生活で色々な音楽を聴いて、その時一番「イケてる」、「かっこいい」と思う感覚を逃さないようにしています。曲作りの面でも、今いちばん自分がワクワクできるサウンドにしたいという思いから始めるようにしています。
例えば、「春」はノイズっぽい音から後半にかけてトラップっぽいサウンドに突入する部分が印象的でした。
みのり:蓮月がアイデアを持ってきて「どうかな?」と聞いてくれて、皆でやってみて「いいね」ってなって、取り入れました。
「悪夢のような」はMONJOEさんと一緒に制作された曲ですよね。シンセポップとブラックミュージックのムードが全面に出たサウンドが印象的でした。演奏の面でも、いつもとは違う感覚だったのでしょうか?
ボリ:実はこの曲、初めの段階から構成案はあって、アレンジしていく中で少し苦戦して、それを整えてもらう形でMONJOEさんにお願いしたんです。その後、整理されたアレンジが返ってきた、という感じの流れでした。
みのり:普段は、自分で作ったフレーズを自分で弾くので弾きやすいように作るんですけど、アレンジしてくれる方が入ると、MONJOEさんが考えたベースラインの部分もあって、自分が作ったものじゃないので手癖が合わない部分もあって、いつもとは違った感覚でしたね。
ボリ:いつも叩いてるドラムって、人間が叩いてるんで多少早かったり遅かったりがあると思うんですが、今回はなるべく精密に、極限まで……人だけど、マシーンみたいなところを狙ってやる、っていうことをやり始めた時に気づいて、「これは大変だな」って。こういうプレイスタイルもあるんだという学びになりました。
「メメント・ワルツ」は、蓮月さんにクラシックのバックグラウンドがあったからこそのアレンジだと思います。3拍子の曲ですが、いわゆるポップミュージックとは違う独特なリズム感が印象的でした。弦楽器のアレンジもすごくクラシカルに聴こえました。
蓮月:そうですね。バロックなんかもやっていたので、ヴィオラとかチェロ、コントラバスの音色はすごく好きです。特にチェロの音が好きなので、こうやって曲に取り入れられるようになって良かったなと思います。最初のデモの時点では「ワルツ」って書いていて、ズンチャッチャ、みたいなビートのイメージで、2人に「どうかな?」と聴いてもらったんです。結果、カッコよく仕上がった気はしますが、厳密にはワルツではないですね(笑)。
サウンドの方向性や曲選び、編曲については、どのように話し合っているのか気になります。
みのり:蓮月がやりたいことを詰め込んだ曲を持ってきてくれたり、皆でアレンジするときに「こういうのがやりたい」と伝えてくれたりします。選曲やアレンジは演奏しながらの時もありますし、パソコンに打ち込んでいく時もあります。
蓮月:スタジオで制作しているときも、ちょっと変なアイデアでもメンバーから出てくるアイデアはまず試すようにしています。
アルバムの初めの2曲、イギリスのドラマ『このサイテーな世界の終わり』がモチーフになった「The End of the F***ing World」と「Coming-of-age Story」は、無機質でドライに響くサウンドが10代、20代の無力感や虚しさを表現していると感じました。
蓮月:『このサイテーな世界の終わり(The End of the F***ing World)』はすごく大好きなドラマで、それを自分なりに再解釈して曲にしました。ドラマに寄り添いつつ、自分の考えも歌詞にして再解釈したという感じです。
「27:00」では、「あなたのママになりたい」という歌詞が印象的でした。ここでの「あなた」は色々な対象に解釈できると思いましたが、蓮月さんにとって「ママ」は相手の欠点を受け止めて癒せる絶対的存在で、それゆえ相手についての深い愛情が具体的な形になったのではないかと思います。
蓮月:実際に生まれ変わって母親になるとすれば、自分で産んで、最初から育てて、血は絶対に繋がっていて、というすごい強い繋がり、絆ですよね。現世では絶対に手に入れられないところまで押し進めてしまっている、というような状態を表現したかったです。
「ストックホルムの箱」は、バンド活動を通じて感じる創作への正直な気持ちが描かれているように感じました。苦しみの原因は自分の力量の問題で、でもそれが恥ずかしいから、むしろ「被害者として見られるのがいい」みたいな解釈もできるんじゃないかと。個人的には、その過程で結果的に、創作は生きる理由でもあり、お金にもなるというように聴きました。どのような気持ちで作って演奏されたのでしょうか?
蓮月:この曲は、ストックホルム症候群をテーマに作った作品です。「ストックホルム症候群」という名前の元になった事件の銀行強盗の人質側の視点に立って書いた歌詞です。そこから他の色々な意味も含めて書いていきました。今の解釈、すごく素敵だなと思いました。
「芸術」という単語が出てきて、バンドの創作そのもののことではないかと感じました。
蓮月:そうですね。そこがいきなり現実に切り換わるポイントだな、と。
アルバム全体では、自己否定からくる逃避の中で「あなた」の存在に気づき、自分を変えたいという思い、特に「Fix」や「Untitled」でそういった流れを感じました。
蓮月:歌詞については、サウンドなしでも「目で見たときに美しいか」を大事にしているので、自然とストーリー性も出てくるのかなと思います。

まさに今日(インタビューは8月18日に行われた)、新曲がリリースされました。「赤ワインに涙が」というタイトルや全体のムードが、昭和を彷彿とさせます。安全地帯の「ワインレッドの心」も思い浮かびました。また、バンジョーのサウンドがエキゾチックでした。
蓮月:この曲は、1stアルバムの曲を全て作り終わった後、結構最近に作ったものです。
みのり:バンジョー以外を全部録り終えた後に、「どうかな」と皆で話してた時に「バンジョーを入れてみるのはどうだろう」という案が出て、実際にやってみたらすごくマッチして。
普段、創作活動のインスピレーションはどこから得ているのでしょうか?
蓮月:映画が大好きで、昔からたくさん観てきました。あとは小説もよく読みます。全部を反映することはあんまりないんですが、個別のセリフや感情に反応して、それをヒントにすることはあります。
みのり:私は地理が好きなんです。路線電車とか。各地域の特徴や良さはそれぞれ違っていて、その地域を走る電車がそれぞれの地域を特徴づけるものになっていると思ってて。ツアーだと色々な場所を回るので、「どこから来たの?」と聞いてみたり、その地域に思いを馳せたりします。
ボリ:僕はゲームが好きで、インスピレーションと言っていいかはわからないですけど、ゲームって一度始めるとなかなか終わらせたくなくなるんですよね。なんでこんなに人を集中させたり、没入感を与えたりできるんだろう、どう演出されてるんだろう、と考えるようになりました。ライブでも、ワンマンとフェスは全く違います。フェスは前方に自分たちのファンが30人くらいいたとしても、後方は初めて見る人がほとんどだったりしますから。そういうとき、どういう雰囲気にしたいか、どの曲をどこに置けばどう展開できるか、周りはこうしてくるかもしれないけど、僕らはラストをこう終わらせたら唯一無二の終わり方ができるんじゃないか……そんなことを考えます。
やっぱりワンマンとフェスは違いますよね。セットリストを作る時の戦略はどう考えますか?
ボリ:僕が、こういう感じでやりたいというセットリストのたたき台を出して、「いや、こっちがいいかな」とか言いながら、テコ入れして作っていく形です。当たり前ですけど、盛り上がっているステージは見栄えがいい。でも僕らとしては、楽しみ方を強要しないということを初めの頃から決めていて、いかに自然とお客さんが熱狂できるか、どう流れを持っていけるか。その流れをどう終わらせるか。このまま突き通すのか、一気に盛り上げていくのか……。その時々の客層やステージ構成、天気、時間帯、照明の映え方まで含めて考えます。それが上手くハマった時はすごく気持ちいいですね。
ワンマンツアーが先日終わりましたね。ツアーの感想を伺いたいです。
蓮月:規模も前回の単独公演より大きくなったんですが、自分たちの中でも色々チャレンジがあって、どの公演も同じくらい心を込めてライブできたと思ってます。よかったです。
みのり:規模がすごく大きくなったことで、不安もやっぱりあったんですが……。でもお客さんを見ると、すごく楽しそうにしてくださってて、毎回の公演に色々なお客さんが来てくださって。音楽がしっかり届いてる証拠じゃないかなと思えましたし、率直に嬉しかったです。
ボリ:初日を終えてから、「すごい形が見えてきたな」という感じがしました。楽しくできたなというのもありつつ、この雰囲気を最終日までいい形に、もっと高く持っていきたい、クオリティや全体的な数値的なものも全部、最高地点に到達して終われたらな、と思いながら毎回のステージに挑んでいった気がします。
ライブの時、バンドとしてはこういう目的で作ったのに「こんなふうにも伝わるんだ」と感じたことはありますか? そういった反応は、ライブを通じてよりはっきり感じられるのではないかと思います。
蓮月:歌詞を書いてる身としては、めちゃめちゃたくさんあります。バンドを結成してから数曲リリースした段階で、「こんなにはっきり書いてるのに、全然違うふうに捉えられるんだ」と感じました。なので、そこから「もっと分かりやすい文章の書き方をしてみよう」というふうに、実際に書き方が変わったりもしました。
最後に、仁川ペンタポート・ロック・フェスティバルへの意気込み、そして先日決まった年末の韓国ワンマンライブへの意気込みをお願いします。
みのり:まず、ずっと来たかった韓国に皆で初めて来れたので、すごく嬉しいです。「韓国に行ける、嬉しい!」という感じですね。今までほぼ日本でライブをしてきた私たちが韓国でライブすることになったので、日本とは来てくれるお客さんも違うと思いますし、初めて会う方にたくさん出会える場所になると思います。自分たちの音楽を、皆さんにしっかり伝えられればいいなと思います。皆さんにお会いできるのが楽しみです。
蓮月:私もです。初めてのことなので、どうなるかわからなくて、すごくドキドキ、ワクワクしているんですけど、しっかり丁寧にやれたらいいなと思っています。とても楽しみです。
- CHANMINA「誰がどんな夢を持っていたって、恥ずかしがる理由はないんです」2025.08.18
- Suchmos、喪失を越えた先の『Sunburst』2025.08.05
- SPYAIR、危機を乗り越え新たなステージへ2025.07.08