
『ワン・バトル・アフター・アナザー』
*『ワン・バトル・アフター・アナザー』のネタバレが含まれています。
ユン・ヘイン:映画『ワン・バトル・アフター・アナザー』で、パーフィディア・ビバリーヒルズ(テヤナ・テイラー)とパット・カルフーン(レオナルド・ディカプリオ)は急進的な革命組織「フレンチ75」の隊員であり、恋人同士でもある。理想のためには武力行使も辞さない2人の革命生活は、パーフィディアの妊娠を機にきしみ始める。育児よりも革命の最前線で活動したいパーフィディアと、家長としての暮らしに専念したいパットはぶつかる。これによって衝動性が極限に達したパーフィディアは、銀行で金を奪おうとする最中、セキュリティに発砲し、逃走の末に捕まってしまう。投獄の危機に瀕したパーフィディアは、以前から自分に執着し、脅しをかけ、関係を持ったスティーヴン・ロックジョー警部(ショーン・ペン)に仲間たちの情報を渡す見返りとして、証人保護プログラムに入る。一方、パットとパーフィディアの娘はフレンチ75の助けによってボブ・ファーガソンおよびウィラ・ファーガソン(チェイス・インフィニティ)という新たな身分を得て、架空の都市バクタン・クロスに身を潜める。
16年後、国境地帯の不法移民収容所を管理するロックジョー警部は、純血主義に取り憑かれた白人上流階級男性による結社「クリスマス・アドベンチャラーズ・クラブ」に入会できるまたとないチャンスを得る。ところが入会審査での「他の人種と関係を持ったことがあるか?」という問いが彼の足を引っ張る。彼は、パーフィディアの娘ウィラが証拠になってしまうことを恐れ、2人の母娘を探すべく軍をバクタン・クロスに送り、それなりに穏やかな暮らしを送っていたボブとウィラはロックジョー警部に追われる身となる。映画は、その一部始終をブラックコメディー・タッチで描く。たとえば、ボブと娘の危機を知らせるために電話をかけてきたフレンチ75が、昔のマニュアルどおりホットラインのパスワードを言わなければ情報は渡せないと繰り返すと、ボブはこう答える。「今、ヤクをやってて朦朧としてるんだ。どれだけ月日が経ったと思ってるんだ。ヒントをくれよ」。ドラッグと酒に溺れ、娘に朝食を用意させるボブを見ていると、彼が娘を救うどころか自分の身を守れるのかすら不安になるほどだ。また、16歳の少女を探すために高校のダンスパーティーに軍隊を投入するロックジョー警部や、人種的優越があたかも実在するかのように真顔で語り合う「クリスマス・アドベンチャラーズ・クラブ」の姿は失笑を誘う。
しかし、その滑稽な純血主義者たちがバクタン・クロス住民の生活を脅かしている現実がある。フレンチ75が過去の理念に囚われてパスワードに拘泥する一方、移民のための地下脱出網を無償で提供するセルジオ・セント・カルロス(ベニチオ・デル・トロ)とその家族は、日常そのものを革命のように生きている。そうして映画は、ユーモラスに現実を突き続けると同時に、社会の側面をドキュメンタリーさながらに描き出す。『ワン・バトル・アフター・アナザー』はその題名のとおり、全編を通して人種や階級によってレイヤーや重みの異なる闘いを繰り返す。そして、ポール・トーマス・アンダーソン監督は、ウィラを通して次世代が立つ場所にまで手を伸ばす。ウィラは母の革命家的な遺伝子を受け継ぎ、10代の子供として大人たちの助けと保護を受けているが、それは前世代のレガシーをそのまま継承するという意味ではない。それゆえウィラは、親世代とは異なるやり方で戦っていくはずだ。映画の後半、起伏の激しい道路で自分を追ってきた「クリスマス・アドベンチャラーズ・クラブ」の一員を、彼女が予想外の方法で痛快に片づけてみせたように。逆らえない波の流れである。
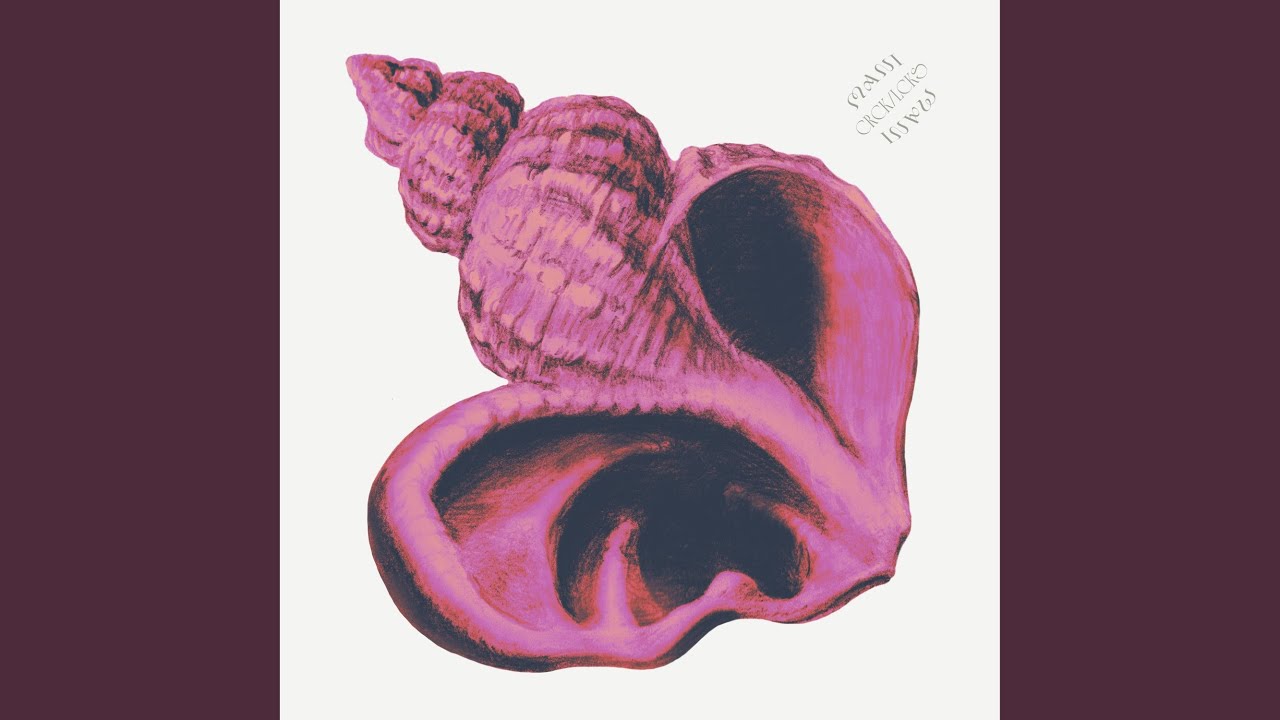
「まにまに」 - CRCK/LCKS
ファン・ソノプ(ポピュラー音楽評論家):日本の音楽界を相当チェックしていると自負する人々でも、CRCK/LCKS(クラック・ラックス)というバンドは多少聞き慣れないかもしれない。心配はいらない。彼らが関わった作品の数々に、知らず知らずのうちに相当触れてきたはずだからだ。ジャズを基盤にキャリアを築き、セッションやサウンドプロデュースなど、多様なポジションで現在のポップ・シーンを縦横無尽に駆けめぐるバンドメンバーらに加え、東京藝術大学の作曲科の卒業生として、坂本龍一や渋谷慶一郎以降では稀な「非クラシック系アーティスト」として名高いボーカルの小田朋美まで。それぞれが明確な個性を持つメンバーたちが、幾度もの衝突と試行錯誤、危機を乗り越え、デビューから10年、フルアルバムとしては6年ぶりのリリースとなる本作は、ついにチームとして機能し、綱渡りのようだったバランスが増幅する様子を見られる秀作だ。
以前のように、ジャズとポップの狭間でそれぞれのリズムを展開するのは相変わらずだが、以前はやや空いていた間隔を埋めるのは「信頼」という接着剤だ。自由なアドリブが生み出す奇跡のような有機性は、荒涼としていながら神秘的だ。聴く者の前に、共存不可能に思える風景を広げてみせる。無理に歩調を合わせて歩くわけではないが、長い歩みの果てに自ずと重なってしまう偶然のような一歩が、カタルシスをもたらす完成形とでも言おうか。ドラムとベースが暴走し、脈絡のないサックスが駆け回り、ギターは乾いたリフを反復する。その綱渡りの上に、ポップなボーカルと旋律を重ねた「まにまに」は、このアルバムのカラーを最も鮮明に示す曲だと言える。「何者かになってやる」という意志を手放したら、それまでなかった「何か」になってしまうというアイロニー。各々がそれぞれの方向へ力強く伸びていくことによって成立するこのクロスオーバー・ミュージックに触れると、先日、Suchmosの復帰コンサートでYONCEが観客に向けて投げかけた言葉がふと頭をよぎる。
「みんなで一つに、なりません。なっても意味がありません。」
『失敗した夏休み』 - ホ・ヒジョン
キム・ボクスン(作家):作家ホ・ヒジョンのデビュー短編集『失敗した夏休み』を紹介しよう。先日、ノーベル文学賞作家ハン・ガンの最新作を訳したペイジ・モリスが英訳を手がけた訳書が刊行され、本作は海外でも注目を集めている。収録された作品は、ひと言で言えば「奇異な魅力」を放つ。SFと超現実の狭間に位置する短編の数々は、明るく軽快な雰囲気とは程遠い。本のタイトルが示唆するように憂鬱な色合いを帯びてはいるものの、その暗がりの中にむしろ独特の面白さを見いだすことができる。ただし、少々露骨な描写があるため、読む前に心の準備はしておきたい。
作品の大半は、単純な解釈を許さない。物語は予想を軽々と飛び越え、時間は非連続に流れ、登場人物と背景は、匿名性の中で読者を緊張させる。テーマは多様だが、その中で「ファンダム」を扱った短編は比較的はっきりしたメッセージを投げかけている。もっとも、その意味に誰もが同意するとは限らない。全編を通して反復される「執着」という主題は、作品が要求する没入度の深さを物語っている。しかし、本作が真に掘り下げるのは、夏の陽光に照らされた軽やかな物語ではなく、その反対側に立つ感情、「孤独」である。
- 『SHOTAROのデザート』、穏やかな瞬間のマリアージュ2025.10.17
- CORTISが見せてくれる青春2025.10.02
- 『顔』、時代の空気と対峙する旅路2025.09.26