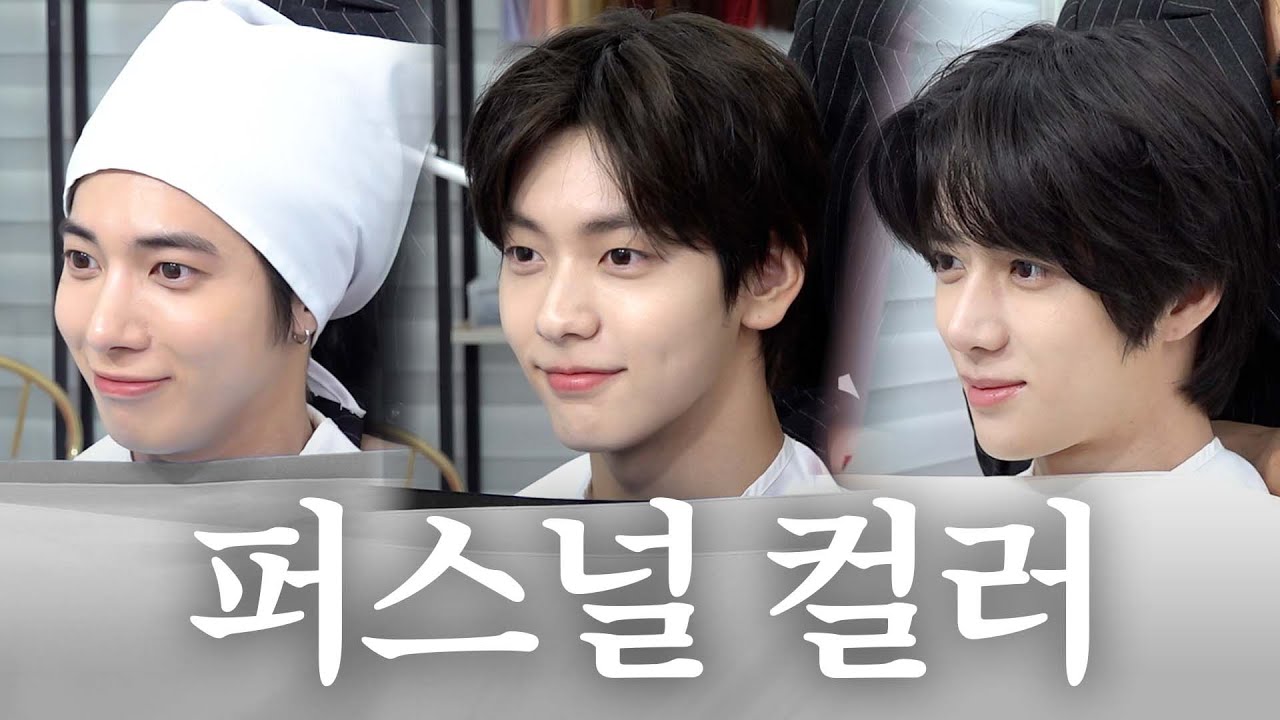
『NOT TO DO』(TOMORROW X TOGETHER 公式YouTube)
チョン・ダナ(客員エディター):「本格的に楽しむだけの撮影、NOT TO DO」。TOMORROW X TOGETHERのオリジナル・コンテンツ『TO DO』のアレンジであり派生コンテンツとして企画された『NOT TO DO』。『TO DO』オープニングの掛け声から音を逆に下げていく『NOT TO DO』の掛け声のように、『NOT TO DO』は『TO DO』とは違って、メンバーたちがミッションに挑まない。つまり、メンバー自身がやり遂げるべき「TO DOリスト」が存在しないのだ。彼らはMOAが望み、スタッフたちが用意したコンテンツを存分に楽しむだけだ。
10月20日に公開された『NOT TO DO』EP.1では、SOOBINとBEOMGYUが占術家のパク・ソンジュンに会い、人相と四柱推命の鑑定を受ける。これによって、それぞれの他メンバーとの相性やTOMORROW X TOGETHERの未来を占いながら、1人の個人と5人のグループが調和する「ケミストリー」を確認できた。10月27日に公開された『NOT TO DO』EP.2では、TAEHYUNとHUENINGKAIが精神科医キム・チョンギのもとを訪れ、TCI、絵画、脳波、自律神経系の検査を通じて、互いを客観的に知る時間を持った。「一人での食事が難しい」と素直に語るTAEHYUNや、忘れたい記憶について正直に話すHUENINGKAIの姿によって、アーティストである以前にひとりの人間として魅力的な彼らの姿が垣間見える。「実際はそうじゃないのに、『そんなこともある』と言うことがかなり多かったんです」と話すTAEHYUNのように、メンバーの率直な姿は彼らが20代の若者たちであることを示し、視聴者との距離を自然に縮める。同時に、それぞれ別の治療プロセスの途中で起きる愉快なエピソードは、TOMORROW X TOGETHERならではのバラエティー感覚を最大化させる。11月10日に公開された『NOT TO DO』最後のエピソードでは、SOOBIN、BEOMGYU、TAEHYUNがパーソナルカラー・コンサルタントのイ・セリョンによる診断を受ける。各メンバーのベストカラーやセカンドカラー、ワーストカラーを知る過程で、普段パーソナルカラーとは縁遠いSOOBINのクローゼットとイ・セリョンによるアドバイスのコントラストが笑いを誘う。各エピソードの最後に、メンバーがコンテンツ体験の感想を歌にしたアドリブ曲が挿入されるのも『NOT TO DO』のちょっとした見どころだ。
TOMORROW X TOGETHERは、『NOT TO DO』でミッションを遂行する代わりに、これまでやったことのない何かに取り組みながら自分自身を知っていき、気づけばデビュー6周年を迎えたチームの安定した関係性をいま一度確かめる。今回、最年長のYEONJUNが1stミニアルバム『NO LABELS : PART 01』活動のため参加できなかったことは惜しまれるが、それにもかかわらず『NOT TO DO』は共に楽しむ姿そのものによって、明日も共に歩むTOMORROW X TOGETHERのエネルギーを見せてくれる。結局、その姿自体がTOMORROW X TOGETHERとMOAの「TO DOリスト」を完成させたとも言えるだろう。

『国宝』
ペ・ドンミ(映画専門誌『シネ21』記者):1964年、ぼたん雪の降り積もる長崎のある新年会。任侠の家に生まれた組長の息子・喜久雄(黒川想矢)は、家族や組員たちの前で歌舞伎を披露する。生まれながらにして美しい少年は女方としての才能が抜きん出ており、著名な歌舞伎俳優・花井半二郎(渡辺謙)の目にも留まる。しかしその新年会で抗争が起こり、喜久雄は父を失う。天涯孤独となった彼は母の遺言に従い、歌舞伎役者になるために花井家へと引き取られる。喜久雄は半二郎の息子で同級生の俊介(越山敬達)とともに稽古に励み、俳優として、そして大人として成長していく。
映画『国宝』は、1964年から2014年にかけての一人の芸術家の50年にわたる人生を追う。子どもの頃は寝る間も惜しむほど歌舞伎に没頭した喜久雄は、青年期になると歌舞伎の血筋を持つ俊介への劣等感に苛まれる芸術家になり、有名になると成功のために身近な人々を失望させる未熟な人間へと転落する。約3時間にも及ぶ長尺で、李相日監督は喜久雄の経験する流転の人生を細やかに描写し、技量としての芸術に始まり、技を超えた芸術について思索する。いっそう深まる喜久雄の芸術性は、彼が演じる歌舞伎によっていっそう強調される。宮女に身をやつした姫が、関所の番人に化けた悪人を討つ『積恋雪関扉』を上演した喜久雄は、藤の精が悲しみと片思いを詠う『二人藤娘』に挑戦し、恋に落ちた二人の女が嫉妬に狂い、蛇と化す『二人道成寺』、結ばれぬ男女が心中する『曾根崎心中』を演じるに至る。
在日コリアンである李相日監督が手がけた『国宝』は、観客動員1200万人を突破し、日本の実写映画歴代興行1位更新を目前にしている。それほど親切かつ大衆的な語り口で観客に歩み寄る作品だ。一方で、複雑でありながら美しい俳優を描くアフォリズムのような台詞は格別に心に残る。日常に比べて舞台はあまりにも美しく、その中で俳優は刹那の劇的瞬間を生き、全身全霊で感情を表現する。喜久雄を指した「正月を迎えたような」、「良いことが起こりそうな」という表現は、俳優という蜃気楼をまなざす大衆の感情を鋭く看破している。

「Grabbing with both feet」 - ウ・ヒジュン
ナ・ウォニョン(ポピュラー音楽評論家):安部公房『砂の女』の冒頭で、語り手は砂の不毛さを「絶えざる流動によって、いかなる生物をも、一切うけつけようとしない点」、つまりどれだけ集めたとしても固定されえない流動性にあると説く。ベーシストでありシンガーソングライターのウ・ヒジュンにとって、人生とその「真実」は、足の指の間に挟まるざらついた砂の塊のようなものなのかもしれない。生きていると信じる何かをつぶさに観察してみると、そこにあるのは絶え間なく動く粒子だけで、そのいくつかが勝手に跳ねたり止まったりした瞬間、死になるのだから。彼女が季節ごとに1枚、今年すでに3枚目となるリリースを続けるプロセスは、言うなればこうした人生の真実を耐えようと、崩れ落ちる砂の城を何度も築き直す試みのようにも聴こえる。すべてのアルバムの核となるインストゥルメンタルを聴くと、サウンドの中心でベースギターが躍動する心臓のように重く響き、その周囲にエレキギターの多様な音色から捉えられたあらゆるノイズまでが、腸のように生々しく絡み合ってざわめく。以前ユーラ(youra)の音楽について表現したように、その光景は意外にもグロテスクで、それゆえ不毛の砂丘に築いた人工物らしい異様な生命力を帯びる。
今回のEPでは、『Ah, the grits of truth sting my feet... and it prickles!(ああ、真実という砂粒が足の裏を刺して痛い!)』というタイトルに相応しく、プロデューサーであるkhcが実際に鼓膜を刺すような無数の音のかけらを撒き散らしている。前作が複数の演奏者やミュージシャン仲間による楽器で構成されていたのとは異なり、今回はそうした音がデジタルな砂粒さながらに細かく砕け、流動的に漂いながら音響の人工美を静かに高める。短く鳴るベースの基音、落ち着かない管弦楽器、正体不明の日本語のサンプリング、壊れたようなアコギサウンド、うごめくようなコーラス、湿気のないざらついた質感――好奇心をそそるようにひしめく「私は永遠に分からないもの」。ダブルタイトル曲「Grabbing with both feet」は、ほぼ一息に流れる最初の3トラックの終着点として、散発的に聴こえていた粒のような音がいつの間にか豊かに調和し、幼い子供が砂遊びで土をしっかり固めて塊を作るように、音響の密度を徐々に高めていく。音は絶えず流動し、言語では決して固定できない。しかし、それらをあれこれと混ぜ合わせれば、「人生を支えてくれる卓越した嘘」がほんの短い瞬間であれ立ち上がることがある。ざわめきながら一時的に人工の命をなす音楽とともに、ウ・ヒジュンが口ずさむように「両足で地面をつかまなければ 存在は飛んでいく」のだから。だからこそ私たちは、砂場の真ん中で足指の間からこぼれ落ちる粒を、どうにか掴んで固めようともがき続けているのだ。
- 『匿名の恋人たち』、匿名で綴る愛のレシピ2025.11.14
- 『ジャスト・メイクアップ』、メイクアップの境界を壊す2025.10.31