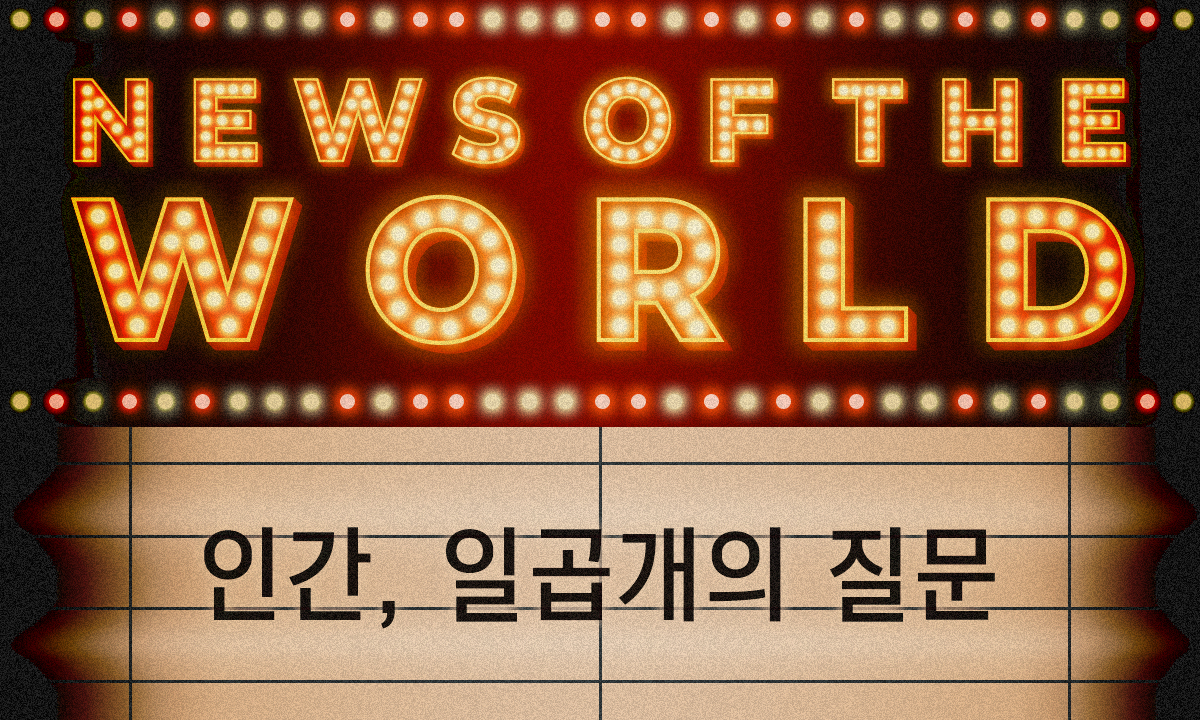
イ・ゴンヒコレクションで今年大きな話題になったサムスンのリウム美術館が、去る10月8日、4年ぶりの企画展『人間、7つの問い』で再開館することを発表した。新型コロナウイルス感染症の影響で1年7か月の間休館していたリウム美術館は、世界的な建築家マリオ・ボッタ、ジャン・ヌーヴェル、レム・コールハースの3人により建築設計され、古美術から現代の美術まで幅広く膨大な量の所蔵品により、韓国最大の私立美術館の地位を確立している。50名余りの作家と130点余りの作品を公開する今回の展示について、主催側は、21世紀の急変する環境とパンデミックの状況の中で人間として存在することの意味を再考すると同時に、未来の予想を試みると紹介している。それゆえ、人間という大きなテーマに関する7つの問いで進められる今回の展示を通して、この時代を構成するものの存在と関係について深く考えることのできる時間を持つことになるだろう。
「人間という存在を定義できるだろうか」という問いから始まる『鏡を見る』の章では、今の時代の人間についての深い思考を扱っている。不完全さを認め、他者との関係を通じて証明される私たちの有限性は、これまでの人間の歴史について振り返り、これからの世界において私たちが他者とともに生きていく方向性について考察させる。美術館の展示紹介映像や来場者たちの記念写真の中に多く見られる代表的な作品として、ロン・ミュエックの『Mask Ⅱ』が登場するのも、そのような私たちの「生」の深さを肌で感じられるからだろう。
続く2章と3章は、『開かれた体』と『歪んだ体』を通して、現代美術において重要なものとして扱われる体についての議論を扱う。生と世の中を直接受け入れる私たちの体は、21世紀に入り核心的な表現手段となった。それにより芸術における行為は、これまで抑圧されてきた要素をさらけ出す。一方『歪んだ体』では、私たちが経験する世の中の非理性的な影にスポットを当てる。依然として私たちとともにある戦争と暴力、死のイメージは、私たちの変種的な形態として表現され、問題意識を提起する。
だとしたら、私たちはどんな方向に進んでいくべきなのか。4章と5章の『みんなの部屋』と『傷つきやすい私たち』で、その方向を模索する試みを見つけることができるだろう。最近の私たちに主に迫っている嫌悪と偏見、差別の問題を扱っており、それに対する抵抗と多様性の尊重を通して今向き合っている問題から抜け出し、皆のための芸術により平等を渇望する。そうして私たちが互いから隔離され疎外される現実から、関係の克服へと進んでいけるだろう。だが今回の展示における視点は、単に人間の関係を考えることにとどまらない。
6章と7章のテーマである『超越の熱望』と『不慣れな共生』では、未来志向的な私たちの生き方を考えるきっかけを提供してくれる。科学技術の発展により限界を超越する時代に至ったが、人工物が人間に取って代わる現実の中で、変わりゆく人間の存在の意味と向き合うことになった。それと同時に私たちは、人間だけの、人間中心の思考から抜け出し、この世界の多様な存在と共存する方向を模索しなければならない、時代的な課題を要求されている。多様な存在とともに生きていき、新たな生態系を提案しようとする試みは、展示会場の中のテーマを越え、新たな共同体について語ったジャン=リュック・ナンシーや、社会のすべての関係についての方法論を提示したブルーノ・ラトゥールのような、この時代の知性たちの哲学的思考とも相接しているのだろう。
そのように今回の展示は、単に人間のためだけの芸術ではなく、私たちが人間として生きていくための人間らしさについて再考させ、過去の二分法的な思考をやめ、水平関係の時代を目指す芸術に没入させる。そうして単一の種として生きていく人間の世界ではなく、すべての存在がともに未来を望める関係について、真剣に考えることのできる時間として残るだろう。
-
 ©️ Leeum Museum of Art
©️ Leeum Museum of Art
トリビア
ロン・ミュエック(Ron Mueck)
オーストラリア出身のハイパーリアリズム彫刻家。彼の作品は繊細な人体表現を通して、人間の生と死をテーマに私たちの根源的考察を盛り込む。リアルな描写だが実際とちがうスケールによって、私たちは鏡の中の見慣れぬイメージを発見したかのように、客観化された私たちの生の姿を見ることができる。
無断転載及び再配布禁止
- [NoW] アンディ・ウォーホルにつながるパーティー会場2021.04.09
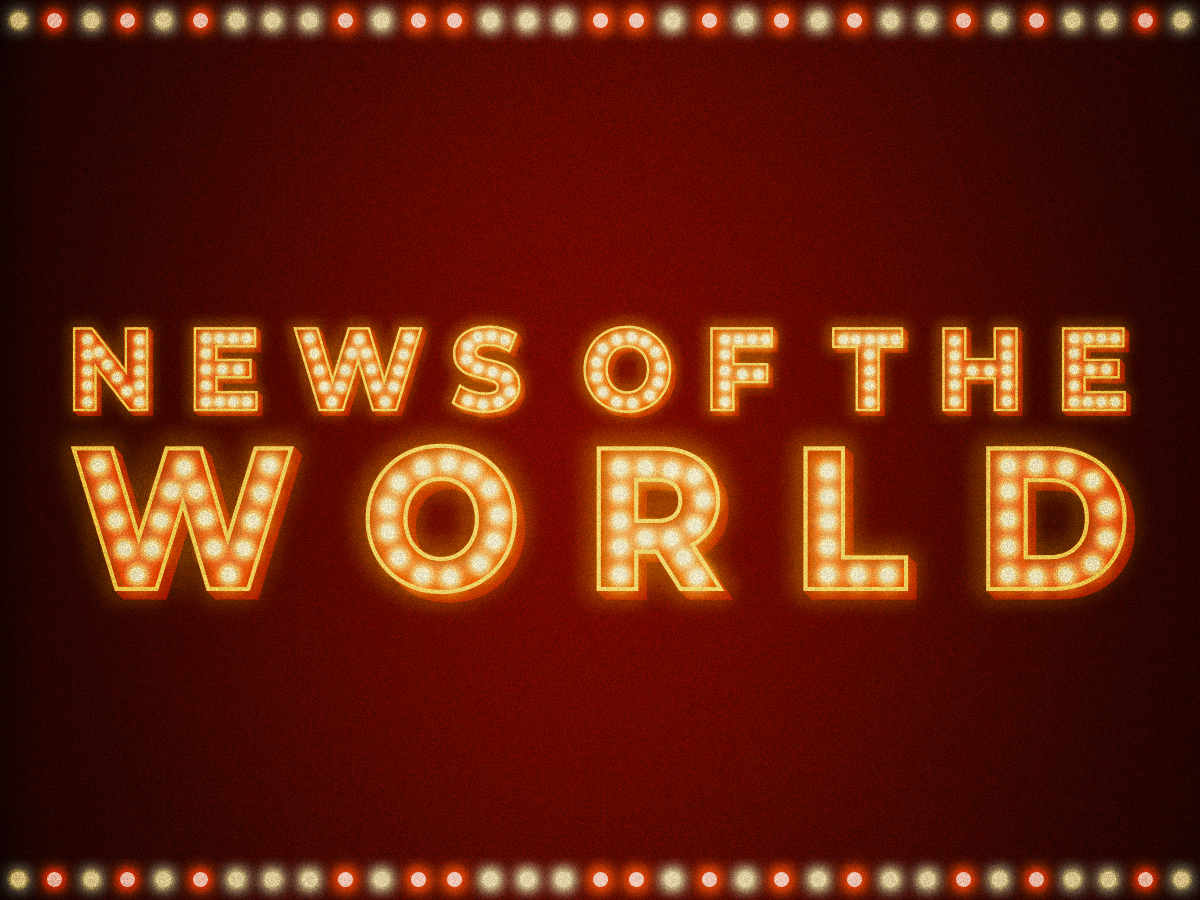
- [NoW] LEE BUL:Beginning2021.05.07

- [NoW] ピカソの永遠の情熱2021.06.04

- [NoW] リヒターの色と光2021.07.02

- [NoW] バンクシーの自由、平和、正義2021.07.30

- [NoW] イ・ゴンヒコレクション特別展『ウェルカム・ホーム:饗宴』2021.08.27

- [NoW]アリス・ダルトン・ブラウン2021.09.24

- [NoW] サルバドール・ダリ、現実と非現実の境界2021.10.22
