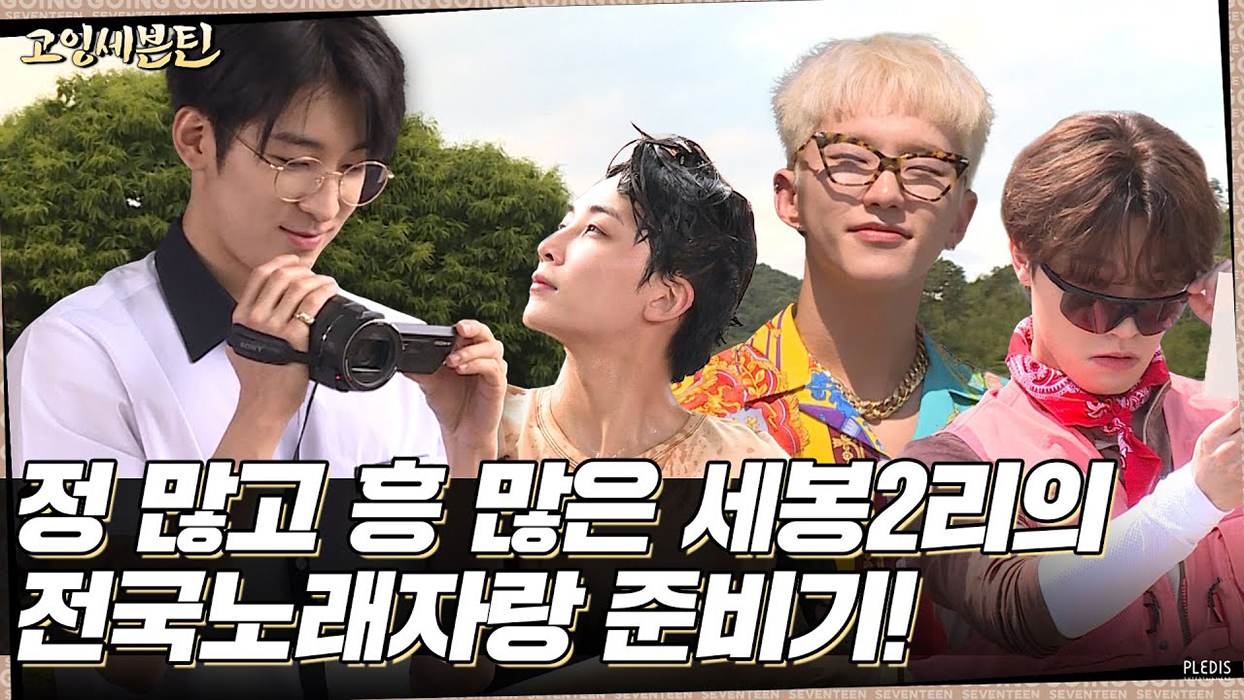Credit
文. イム・スヨン(映画専門誌『シネ21』記者)、ランディ・ソ(ポピュラー音楽解説者 Music Writer)、カン・ミョンソク, キム・ギョウル(作家)
デザイン. チョン・ユリム
写真. SEVENTEEN Youtube
『HUNT』
イム・スヨン(映画専門誌『シネ21』記者):『HUNT』はイ・ジョンジェの初演出への挑戦、そして「清潭(都心の一等地)夫婦」と呼ばれるチョン・ウソンと共に『太陽はない』(1999)以来、23年ぶりの再会となる作品。この作品はトップスターの人気に支えられ、演出デビューも主演のキャスティングも簡単に進んだという誤解をこれ見よがしに覆す。映画の現場経験だけで28年に上るイ・ジョンジェは、商業映画をどう撮ればいいかわかっている専門家だ。1983年、国家安全企画部に潜入したスパイ「ドンリム」を割り出すという任務を任された海外チームの次長パク・ピョンホ(イ・ジョンジェ)と国内チームの次長キム・ジョンド(チョン・ウソン)が自分の生存のために瀬戸際でチキンゲームを始める。『HUNT』はアウンサン廟で発生したテロ事件をモチーフにしているものの、実話に囚われない想像力を果敢に発揮する。そのおかげで、観客が歴史の再現に求める倫理的負担を下ろし、時代背景に冷戦、情報機関、疑念と裏切りの情緒を最大化した後、スパイ・アクション物の舞台にする。それに合わせ、さまざまな集団で起こるジレンマ、結果のために過程の欠如を正当化する矛盾を捉え、普遍的な問いを投げかける。同時代の韓国に送る注釈とも取れる、監督イ・ジョンジェの驚くべきデビュー作だ。
「MORE」 - J-HOPE
ランディ・ソ(ポピュラー音楽解説者 Music Writer):7月の1か月はずっと「ホープ・ワールド(Hope World)」だった。BTSのソロ活動期、「チャプター2」のトップバッターであるJ-HOPEは、仰天するほどよくできているセルフ・プロデューシング・アルバムで世界に二度目のお目見えとなった。先行公開曲「MORE」は、本腰を入れ準備した彼の初めての正式アルバムに対する期待感を高めるには充分だった。彼の代表的な武器と言えるダンスをしまっておいた点にも驚いたが、コーラスにグランジなロック・バンド・サウンドで勝負をかけた点は新鮮な衝撃だった。BTSの初期にもシャウティング・スタイルのラップで自身の位置を強固にした彼は、新しいソロ・キャリアの始まりでもこのように「叫び」で自身の存在感を示す。彼がアルバム発売前に予告した暗い欲望のナラティブは、俗に男性歌手がキャリアを切り替える時に掲げる「暗い(と書いて『汚い』と読む)欲望」のようなアプローチとはちがう様子だ。極度の向上心とその裏で消耗されていく魂を両方とも観察したこのアルバムは、まさに自分のためのことが自己破壊につながったりもする、人間の単純でありながら避けられないアイロニーを表した。その頭出しとして「MORE」は、この上なく効果的な始まりだった。
『GOING SEVENTEEN』の中の「WONWOO日記」+「8月のクリスマス」
カン・ミョンソク:SEVENTEENのオリジナル・バラエティ・コンテンツ『GOING SEVENTEEN』の「WONWOO日記」は、WONWOOによると(Weverseで明かした)メンバーに大まかな状況だけが与えられたまま、アドリブで展開されたコントだった。アイドルが2本のエピソードで1時間余りの尺でコントを披露できるのも不思議だが、その内容はさらに摩訶不思議だ。ビデオで農村「セボン2里」の日常を撮る学生WONWOOの視線をたどっていくコントは、『田園日記』をパロディした農村ドラマに『全国のど自慢』が加わり、『瞬間捕捉世の中にこんなことが』を経て『X-ファイル』と『ストレンジャー・シングス 未知の世界』を合体させたミステリーに『ツイン・ピークス ローラ・パーマー最期の7日間』までちらつかせる雰囲気で終わってしまう(これ以上描写したら深刻なネタバレになるほど詳細なあらすじだ)。これらすべてを絶妙に爆笑を取るタイミングより3分の1拍子遅れながら、笑いと同時に後半になるほど奇妙な違和感を生み出すメンバーの不思議なバラエティ感覚は、このグループが歌手として今年、フル・アルバムとリパッケージ・アルバムを初週で318万枚以上売り上げたあのグループなのかと、画面を拡大し確かめるようになる。
見事に笑わせた後、不気味な雰囲気を漂わせる「結末」は、CARATのさまざまな想像を生み出し、『GOING SEVENTEEN』はまるでそんな反応を予想したかのようにその翌週、納涼特集として「8月のクリスマス II」を出した。メンバーは3人か4人でユニットを組み、真っ暗な部屋の中、PCでホラーゲームをプレイする。メンバーがゲームをしながら度肝を抜かれることを期待するところだが、ゲームぐらいで驚くSEVENTEENではない。それよりWONWOOはゲームが得意で、S.COUPSはすでに試したことのあるゲームだったため、すぐに勝ち、収録を終わらせることもできたはずだが、他のメンバーもゲームを試せるように譲る。そんな中、オープニングで疲れを知らず走り回る末っ子・DINO(a.k.a. ピ・チョリン)もいる。エピソードのサムネイルに「暗い部屋で一人で視聴しないでください」という一文でいきなり脅かしてくるが、「8月のクリスマス II」はホラーゲームから表れるメンバーのキャラクターと、一人がゲームをすれば、他のメンバーが会話の間が空かないよう立て板に水のごとく自然な進行をするチームワークを見せる。そして、「8月のクリスマス II」でメンバーの普段の姿を知った上で「WONWOOの日記」を見返すと、笑い過ぎて疲れた挙句、疑問が生じる。あのグループはどうしてあんな顔であんなことまでし、しかもあんなにおもしろいのか。それなのに、下半期に歌手として日本のドームツアーを含むワールドツアーを回る予定だという。
『くらやみの速さはどれくらい』 - エリザベス・ムーン
キム・ギョウル(作家):あなたがドラマ『ウ・ヨンウ弁護士は天才肌』をおもしろく観たのであれば、この本を読むべきだろう。自閉スペクトラム症を持つ人の一人称視点で展開されるこの小説は、2002年出版と同時に文学界に衝撃を与え、アーサー・C・クラーク賞の最終候補作にノミネートされた上、ネビュラ賞長編小説部門を受賞した。自閉症が幼少期に発見されれば、医学技術で完治できる近未来の世界、自閉症最後の世代に含まれるルウ・アレンデイルは、毎日会社に出て仕事をこなし、毎週フェンシング同好会に行くなど、自分なりの生活を営む。そういう面で彼は「正常」と思われる。しかし、彼は確かに自閉スペクトラム症を持っており、それが即ち彼のアイデンティティだ。それでは、彼は「異常」なのか。自閉症者に対する優遇を撤廃し、彼らを無理やり治療しようとする上司クレンショウやフェンシング同好会でルウのことを嫉妬する「健常者」ドンがルウを注視している。
小説を書いたエリザベス・ムーンには、実際に自閉スペクトラム症の息子がいる。この小説の出発点がそもそも息子の言葉だった。しかし、息子はルウやウ・ヨンウのような典型的な「自閉症の天才」ではない。当然ながら、人間はそれぞれちがうもので、それは自閉症者だろうがそうでなかろうが同じだ。その狭間で誰が正常で誰が異常かを我々がどのように判断できるだろうか。小説は自ずと読者をこの質問に浸らせる。読者は物語が進むにつれ、ルウの考え方に慣れていき、ひいては心地よさを感じる状態に至る。それは自閉症者の頭の中に入ってみる経験だが、またそれと同時に、すべての自閉症者の経験が同じわけではない。この事実を身にしみる思いで記憶すること、感情移入することと距離を置くことの間の多彩な経験がこの小説からの最も大切な贈り物なのだろう。もちろん、小説自体がおもしろいという点は言うまでもない。
Copyright © Weverse Magazine. All rights reserved.
無断転載及び再配布禁止